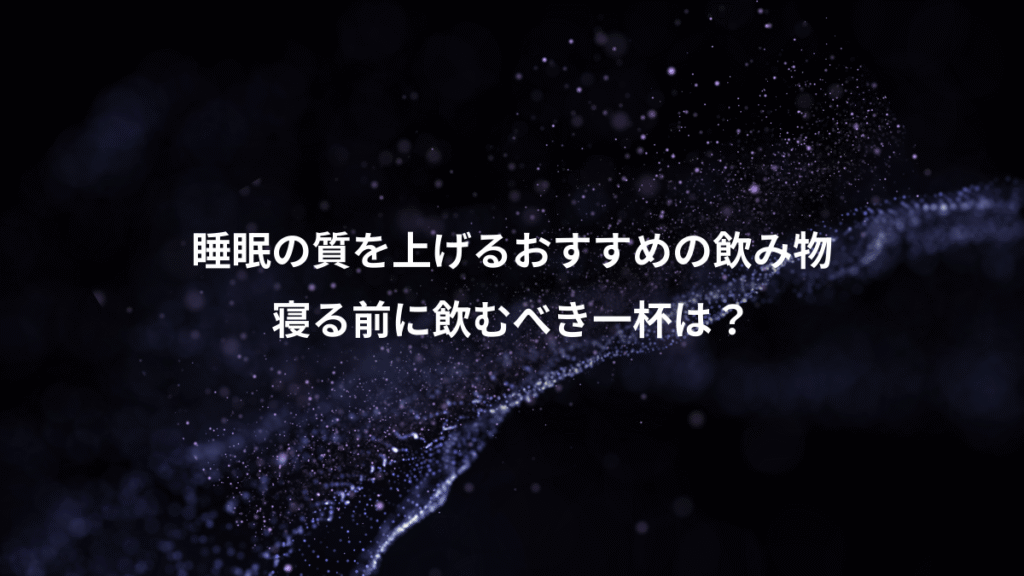「夜中に何度も目が覚める」「朝起きても疲れが取れていない」といった睡眠に関する悩みは、多くの現代人が抱える共通の課題です。質の高い睡眠は、日中のパフォーマンス向上や心身の健康維持に不可欠であり、その解決策を模索している方も少なくないでしょう。
実は、寝る前に飲む一杯の飲み物が、睡眠の質を大きく左右することをご存知でしょうか。体を温め、心をリラックスさせ、睡眠をサポートする栄養素を補給することで、私たちはより深く、快適な眠りへと導かれます。
この記事では、睡眠の質を上げる飲み物の効果や関連する栄養素について科学的な視点から詳しく解説します。さらに、専門的な知見に基づき厳選した「おすすめの飲み物ランキング15選」から、コンビニで手軽に購入できる機能性表示食品まで、幅広くご紹介します。
また、飲み物を飲む最適なタイミングや、逆に睡眠を妨げてしまうNGな飲み物、そして飲み物と合わせて実践したい生活習慣改善のヒントまで、網羅的に解説していきます。
この記事を読めば、あなたに最適な「眠る前の一杯」が見つかり、明日からの目覚めがよりすっきりとしたものになるはずです。ぜひ、自分に合った方法を見つけるための参考にしてください。
目次
睡眠の質を上げる飲み物の効果とは?

寝る前に温かい飲み物を飲むと、何となくリラックスできてよく眠れるような気がする、という経験は多くの人にあるかもしれません。その感覚は、実は科学的な根拠に基づいています。睡眠の質を上げる飲み物には、主に「体を温める効果」「リラックス効果」「栄養補給効果」という3つの大きな役割があります。これらの効果が複合的に作用することで、私たちはスムーズな入眠と質の高い睡眠を得られるのです。
ここでは、それぞれの効果が具体的にどのようなメカニズムで私たちの睡眠に働きかけるのかを、専門的な視点から詳しく解説していきます。
体を温めて入眠しやすくする
私たちの体には、「深部体温」という脳や内臓など体の中心部の温度を測る指標があります。人間は、この深部体温が低下する過程で自然な眠気を感じるようにプログラムされています。日中の活動時間帯は高く保たれている深部体温が、夜になるにつれて手足の末端から熱を放出(熱放散)することで徐々に下がり、体が休息モード、つまり睡眠状態へと移行するのです。
この体のメカニズムを効果的に利用するのが、寝る前に温かい飲み物を飲むという習慣です。
就寝の1〜2時間前に温かい飲み物を摂取すると、一時的に体の中から温められ、深部体温がわずかに上昇します。その後、体は上昇した体温を元に戻そうと、手足の血管を拡張させて血行を促進し、熱を体外へ効率的に放出しようとします。この意図的に作られた体温上昇と、その後のスムーズな体温低下のプロセスが、強力な眠気を誘発するのです。
特に、普段から手足が冷えやすく、なかなか寝付けない「冷え性」の方にとって、この方法は非常に有効です。冷え性の人は末端の血行が悪いため、熱放散がうまく行われず、深部体温が下がりにくい傾向があります。温かい飲み物で内側から血行を促進することで、この問題を解消し、自然な入眠をサポートできます。
ただし、注意点もあります。飲み物の温度が高すぎると、体を興奮状態にする交感神経が刺激されてしまい、逆効果になる可能性があります。また、やけどのリスクも考えられます。理想的な温度は、50〜60℃程度の人肌より少し温かいと感じるくらいです。ゆっくりと時間をかけて飲むことで、体への負担も少なく、リラックス効果も高まります。
リラックス効果で心を落ち着かせる
現代社会では、仕事のプレッシャーや人間関係のストレス、将来への不安など、多くの精神的ストレスに晒されています。こうしたストレスは、自律神経のバランスを乱す大きな原因となります。
自律神経には、体を活動的にする「交感神経」と、リラックスさせる「副交感神経」の2つがあります。質の高い睡眠を得るためには、就寝時に副交感神経が優位な状態になっていることが不可欠です。しかし、ストレスや緊張状態が続くと交感神経が優位なままとなり、「ベッドに入っても頭が冴えて眠れない」「考え事が止まらない」といった状態に陥ってしまいます。
ここで役立つのが、リラックス効果のある飲み物です。特定の飲み物に含まれる香りや成分、そして「温かいものを飲む」という行為そのものが、心身の緊張を和らげ、副交感神経を優位に切り替える手助けをしてくれます。
例えば、カモミールやラベンダーといったハーブティーの香りには、アロマテラピー効果があり、嗅覚を通じて脳に直接働きかけ、鎮静作用をもたらします。また、牛乳やホットココアをゆっくりと飲むという行為は、幼少期の安心感を呼び覚ます心理的な効果(プライミング効果)も期待できると言われています。
さらに、温かい飲み物が胃腸に入ることで内臓が温まり、副交感神経が刺激されやすくなるという側面もあります。このように、飲み物がもたらすリラックス効果は、単なる気分の問題ではなく、自律神経の働きに直接的・間接的にアプローチし、睡眠に適した心身の状態を作り出すための重要なプロセスなのです。
日中の緊張を夜まで引きずりがちな方や、心配事で頭がいっぱいになってしまう方は、ぜひ寝る前のリラックスタイムとして、お気に入りの一杯を取り入れてみることをおすすめします。
睡眠をサポートする栄養素を補給する
私たちの睡眠は、「メラトニン」というホルモンによって大きくコントロールされています。メラトニンは「睡眠ホルモン」とも呼ばれ、体内時計を調整し、自然な眠りを誘う働きをします。このメラトニンは、日中に分泌される「セロトニン」という神経伝達物質を原料として、夜間に脳の松果体という部分で生成されます。
つまり、質の高い睡眠のためには、原料となるセロトニン、そしてそのまた原料となる栄養素が体内に十分に存在することが前提となります。その代表的な栄養素が「トリプトファン」という必須アミノ酸です。
このトリプトファンをはじめとして、睡眠の質を向上させるためには、以下のような様々な栄養素が関わっています。
- グリシン: 深部体温を下げ、睡眠の質を高めるアミノ酸。
- GABA(ギャバ): 脳の興奮を鎮め、リラックス効果をもたらす神経伝達物質。
- テアニン: 緑茶に含まれるアミノ酸で、リラックス状態を示すα波を増加させる。
- マグネシウム: 神経の興奮を抑え、筋肉の弛緩を助けるミネラル。
- カルシウム: イライラを鎮め、精神を安定させる効果があるミネラル。
これらの栄養素は、日々の食事から摂取することが基本ですが、不足しがちな場合や、より積極的に睡眠の質を改善したい場合には、寝る前の飲み物で手軽に補給するのが非常に効率的です。
例えば、ホットミルクからはトリプトファンとカルシウムが、アーモンドミルクからはマグネシウムが、特定の機能性表示食品からはGABAが摂取できます。このように、自分の食生活や体調に合わせて、不足している栄養素を補える飲み物を選ぶことで、より戦略的に睡眠の質を高めるアプローチが可能になります。
次の章では、これらの睡眠をサポートする主要な栄養素について、一つひとつ掘り下げて詳しく解説していきます。
睡眠の質向上に役立つ主な栄養素
睡眠の質を高める飲み物を理解する上で、その中に含まれる有効成分、つまり「栄養素」の働きを知ることは非常に重要です。なぜその飲み物が睡眠に良いのか、その科学的根拠を把握することで、より自分に合った一杯を選べるようになります。ここでは、特に睡眠との関連が深い代表的な4つの栄養素「グリシン」「トリプトファン」「GABA」「テアニン」について、そのメカニズムと効果を詳しく解説します。
| 栄養素 | 主な働き | 特徴 |
|---|---|---|
| グリシン | 深部体温を低下させ、ノンレム睡眠(深い眠り)の時間を増やす | 末梢の血流を増加させることで、体の中心部の熱を効率的に逃がす。 |
| トリプトファン | 睡眠ホルモン「メラトニン」の原料となる | 体内で生成できない必須アミノ酸。セロトニン(精神安定)を経てメラトニンに変化する。 |
| GABA | 脳の興奮を鎮め、心身をリラックスさせる | 抑制性の神経伝達物質。ストレスや不安を和らげる効果が期待される。 |
| テアニン | リラックス状態を示す脳波「α波」を増加させる | 緑茶のうま味成分。覚醒作用のあるカフェインの働きを穏やかにする効果も。 |
グリシン
グリシンは、私たちの体を構成するタンパク質の元となるアミノ酸の一種です。体内で合成できる「非必須アミノ酸」に分類されますが、睡眠に対して非常に特徴的な働きを持つことが近年の研究で明らかになっています。
その最大の効果は、スムーズな入眠を促し、睡眠の質を向上させる点にあります。前述の通り、人は深部体温が下がることで眠気を感じます。グリシンには、手足などの末梢血管を拡張させ、血流を増やす作用があります。これにより、体の中心部にこもった熱が効率的に体外へ放出され、深部体温がスムーズに低下するのです。
ある研究では、就寝前にグリシンを摂取したグループは、摂取しなかったグループに比べて、ベッドに入ってから眠りにつくまでの時間(入眠潜時)が短縮され、ノンレム睡眠、特に最も深い眠りである「徐波睡眠」の時間が長くなったことが報告されています。これは、グリシンが単に寝つきを良くするだけでなく、睡眠の「質」そのものを深める力があることを示唆しています。
さらに、グリシンを摂取した翌朝は、眠気や疲労感が少なく、日中の作業効率が向上したというデータもあります。これは、夜間の睡眠が深くなることで、脳と体がしっかりと休息できた結果と考えられます。
グリシンは、エビ、ホタテ、イカなどの魚介類や、豚足、牛すじ、鶏皮といったゼラチン質の多い食品に豊富に含まれています。飲み物で手軽に摂りたい場合は、これらの食材を使ったスープや、出汁の効いた味噌汁などがおすすめです。また、サプリメントやグリシンを添加した機能性表示食品も市販されており、より手軽に摂取することも可能です。
トリプトファン
トリプトファンは、人間の体内で生成することができない9種類の「必須アミノ酸」の一つです。食事から摂取する必要がある非常に重要な栄養素であり、特に精神の安定と睡眠に深く関わっています。
トリプトファンの最も重要な役割は、「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンと、「睡眠ホルモン」と呼ばれるメラトニンの両方の原料になることです。この一連の流れは、質の高い睡眠を理解する上で欠かせません。
- 摂取: 食事や飲み物からトリプトファンを摂取します。
- セロトニン生成: 脳に運ばれたトリプトファンは、ビタミンB6やマグネシウム、ナイアシンなどの助けを借りて、日中にセロトニンへと変換されます。セロトニンは、精神を安定させ、幸福感をもたらす神経伝達物質です。
- メラトニン生成: 日中に生成されたセロトニンは、夜になり周囲が暗くなると、脳の松果体でメラトニンに変換されます。メラトニンが分泌されることで、私たちは自然な眠気を感じ、深い眠りへと入っていきます。
つまり、日中のセロトニンが不足すると、夜間のメラトニンも十分に生成されず、寝つきが悪くなったり、夜中に目が覚めやすくなったりするのです。したがって、その大元であるトリプトファンを日頃から十分に摂取しておくことが、安定した睡眠サイクルを維持するための鍵となります。
トリプトファンは、牛乳、チーズ、ヨーグルトなどの乳製品、豆腐、納豆、味噌、豆乳などの大豆製品に特に多く含まれています。このため、寝る前にホットミルクや温かい豆乳を飲むことは、トリプトファンを補給する上で非常に理にかなった習慣と言えます。
また、トリプトファンを効率よく脳に運ぶためには、炭水化物(糖質)を一緒に摂るのが効果的です。糖質を摂るとインスリンが分泌され、他のアミノ酸が筋肉に取り込まれやすくなるため、相対的にトリプトファンが脳に届きやすくなるのです。ホットミルクに少量のはちみつを加えるのは、この点でも非常に良い組み合わせです。
GABA
GABA(ギャバ)は、γ-アミノ酪酸(Gamma-Aminobutyric Acid)の略称で、主に脳や脊髄に存在する抑制性の神経伝達物質です。興奮性の神経伝達物質(グルタミン酸など)の働きを抑え、神経の高ぶりを鎮める、いわば「脳のブレーキ役」のような存在です。
ストレス社会に生きる私たちは、常に交感神経が優位になりがちで、脳が過剰に興奮している状態が少なくありません。この興奮状態が続くと、不安感やイライラが増し、夜になってもリラックスできず、なかなか寝付けない原因となります。
GABAには、この過剰な神経の興奮を抑え、心身をリラックスさせる効果があります。GABAが脳内の受容体に結合すると、神経細胞の活動が穏やかになり、高ぶった感情や緊張が緩和されます。これにより、睡眠前に優位にすべき副交感神経への切り替えがスムーズになり、穏やかな気持ちで眠りにつくことができます。
近年の研究では、GABAを摂取することで、ストレスの軽減や睡眠の質の改善が報告されています。具体的には、寝つきが良くなる、深いノンレム睡眠の時間が長くなる、すっきりとした目覚めが得られるといった効果が確認されており、多くの機能性表示食品に応用されています。
GABAは、発芽玄米やトマト、かぼちゃ、じゃがいも、また味噌や漬物といった発酵食品に多く含まれています。飲み物では、トマトジュースや一部の青汁、そしてGABAを機能性関与成分として添加した乳酸菌飲料やサポートドリンクなどが市販されており、コンビニなどでも手軽に入手できます。
ストレスを感じやすい方や、考え事が多くて眠れないという方は、GABAの働きを意識した飲み物を取り入れてみると良いでしょう。
テアニン
テアニンは、お茶、特に玉露や抹茶などの高級な緑茶に豊富に含まれるアミノ酸の一種です。お茶の「うま味」や「甘み」の成分であり、古くから日本人に親しまれてきました。
テアニンの最も注目すべき効果は、脳波に直接働きかけ、リラックス状態を作り出す能力です。テアニンを摂取して40分から1時間ほどすると、脳波の中で、リラックスしている時や集中している時に現れる「α波」が顕著に増加することが確認されています。
このα波が増えることで、心拍数が落ち着き、血圧の上昇が抑制され、心身ともに穏やかな状態になります。これは、睡眠前の過度な緊張や興奮を和らげるのに非常に効果的です。
また、テアニンにはもう一つ興味深い働きがあります。それは、カフェインによる興奮作用を穏やかにするというものです。緑茶には覚醒作用のあるカフェインも含まれていますが、同時にテアニンも含まれているため、コーヒーを飲んだ時のような急激な覚醒感ではなく、穏やかな覚醒状態になると言われています。
ただし、睡眠の質を高める目的で寝る前に飲む場合は、やはりカフェインの影響を考慮する必要があります。そのため、カフェイン含有量が少ないほうじ茶や玄米茶、あるいは「カフェインレス」「デカフェ」と表示された緑茶を選ぶのが賢明です。もしくは、緑茶由来のテアニン成分だけを抽出したサプリメントや機能性表示食品を利用するのも一つの方法です。
テアニンは、リラックス効果だけでなく、集中力を高めたり、月経前症候群(PMS)の症状を緩和したりする効果も報告されており、日中から夜間まで幅広く私たちの心身をサポートしてくれる注目の成分です。
睡眠の質を上げる飲み物おすすめランキング15選
ここでは、これまで解説してきた「体を温める」「リラックスさせる」「栄養を補給する」という3つの効果を踏まえ、寝る前の一杯として特におすすめの飲み物をランキング形式で15種類ご紹介します。それぞれに異なる特徴や効果があるため、ご自身の体調や好みに合わせて、最適な一杯を見つけてみてください。
① 白湯
最もシンプルでありながら、非常に効果的なのが白湯です。水を一度沸騰させてから、50〜60℃程度の飲みやすい温度まで冷ましたもので、不純物が取り除かれ、口当たりがまろやかになっているのが特徴です。
おすすめの理由:
内臓を直接温めることで血行が促進され、全身がリラックスします。特に、前述した「深部体温」を一度上げてから下げるという睡眠のメカニズムをサポートするのに最適です。また、胃腸の働きを助け、消化を促進する効果も期待できます。材料は水だけなので、カロリーやカフェイン、糖質などを一切気にせず、誰でも気軽に始められるのが最大の魅力です。
飲む際のポイント:
一気に飲むのではなく、5〜10分かけてゆっくりとすするように飲むのがおすすめです。レモンや生姜のスライスを少し加えると、風味が増し、さらなるリラックス効果や血行促進効果が期待できます。
② ホットミルク
古くから「眠れない時にはホットミルク」と言われるほど、定番の安眠ドリンクです。その効果には科学的な裏付けがあります。
おすすめの理由:
牛乳には、睡眠ホルモン「メラトニン」の原料となる必須アミノ酸「トリプトファン」が豊富に含まれています。また、神経の興奮を鎮める「カルシウム」も多く、イライラや不安を和らげてくれます。温かいミルクの優しい香りと味わいが、心理的な安心感をもたらす効果も大きいでしょう。
飲む際のポイント:
トリプトファンの吸収を助ける糖質を少量加えるのが効果的です。はちみつを小さじ1杯程度加えると、栄養価も高まり、喉の痛みや咳を鎮める効果も期待できます。ただし、乳糖不耐症でお腹がゴロゴロする方は、次に紹介するアーモンドミルクなどを試してみましょう。
③ カモミールティー
「リラックスハーブの女王」とも呼ばれるカモミールを使ったハーブティーは、安眠効果で世界的に知られています。
おすすめの理由:
カモミールに含まれる「アピゲニン」というフラボノイド成分が、脳の特定受容体に作用し、鎮静効果や抗不安作用をもたらします。リンゴのような甘く優しい香りが、高ぶった神経を穏やかに鎮めてくれます。もちろんノンカフェインなので、寝る前に安心して飲むことができます。
飲む際のポイント:
ティーバッグで手軽に楽しめますが、より香りを楽しみたい場合はドライハーブ(花)から淹れるのがおすすめです。はちみつやミルクとの相性も抜群です。
④ ルイボスティー
南アフリカ原産のルイボスという植物の葉を発酵させて作られるお茶で、近年日本でも人気が高まっています。
おすすめの理由:
完全ノンカフェインでありながら、マグネシウムなどのミネラルが豊富に含まれています。マグネシウムは神経の伝達を正常に保ち、筋肉の緊張をほぐす働きがあるため、心身のリラックスに繋がります。また、強力な抗酸化作用を持つフラボノイドも豊富で、ストレスや疲労の軽減をサポートしてくれます。
飲む際のポイント:
クセが少なく、すっきりとした味わいで飲みやすいのが特徴です。ホットでもアイスでも美味しく飲めますが、睡眠のためには温めて飲むのがおすすめです。
⑤ ホットココア
ココアの甘い香りと味わいは、心を満たし、リラックスさせてくれます。
おすすめの理由:
ココアの原料であるカカオには、「テオブロミン」という成分が含まれています。テオブロミンは、カフェインに似た構造を持ちながら、その作用は非常に穏やかで、自律神経を整えてリラックスさせる効果が知られています。また、ストレスへの抵抗力を高めるGABAも含まれています。
飲む際のポイント:
市販の調整ココアは砂糖が多く含まれていることが多いので、注意が必要です。無糖のピュアココアを選び、甘みははちみつやオリゴ糖で自分で調整するのがおすすめです。また、ココアには少量ながらカフェインも含まれるため、カフェインに敏感な方は飲み過ぎに注意しましょう。
⑥ 生姜湯(ホットジンジャー)
体の冷えが気になる方、特に冬場の寝つきが悪い方には生姜湯が最適です。
おすすめの理由:
生姜に含まれる辛味成分「ジンゲロール」は、加熱することで「ショウガオール」という成分に変化します。このショウガオールには、胃腸を直接刺激して体の深部から熱を作り出し、血行を促進する強力な作用があります。手足の先までポカポカになり、スムーズな入眠を助けます。
飲む際のポイント:
生の生姜をすりおろして使うのが最も効果的です。お湯にすりおろし生姜とはちみつを加えるだけで簡単に作れます。チューブタイプの生姜でも代用可能です。胃への刺激が強すぎると感じる方は、量を調整してください。
⑦ 甘酒
「飲む点滴」とも称される甘酒は、栄養価が非常に高く、疲労回復と安眠の両方に効果的です。
おすすめの理由:
米麹から作られる甘酒には、脳の唯一のエネルギー源である「ブドウ糖」が豊富に含まれており、疲れた脳を癒してくれます。また、ビタミンB群も豊富で、エネルギー代謝を助け、疲労回復を促進します。さらに、麹菌が生成するGABAや、トリプトファンも含まれており、睡眠を多角的にサポートします。
飲む際のポイント:
甘酒には「米麹甘酒」(ノンアルコール)と「酒粕甘酒」(微量のアルコールを含む)の2種類があります。寝る前に飲むのは、アルコールを含まない「米麹甘酒」にしましょう。温めてゆっくり飲むことで、体が温まり、よりリラックスできます。
⑧ 味噌汁
意外に思われるかもしれませんが、日本の伝統的なスープである味噌汁も、優れた安眠ドリンクとなり得ます。
おすすめの理由:
味噌の原料である大豆には、トリプトファンが豊富に含まれています。また、発酵過程でGABAが生成されるため、リラックス効果も期待できます。豆腐やわかめ、きのこなどの具材を加えることで、マグネシウムや他のビタミン・ミネラルも同時に摂取できます。
飲む際のポイント:
寝る前に飲む場合は、塩分の摂りすぎに注意が必要です。出汁をしっかり効かせた減塩タイプにし、量は少なめ(お椀に半分程度)にしましょう。体を温め、ホッとする味わいが心を落ち着かせてくれます。
⑨ アーモンドミルク
牛乳が苦手な方や、ヴィーガンの方におすすめなのがアーモンドミルクです。
おすすめの理由:
アーモンドには、神経の興奮を抑えるミネラルである「マグネシウム」が豊富に含まれています。マグネシウムは、天然の精神安定剤とも言われ、筋肉の弛緩を助け、安らかな眠りへと導きます。また、トリプトファンも含まれており、乳製品にアレルギーがある人でも安心して摂取できます。
飲む際のポイント:
市販のアーモンドミルクには砂糖が添加されているものも多いので、「砂糖不使用」タイプを選ぶのがおすすめです。温めて飲むと、香ばしい香りが引き立ち、リラックス効果が高まります。
⑩ ミントティー
爽やかな香りが特徴のミントティーは、気分をリフレッシュさせたい時だけでなく、寝る前のリラックスタイムにも適しています。
おすすめの理由:
ミントに含まれる「メントール」の香りには、鎮静作用があり、神経の緊張を和らげてくれます。また、胃腸の調子を整える効果も知られており、消化不良による不快感を和らげ、快適な眠りをサポートします。特にペパーミントよりも香りが穏やかなスペアミントがおすすめです。
飲む際のポイント:
清涼感が強すぎると感じる場合は、他のハーブ(カモミールなど)とブレンドすると、よりマイルドで飲みやすくなります。
⑪ ラベンダーティー
アロマテラピーでも安眠効果で有名なラベンダーは、ハーブティーとしても楽しめます。
おすすめの理由:
ラベンダーの主成分である「リナロール」や「酢酸リナリル」という香り成分には、優れた鎮静作用と抗不安作用があり、副交感神経を優位にして心身を深いリラックス状態に導きます。ストレスや不安で眠れない夜に特におすすめです。
飲む際のポイント:
香りが非常に強いため、最初は少量から試すのが良いでしょう。飲み慣れない方は、カモミールやレモンバームなど、他のハーブとブレンドされたものから始めると飲みやすいです。
⑫ 乳酸菌飲料
腸内環境と睡眠の質には、密接な関係があることが近年の研究でわかってきています。
おすすめの理由:
「腸脳相関」という言葉があるように、腸と脳は互いに影響を及ぼしあっています。腸内環境が整うと、セロトニンの前駆体であるトリプトファンの吸収が良くなったり、GABAが産生されやすくなったりすると考えられています。継続的に乳酸菌を摂取することで腸内環境を改善し、間接的に睡眠の質を高める効果が期待できます。
飲む際のポイント:
糖分が多い製品もあるため、成分表示を確認し、糖質が控えめなものを選ぶと良いでしょう。睡眠サポートを謳った機能性表示食品も多く販売されています。
⑬ チェリージュース
特に「タートチェリー」という酸味の強い品種のチェリージュースは、天然の睡眠補助飲料として注目されています。
おすすめの理由:
タートチェリーには、睡眠ホルモンである「メラトニン」そのものが自然な形で含まれています。また、メラトニンの原料となるトリプトファンも含まれており、ダブルの効果で睡眠をサポートします。研究では、タートチェリージュースの摂取が、睡眠時間の延長や睡眠効率の改善に繋がることが示されています。
飲む際のポイント:
甘味料などが添加されていない100%濃縮還元タイプを選びましょう。酸味が強いので、水やお湯で割って飲むのがおすすめです。
⑭ 青汁
健康飲料のイメージが強い青汁ですが、製品によっては睡眠サポートに役立つものもあります。
おすすめの理由:
青汁の原料としてよく使われる大麦若葉やケールには、リラックス効果のあるGABAや、神経の興奮を抑えるカルシウム、マグネシウムが含まれていることがあります。食物繊維も豊富なので、腸内環境の改善にも繋がります。
飲む際のポイント:
製品によって含まれる栄養素が大きく異なるため、GABAやテアニンなどが強化された、睡眠サポートを目的とした製品を選ぶのが効果的です。水だけでなく、牛乳や豆乳で割ると、トリプトファンも同時に摂取でき、味もまろやかになります。
⑮ レモンバームティー
レモンのような爽やかな香りが特徴のレモンバームも、古くから鎮静作用のあるハーブとして利用されてきました。
おすすめの理由:
レモンバームに含まれる「ロスマリン酸」などの成分が、脳内のGABAの分解を抑制し、結果的にGABAの濃度を高めることで、穏やかな鎮静作用と抗不安作用を発揮します。神経の高ぶりを鎮め、穏やかな気持ちで眠りにつきたい時に最適です。
飲む際のポイント:
単体でも美味しいですが、ミントやカモミールとブレンドすると、さらに風味豊かで相乗効果も期待できます。
コンビニで手軽に買える睡眠サポート飲料3選
忙しい毎日の中で、「寝る前の飲み物を自分で準備するのは少し面倒…」と感じることもあるでしょう。そんな時に頼りになるのが、コンビニエンスストアで手軽に購入できる睡眠サポート飲料です。これらは「機能性表示食品」として、睡眠の質を向上させる効果が科学的に報告された成分を含んでおり、より手軽かつ効果的に睡眠ケアを行いたい方におすすめです。ここでは、代表的な3つの製品を、公式サイトの情報に基づいて詳しくご紹介します。
① ヤクルト1000
株式会社ヤクルト本社が販売する「Yakult(ヤクルト)1000」は、近年の睡眠市場で大きな注目を集めている乳酸菌飲料です。
- 機能性関与成分: 乳酸菌 シロタ株(L.カゼイ YIT 9029)
- 届出表示: 「本品には乳酸菌 シロタ株(L.カゼイ YIT 9029)が含まれるので、一時的な精神的ストレスがかかる状況でのストレスを和らげ、また、睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)を高める機能があります。」(株式会社ヤクルト本社公式サイトより引用)
特徴とメカニズム:
この製品の最大の特徴は、1本(100ml)あたりに1000億個という非常に高密度の「乳酸菌 シロタ株」を含んでいる点です。乳酸菌 シロタ株は、生きて腸まで届くことが科学的に証明されています。
その働きは、単に腸内環境を整えるだけではありません。研究により、乳酸菌 シロタ株が腸から脳へと働きかける「腸脳相関」を通じて、ストレスホルモンであるコルチゾールの過剰な分泌を抑制することが示唆されています。日中のストレスが緩和されることで、夜間のスムーズな入眠と深い眠りに繋がりやすくなるのです。
「眠りの深さ」や「すっきりとした目覚め」といった具体的な睡眠の質向上だけでなく、その原因となりうる「一時的な精神的ストレス」の緩和にもアプローチするのが大きな強みです。日中のストレスが多く、それが原因で寝つきが悪い、眠りが浅いと感じている方に特におすすめの飲料と言えるでしょう。継続的に飲むことで、腸内環境の改善と共に、ストレスに負けない心身の状態を目指すことができます。
参照:株式会社ヤクルト本社公式サイト
② ネルノダ
ハウスウェルネスフーズ株式会社が展開する「ネルノダ」は、睡眠の質向上に特化した機能性関与成分「GABA」を配合したブランドです。
- 機能性関与成分: GABA 100mg
- 届出表示: 「本品にはGABAが含まれており、GABAには睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)の向上に役立つ機能があることが報告されています。」(ハウスウェルネスフーズ株式会社公式サイトより引用)
特徴とメカニズム:
ネルノダの主役は、前章でも解説した「GABA(ギャバ)」です。GABAは、脳内に存在する抑制性の神経伝達物質で、興奮した神経を鎮め、心身をリラックスさせる働きがあります。
ネルノダには、このGABAが機能性表示食品として効果が報告されている量である100mg配合されています。就寝前に摂取することで、日中の活動で高ぶった交感神経から、リラックスモードの副交感神経への切り替えをスムーズにし、穏やかな入眠をサポートします。
特に効果が報告されているのは「眠りの深さ」と「すっきりとした目覚め」です。深いノンレム睡眠の割合を増やすことで、夜中に目が覚めることを減らし、朝起きた時の疲労感を軽減する効果が期待されます。
ネルノダには、飲みやすいドリンクタイプ(100ml)の他に、水なしで飲める粒タイプもあり、ライフスタイルや好みに合わせて選べる点も便利です。旅行先や出張先でも手軽に睡眠ケアをしたい場合に重宝します。考え事が多くて頭が冴えてしまう方や、深い眠りを得て翌朝スッキリ起きたい方に適した製品です。
参照:ハウスウェルネスフーズ株式会社公式サイト
③ キリン おいしい免疫ケア 睡眠
キリンビバレッジ株式会社から発売されている「キリン おいしい免疫ケア 睡眠」は、その名の通り、「免疫」と「睡眠」という2つの重要な健康課題に同時にアプローチするユニークな製品です。
- 機能性関与成分: プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma)1,000億個
- 届出表示: 「本品は、プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma)を含みます。プラズマ乳酸菌はpDC(プラズマサイトイド樹状細胞)に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されています。また、睡眠の質(眠りの深さ、起床時の疲労感や眠気)の改善に役立つことが報告されています。」(キリンホールディングス株式会社公式サイトより引用)
特徴とメカニズム:
この製品の鍵となるのは、キリンが独自に発見した「プラズマ乳酸菌」です。一般的な乳酸菌が一部の免疫細胞にしか働きかけないのに対し、プラズマ乳酸菌は免疫の司令塔である「pDC(プラズマサイトイド樹状細胞)」を直接活性化させるという特徴があります。これにより、免疫システム全体の維持に貢献します。
そして、このプラズマ乳酸菌には、睡眠の質を改善する機能も報告されています。具体的なメカニズムはまだ研究段階ですが、免疫システムの安定化が、自律神経のバランスや体内の炎症反応などに良い影響を与え、結果として睡眠の質向上に繋がる可能性が考えられています。
届出表示にあるように、「眠りの深さ」だけでなく、「起床時の疲労感や眠気」の改善にも役立つとされており、日中のパフォーマンスを重視する方にも嬉しい効果です。季節の変わり目などで体調を崩しやすい方や、日々の健康維持と睡眠ケアを一本でまとめて行いたいという、効率を重視する現代人にぴったりの飲料と言えるでしょう。
参照:キリンホールディングス株式会社公式サイト
睡眠の質を上げる飲み物を飲むベストなタイミング
せっかく睡眠に良い飲み物を選んでも、飲むタイミングを間違えるとその効果を十分に得られないことがあります。むしろ、タイミングによっては逆効果になってしまうことさえあります。ここでは、睡眠の質を最大化するための、飲み物を飲むベストなタイミングについて解説します。
就寝の1〜2時間前が目安
結論から言うと、睡眠の質を高めるための飲み物を飲む最適なタイミングは、就寝する1〜2時間前です。これには、主に2つの科学的な理由があります。
理由1:深部体温のコントロール
一つ目の理由は、本記事で繰り返し解説している「深部体温」のメカニズムに関わります。温かい飲み物を飲むと、一時的に深部体温が上昇します。その後、体は熱を放出して体温を下げようと働き、この体温が下降するタイミングで、私たちは最も強い眠気を感じます。この一連のプロセスには、ある程度の時間が必要です。
就寝直前に飲んでしまうと、体温がまだ上昇している段階でベッドに入ることになり、かえって寝つきを妨げてしまう可能性があります。就寝の1〜2時間前に飲んでおくことで、ちょうどベッドに入る頃に体温がスムーズに下がり始め、自然な眠りの波に乗ることができるのです。
理由2:利尿作用と消化への配慮
二つ目の理由は、生理的な問題です。就寝直前に水分を多く摂ると、夜中に尿意で目が覚めてしまう「夜間頻尿」のリスクが高まります。睡眠の質を高めるためには、途中で覚醒することなく、朝までぐっすり眠り続けることが重要です。就寝の1〜2時間前に飲んでおけば、寝る前に一度トイレを済ませておく時間的余裕が生まれます。
また、牛乳や甘酒、味噌汁といった消化が必要な飲み物の場合、胃の中に物が入ったまま眠ると、睡眠中も消化器官が働き続けることになり、眠りが浅くなる原因となります。少し時間を置くことで、胃への負担を減らし、体を完全にリラックスモードに切り替えることができます。
ハーブティーに含まれるリラックス成分や、機能性表示食品に含まれるGABAなどの成分が体に吸収され、効果を発揮し始めるまでにも30分〜1時間程度の時間が必要とされています。これらの理由から、「就寝の1〜2時間前」というタイミングが、あらゆる面で最も合理的かつ効果的であると言えるのです。
温かい飲み物はゆっくりと飲む
飲むタイミングと合わせて重要になるのが、「飲み方」です。特に温かい飲み物は、焦って一気に飲むのではなく、ゆっくりと時間をかけて味わうことを心がけましょう。
リラックス効果の最大化:
ゆっくりと飲むという行為そのものが、心を落ち着かせ、副交感神経を優位にするための「儀式」となります。温かいマグカップを両手で包み込み、立ち上る湯気の香りを楽しみ、一口ずつ丁寧に味わう。この一連の動作が、日中の慌ただしさや緊張から心を切り離し、睡眠への準備を整えてくれます。テレビやスマートフォンを見ながら無意識に飲むのではなく、その時間だけは飲み物と自分自身に向き合う「マインドフルネス」な時間と捉えると、より高いリラックス効果が得られます。
体への負担を軽減:
熱すぎる飲み物を一気に飲むと、食道や胃の粘膜を傷つけるリスクがあります。また、急激な温度変化は体にストレスを与え、交感神経を刺激してしまう可能性も否定できません。5〜10分かけてゆっくりと飲むことで、飲み物の温度も適度に下がり、体に優しく作用します。
寝る前の15分間を「リラックスドリンクタイム」として毎日の習慣に組み込むことで、心と体の両方が自然と「これから眠るんだ」というモードに切り替わるようになります。ぜひ、この豊かな時間を大切にしてみてください。
寝る前に避けるべき!睡眠の質を下げるNGな飲み物
これまで睡眠の質を「上げる」飲み物を紹介してきましたが、一方で、良かれと思って飲んだものが、実は睡眠の質を著しく「下げる」原因になっているケースも少なくありません。ここでは、快適な睡眠のために、寝る前には絶対に避けるべきNGな飲み物とその理由を詳しく解説します。
| NGな飲み物の種類 | 避けるべき理由 | 具体例 |
|---|---|---|
| カフェイン飲料 | 脳を覚醒させ、眠気を妨げる。利尿作用もある。 | コーヒー、紅茶、緑茶、ほうじ茶、ウーロン茶、エナジードリンク、コーラなど |
| アルコール類 | 入眠は早めるが、中途覚醒や浅い眠りの原因になる。 | ビール、ワイン、日本酒、ウイスキーなど全ての酒類 |
| 冷たい飲み物 | 内臓を冷やし、深部体温の低下を妨げる。 | 冷たい水、アイスティー、冷えたジュースなど |
カフェインを多く含む飲み物
カフェインは、日中の眠気覚ましや集中力アップの強い味方ですが、夜に摂取すると睡眠にとって最大の敵となります。
なぜNGなのか?
その理由は、カフェインが持つ強力な覚醒作用にあります。私たちの脳内では、活動している間に「アデノシン」という物質が蓄積します。このアデノシンが脳内の受容体に結合することで、私たちは眠気を感じます。ところが、カフェインはアデノシンと構造が似ているため、アデノシンの代わりに受容体に結合し、その働きをブロックしてしまいます。これにより、脳は「まだ疲れていない」と錯覚し、覚醒状態が続いてしまうのです。
さらに重要なのが、カフェインの持続時間です。カフェインの血中濃度が半分になるまでにかかる時間(半減期)は、健康な成人で約4時間と言われています。つまり、夕方5時にコーヒーを一杯飲んだ場合、夜9時になってもその半分のカフェインが体内に残っている計算になります。人によってはさらに長く影響が続くため、専門家の間では「就寝の5〜6時間前からはカフェインを摂取しない」ことが推奨されています。
また、カフェインには利尿作用もあるため、夜中にトイレに行きたくなり、中途覚醒の原因にもなります。
コーヒー
言わずと知れたカフェイン飲料の代表格です。ドリップコーヒー1杯(150ml)あたり、約60mg〜90mgのカフェインが含まれています。寝る前の摂取は絶対に避けましょう。日中に飲む場合も、午後3時以降は控えるのが賢明です。
紅茶・緑茶
紅茶や緑茶にもカフェインは含まれています。カップ1杯(150ml)あたり、紅茶で約30mg、煎茶で約30mgのカフェインが含まれます。リラックス効果のあるテアニンも含まれていますが、睡眠への影響を考えると、カフェインの覚醒作用の方が勝る可能性が高いです。寝る前に飲むのであれば、カモミールティーやルイボスティーなどのノンカフェインのハーブティーを選びましょう。意外なことに、ほうじ茶や玄米茶、ウーロン茶にもカフェインは含まれているので注意が必要です。
エナジードリンク
多量のカフェイン(製品によってはコーヒーの2倍以上)に加え、大量の糖分が含まれています。これらは交感神経を強力に刺激し、脳を興奮状態にするため、睡眠の質を著しく低下させます。夜間の勉強や仕事のために飲むのは、翌日のパフォーマンス低下に直結するため、避けるべきです。
アルコール類
「寝つきを良くするために寝酒を飲む」という習慣がある人もいますが、これは睡眠の質を犠牲にする非常に危険な習慣です。
なぜNGなのか?
アルコールは確かに入眠作用があり、飲み始めはリラックスして眠くなるように感じます。しかし、その効果は長くは続きません。アルコールが体内で分解される過程で、「アセトアルデヒド」という毒性の強い覚醒物質が生成されます。このアセトアルデヒドが、睡眠の後半部分で交感神経を刺激し、眠りを浅くしたり、早朝に目が覚めてしまう「中途覚醒」を引き起こしたりするのです。
さらに、アルコールは深いノンレム睡眠を減少させ、夢を見る時間であるレム睡眠を抑制します。その結果、睡眠全体の構造が乱れ、「たくさん寝たはずなのに疲れが取れない」「悪夢を見やすい」といった状態に陥ります。
また、アルコールには筋弛緩作用があるため、喉の周りの筋肉が緩み、いびきや睡眠時無呼吸症候群を悪化させる原因にもなります。利尿作用も強く、脱水症状や夜間頻尿を引き起こすなど、睡眠にとって百害あって一利なしと言っても過言ではありません。
質の高い睡眠を求めるのであれば、アルコールは睡眠薬の代わりにはならないという事実を認識し、寝る前の飲酒はきっぱりとやめることが重要です。
冷たい飲み物
暑い日や運動の後には冷たい飲み物が美味しく感じられますが、寝る前に飲むのは避けるべきです。
なぜNGなのか?
理由は、深部体温の低下を妨げるからです。前述の通り、人は深部体温が下がることで眠りにつきます。しかし、就寝前に冷たい飲み物を飲むと、内臓が急激に冷やされます。すると、体は生命維持のために体温を元に戻そう(上げよう)と、熱を産生し始めます。これは、眠るために体温を下げたい方向とは真逆の働きです。結果として、体が覚醒モードになってしまい、寝つきが悪くなる可能性があります。
また、冷たい飲み物は胃腸に負担をかけ、消化活動を妨げることもあります。寝る前は、常温の水や白湯、温かいハーブティーなど、体に負担をかけずに水分補給できるものを選びましょう。
飲み物以外で睡眠の質を高める5つの習慣
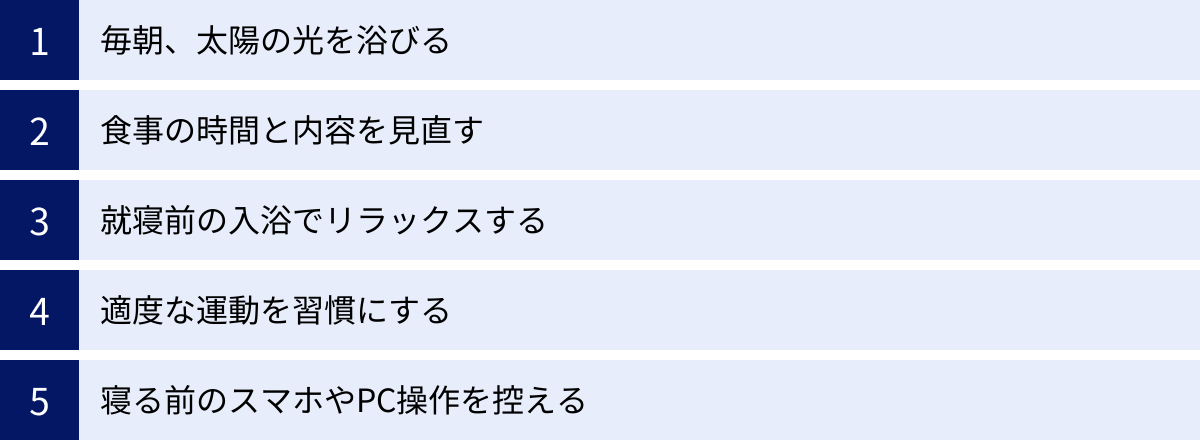
寝る前の飲み物を見直すことは、睡眠の質を向上させるための非常に有効なアプローチですが、それだけで全ての睡眠問題が解決するわけではありません。質の高い睡眠は、日中の過ごし方から寝室の環境まで、生活全体の習慣によって作られます。ここでは、飲み物の工夫と合わせて実践したい、睡眠の質を根本から高めるための5つの重要な習慣をご紹介します。
① 毎朝、太陽の光を浴びる
私たちの体には、約24時間周期で心身の状態をコントロールする「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この体内時計が正しく機能していることが、夜の自然な眠りのために不可欠です。
そして、この体内時計を毎日リセットするための最強のスイッチが「太陽の光」です。朝、起きたらすぐにカーテンを開け、15〜30分ほど太陽の光を浴びる習慣をつけましょう。網膜から入った光の刺激が脳に伝わり、体内時計がリセットされます。
これにより、精神を安定させる「セロトニン」の分泌が活発になります。そして、このセロトニンは、リセットから約14〜16時間後に睡眠ホルモン「メラトニン」に変換される性質があります。つまり、朝の光を浴びることが、その日の夜の眠りの質を決定づけるのです。
曇りや雨の日でも、屋外の光は室内の照明よりずっと強いため、ベランダに出たり、窓際で過ごしたりするだけでも効果があります。毎日同じ時間に起き、光を浴びることで、規則正しい睡眠と覚醒のリズムが体に刻まれていきます。
② 食事の時間と内容を見直す
食事もまた、体内時計と睡眠の質に大きな影響を与えます。特に夕食の時間と内容には注意が必要です。
就寝の3時間前までに夕食を終えるのが理想です。就寝時に胃の中に未消化の食べ物が残っていると、睡眠中も消化器官が活発に働き続けることになり、脳や体が十分に休息できません。結果として、眠りが浅くなったり、夜中に目が覚めたりする原因になります。
また、夕食の内容も重要です。脂っこいものや、香辛料の強い刺激的な食事は消化に時間がかかり、交感神経を刺激するため避けましょう。逆に、睡眠をサポートするトリプトファン(魚、大豆製品、乳製品など)やGABA(トマト、きのこなど)、マグネシウム(海藻、ナッツ類など)を意識的に取り入れた、消化の良い和食中心のメニューがおすすめです。
朝食をしっかり食べることも、体内時計を正常に動かす上で重要です。朝食を抜くと、体のエネルギーが不足し、日中の活動性が低下するだけでなく、夜の睡眠リズムにも悪影響を及ぼします。
③ 就寝前の入浴でリラックスする
就寝前の入浴は、飲み物と同様に深部体温をコントロールし、リラックス効果を高めるための非常に有効な手段です。
最適な入浴法は、就寝の90分〜2時間前に、38〜40℃程度のぬるめのお湯に15〜20分ほどゆっくりと浸かることです。これにより、体の芯から温まり、血行が促進されます。そして、お風呂から上がった後に深部体温がスムーズに低下し始め、自然で強い眠気を誘います。
42℃以上の熱いお湯は交感神経を刺激して体を覚醒させてしまうため、逆効果です。シャワーだけで済ませるのではなく、湯船に浸かって心身の緊張をほぐす時間を作りましょう。好きな香りの入浴剤を使ったり、照明を少し落としたりするのも、リラックス効果を高めるのに役立ちます。
④ 適度な運動を習慣にする
日中に適度な運動を行うと、心地よい疲労感が得られ、夜の寝つきが良くなり、深い睡眠が増えることがわかっています。
ウォーキングやジョギング、ヨガなどの有酸素運動が特におすすめで、週に3〜5回、1回30分程度を目安に習慣にすると良いでしょう。運動を行う時間帯としては、夕方(午後4時〜6時頃)が最も効果的とされています。夕方に運動で体温を一度上げておくと、夜にかけて体温が下がりやすくなり、スムーズな入眠に繋がります。
ただし、就寝直前の激しい運動は避けるべきです。ランニングや筋力トレーニングなどの激しい運動は、交感神経を興奮させ、体温を上昇させてしまうため、かえって眠りを妨げます。寝る前に行うのであれば、軽いストレッチや深呼吸など、心身をリラックスさせる程度のものに留めましょう。
⑤ 寝る前のスマホやPC操作を控える
現代人にとって最も難しい習慣かもしれませんが、睡眠の質を考える上で極めて重要です。スマートフォンやパソコン、タブレットなどの画面から発せられる「ブルーライト」は、太陽光に多く含まれる波長の短い光で、非常に強い覚醒作用があります。
夜にこのブルーライトを浴びると、脳は「まだ昼間だ」と勘違いし、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制してしまいます。これにより、体内時計が後ろにずれ込み、寝つきが悪くなるだけでなく、睡眠の質全体が低下します。
理想は、就寝の1〜2時間前には全てのデジタルデバイスの電源をオフにすることです。その時間は、読書をしたり、音楽を聴いたり、家族と話したり、温かい飲み物を飲んでリラックスしたりと、脳を休ませる時間にあてましょう。どうしてもスマホを見る必要がある場合は、画面の明るさを最低限にし、ブルーライトカット機能(ナイトシフトモードなど)を必ず利用するようにしてください。
これらの5つの習慣は、一つひとつは小さなことかもしれませんが、継続することで睡眠の質に大きな変化をもたらします。ぜひ、飲み物の見直しと合わせて、できることから取り入れてみてください。
まとめ
質の高い睡眠は、健康で活力に満ちた毎日を送るための基盤です。この記事では、そのための有効な手段の一つとして、「寝る前に飲む一杯の飲み物」に焦点を当て、その効果から具体的なおすすめ、注意点までを網羅的に解説してきました。
最後に、この記事の重要なポイントを改めて振り返ります。
- 睡眠を助ける飲み物の3大効果: 温かい飲み物は①体を温めて深部体温の低下を促し、②香りや成分で心身をリラックスさせ、③睡眠に必要な栄養素(トリプトファン、GABAなど)を補給することで、私たちを快適な眠りへと導きます。
- あなたに合った一杯を見つける: 最もシンプルで効果的な「白湯」、トリプトファン豊富な「ホットミルク」、リラックス効果の高い「カモミールティー」など、15種類の飲み物をご紹介しました。ご自身の体調や悩み、好みに合わせて、お気に入りの一杯を見つけることが継続の鍵です。
- 飲むタイミングが重要: 効果を最大化するためのベストなタイミングは「就寝の1〜2時間前」です。体温調節や消化、利尿作用の観点からも、この時間を守ることが推奨されます。
- 避けるべきNGな飲み物: カフェイン(コーヒー、紅茶、緑茶など)とアルコールは、睡眠の質を著しく低下させる二大要因です。夕方以降は摂取を控えるようにしましょう。
- 生活習慣全体で質を高める: 飲み物の工夫と合わせて、①朝日を浴びる、②食事の改善、③就寝前の入浴、④適度な運動、⑤寝る前のデジタルデトックスといった生活習慣を見直すことが、根本的な睡眠改善に繋がります。
睡眠の悩みは人それぞれですが、解決への第一歩は、日々の小さな習慣を変えることから始まります。今夜からでもすぐに始められる「寝る前の一杯」を見直し、あなた自身の心と体に合ったリラックスタイムを取り入れてみてはいかがでしょうか。
この記事が、あなたの睡眠の質を向上させ、よりすっきりと快適な朝を迎えるための一助となれば幸いです。