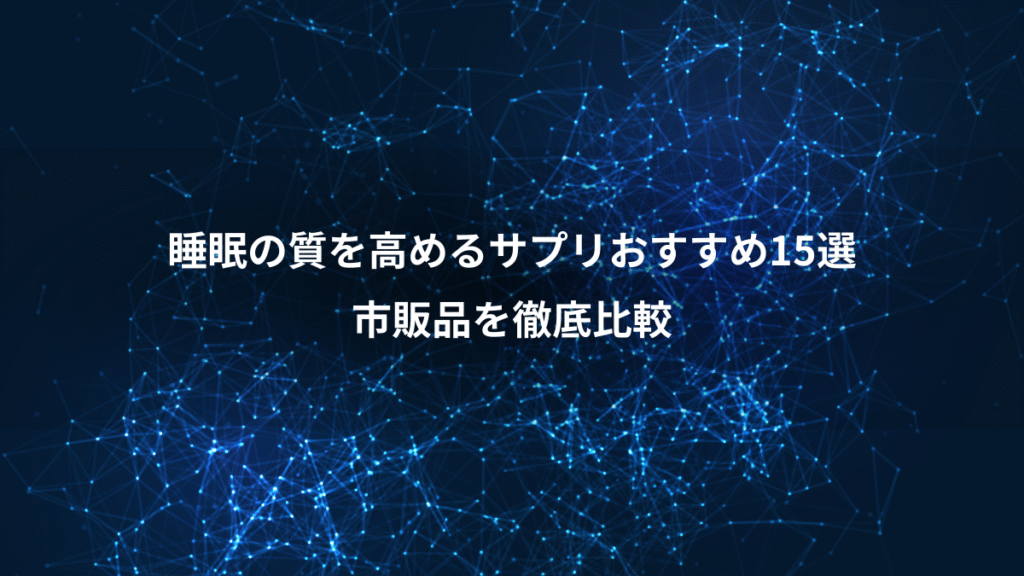「夜中に何度も目が覚める」「朝起きても疲れが取れていない」「日中も眠気が続いて仕事に集中できない」。現代社会では、このような睡眠に関する悩みを抱える人が少なくありません。質の高い睡眠は、心身の健康を維持し、日々のパフォーマンスを最大限に発揮するために不可欠です。
しかし、生活習慣をすぐに改善するのは難しいと感じる方も多いでしょう。そこで注目されているのが、睡眠の質を高めることをサポートするサプリメントです。これらは医薬品とは異なり、機能性関与成分の働きによって、穏やかに睡眠の悩みにアプローチします。
この記事では、睡眠の質を高めるサプリの基本的な知識から、自分に合った製品の選び方、そして市販で人気のおすすめサプリ15選まで、網羅的に詳しく解説します。さらに、サプリだけに頼らない根本的な睡眠改善のための生活習慣についても触れていきます。
質の良い睡眠を取り戻し、すっきりと活力に満ちた毎日を送るための一助として、ぜひ本記事をお役立てください。
目次
睡眠の質を高めるサプリとは

「睡眠サプリ」と一言でいっても、その定義や役割はさまざまです。ここでは、睡眠の質を高めるサプリがどのようなもので、どのような効果が期待できるのか、そして混同されがちな医薬品との違いは何かを詳しく解説します。正しく理解することが、自分に合った製品を見つけるための第一歩です。
睡眠をサポートする機能性表示食品
睡眠の質を高めるサプリメントの多くは、「機能性表示食品」として販売されています。これは、健康の維持及び増進に役立つ特定の保健の目的が期待できる旨(機能性)を表示するものとして、消費者庁に届け出られた食品のことを指します。
機能性表示食品の最大の特徴は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を商品パッケージに表示できる点にあります。つまり、「睡眠の質を高める」「ストレスを緩和する」といった具体的な効果を表示するためには、その製品に含まれる「機能性関与成分」が、ヒトを対象とした臨床試験や、複数の研究論文を統合的に分析した研究レビューによって、その機能を持つことが確認されている必要があります。
これらの科学的根拠に関する情報は、消費者庁のウェブサイトで公開されており、誰でも届出内容を確認できます。これにより、消費者は表示されている効果の根拠を理解した上で、製品を選択できます。
ただし、ここで重要なのは、機能性表示食品はあくまで「食品」であり、病気の診断、治療、予防を目的としたものではないということです。特定の保健の目的が期待できるものではありますが、医薬品とは明確に異なります。また、国の個別審査を受けて許可された「特定保健用食品(トクホ)」とも異なり、事業者の責任で機能性を表示する制度である点も特徴です。
現代社会において、ストレス、不規則な生活、スマートフォンの長時間利用など、睡眠の質を低下させる要因は数多く存在します。こうした背景から、手軽に取り入れられる健康習慣の一つとして、科学的根拠に基づいた睡眠サポートサプリ、すなわち機能性表示食品が多くの人々に選ばれているのです。
期待できる主な効果
睡眠の質を高めるサプリに含まれる機能性関与成分によって、さまざまな効果が期待できます。ここでは、代表的な効果を3つに分けて詳しく見ていきましょう。
睡眠の質の向上
サプリメントに期待される最も中心的な効果が、睡眠の質の向上です。これは単に「眠れるようになる」ということだけを指すのではありません。具体的には、以下のような多角的な改善が報告されています。
- 寝つきの改善: 布団に入ってから眠りにつくまでの時間が短縮される。
- 眠りの深化: 睡眠中の深い眠り(ノンレム睡眠)の割合や時間が増加し、ぐっすりと眠れるようになる。
- 中途覚醒の減少: 夜中に目が覚めてしまう回数が減る。
- 睡眠時間の延長: 途中で起きることなく、朝までしっかりと眠れるようになる。
- 起床時の爽快感: 朝、すっきりと目覚められる感覚や、睡眠に対する満足感が高まる。
これらの効果は、例えば「L-テアニン」がもたらすリラックス作用や、「グリシン」が深部体温をスムーズに低下させる作用、「クロセチン」が中途覚醒を減らす作用など、各機能性関与成分の独自のメカニズムによってもたらされます。自分の睡眠の悩みが「寝つきが悪い」「眠りが浅い」「途中で起きてしまう」のうち、どれに当てはまるかを考えることが、成分選びの鍵となります。
ストレスや疲労感の緩和
睡眠の悩みは、日中のストレスや疲労感と密接に関連しています。過度なストレスは交感神経を優位にし、心身を興奮状態にさせるため、寝つきが悪くなったり眠りが浅くなったりします。逆に、睡眠不足はストレス耐性を低下させ、疲労を蓄積させるという悪循環に陥りがちです。
一部の睡眠サポートサプリには、一時的な精神的ストレスや、仕事や勉強による疲労感を緩和する機能が報告されている成分が含まれています。代表的な成分が「GABA(ギャバ)」です。GABAは、脳内の興奮性の神経伝達を抑制する働きがあり、高ぶった神経を落ち着かせ、リラックス状態へと導きます。
この作用により、就寝前に摂取することで心身の緊張が和らぎ、スムーズな入眠をサポートします。また、日中のストレスを軽減することで、夜の睡眠の質そのものを根本から改善する効果も期待できます。良質な睡眠がとれるようになると、翌日の疲労感が軽減され、日中のパフォーマンス向上にも繋がるでしょう。睡眠の悩みと同時に、日中のストレスや疲労感も気になる方には、こうした機能を持つ成分が含まれたサプリがおすすめです。
一時的な気分の落ち込みを和らげる
睡眠不足は、身体的な疲労だけでなく、精神的な健康にも大きな影響を及ぼします。気分の浮き沈みが激しくなったり、ささいなことでイライラしたり、前向きな気持ちになれなかったりするのは、睡眠の質が低下しているサインかもしれません。
このような一時的な気分の落ち込みに対して、ポジティブな気分をサポートする機能が報告されている成分も存在します。その代表格が「ラフマ由来ヒペロシド」および「ラフマ由来イソクエルシトリン」です。
これらの成分は、幸福感や安心感に関わる神経伝達物質「セロトニン」の量を増やす働きが報告されています。セロトニンは、夜になると睡眠を促すホルモン「メラトニン」の材料にもなるため、セロトニンの量を安定させることは、気分の安定だけでなく、質の高い睡眠にも繋がります。
睡眠の質を高めると同時に、一時的な気分の落ち込みもケアしたいと考える方にとって、ラフマ由来成分を含むサプリは有効な選択肢の一つとなり得ます。
睡眠薬や睡眠改善薬との違い
睡眠に関する製品を選ぶ上で、サプリメントと医薬品の違いを正しく理解することは非常に重要です。これらは目的、作用、入手方法などが全く異なります。誤った認識でいると、期待した効果が得られないだけでなく、思わぬ健康リスクを招く可能性もあります。
| 項目 | 睡眠サプリ(機能性表示食品) | 睡眠改善薬(一般用医薬品) | 睡眠薬(医療用医薬品) |
|---|---|---|---|
| 分類 | 食品 | 第2類医薬品・指定第2類医薬品 | 処方箋医薬品 |
| 目的 | 睡眠の質の向上をサポート | 一時的な不眠症状の緩和 | 不眠症の治療 |
| 主な成分 | L-テアニン、GABA、グリシンなど | ジフェンヒドラミン塩酸塩(抗ヒスタミン薬) | ベンゾジアゼピン系、非ベンゾジアゼピン系など |
| 作用機序 | リラックス促進、深部体温調整など、穏やかに睡眠環境を整える | 脳の活動を抑えるヒスタミンの働きをブロックし、眠気を誘発する | 脳の中枢神経に直接作用し、半ば強制的に睡眠状態を誘発する |
| 入手方法 | ドラッグストア、オンラインストアなど | 薬剤師または登録販売者がいる薬局・ドラッグストア | 医師の診察・処方箋が必要 |
| 特徴 | ・習慣性や依存性のリスクが低い ・継続的な使用が可能 ・生活習慣の見直しと併用 |
・一時的な不眠にのみ使用 ・連用は推奨されない ・副作用(翌日の眠気など)の可能性 |
・作用が強い ・依存性や耐性、副作用のリスクがある ・医師の厳格な管理下で使用 |
- 睡眠薬(医療用医薬品)
これは、医師の診断に基づいて処方される「治療薬」です。不眠症という病気の治療を目的とし、脳の機能を抑制することで強制的に眠りを引き起こします。作用が強力な分、依存性や耐性(薬が効きにくくなること)、副作用のリスクも伴うため、医師の厳格な指導のもとで使用する必要があります。 - 睡眠改善薬(一般用医薬品)
こちらは、薬局やドラッグストアで薬剤師や登録販売者から購入できる医薬品です。「寝つきが悪い」「眠りが浅い」といった、一時的な不眠症状を緩和することを目的としています。主成分は、アレルギー薬などにも使われる「ジフェンヒドラミン塩酸塩」という抗ヒスタミン薬で、その副作用である眠気を利用したものです。あくまで一時的な使用を前提としており、慢性的な不眠には使用できません。 - 睡眠サプリ(機能性表示食品)
これらは前述の通り「食品」に分類されます。病気の治療や症状の緩和ではなく、日々の食生活の延長として、睡眠の質の向上をサポートするのが目的です。L-テアニンやGABAといった成分が、心身をリラックスさせたり、睡眠に関わる生理的なリズムを整えたりすることで、自然な眠りを穏やかに支えます。医薬品のような強制力や即効性はありませんが、その分、習慣性のリスクが低く、健康的な生活習慣の一環として継続しやすいのが大きな違いです。
慢性的な不眠で日常生活に支障が出ている場合は、自己判断でサプリや市販薬に頼るのではなく、まず専門の医療機関を受診することが最も重要です。サプリメントは、あくまで健康な人が睡眠の質をさらに高めたい、あるいは軽度な睡眠の悩みを改善したい場合に適した選択肢と捉えましょう。
睡眠の質を高めるサプリの選び方
市場には多種多様な睡眠サプリがあふれており、どれを選べば良いか迷ってしまう方も多いでしょう。ここでは、数ある製品の中から自分に最適な一品を見つけるための4つの重要なポイントを解説します。
悩みに合った機能性関与成分で選ぶ
睡眠サプリ選びで最も重要なのが、自分の睡眠の悩みに合った機能性関与成分が配合されているかを確認することです。成分によってアプローチの仕方が異なるため、期待する効果と成分の特性を照らし合わせることが大切です。
| 悩み・目的 | 主な機能性関与成分 | 期待される効果・作用機序 |
|---|---|---|
| 眠りを深くしたい すっきり目覚めたい |
L-テアニン | ・交感神経の働きを抑え、リラックス状態に導く ・起床時の疲労感を軽減し、睡眠の質を向上させる |
| グリシン | ・深部体温をスムーズに低下させ、深い眠り(徐波睡眠)へ導く ・睡眠の質(眠りの深さ)を高める |
|
| クロセチン | ・深い眠りを促し、中途覚醒の回数を減らす ・起床時の眠気を軽減し、すっきりとした目覚めをサポート |
|
| ストレスや疲労を感じる | GABA | ・興奮性の神経伝達を抑制し、精神的なストレスや疲労感を緩和 ・リラックス作用により、睡眠の質を高める |
| 一時的に気分が落ち込む | ラフマ由来成分 (ヒペロシド, イソクエルシトリン) |
・セロトニンの量を調整し、ポジティブな気分をサポート ・睡眠の質(眠りの深さ)を向上させる |
| 加齢による睡眠の質の低下 | セサミン類 | ・抗酸化作用や自律神経のバランス調整機能により、加齢で低下しがちな睡眠の質(寝つき、眠りの深さ、寝覚め)を改善 |
眠りの深さを改善したいなら「L-テアニン」「グリシン」「クロセチン」
「夜中に何度も目が覚める」「ぐっすり眠れた感じがしない」といった、眠りの深さに関する悩みには、これらの成分がおすすめです。
- L-テアニン: 緑茶に含まれるアミノ酸の一種で、リラックス効果があることで知られています。摂取すると、脳内でリラックス状態の指標となるα波が増加することが報告されています。交感神経の活動を抑制し、副交感神経を優位にすることで、心身の緊張を和らげ、スムーズな入眠と質の高い睡眠をサポートします。また、起床時の疲労感を軽減する効果も報告されており、すっきりとした目覚めを求める方に適しています。
- グリシン: 最も単純な構造を持つアミノ酸で、私たちの体内にも存在します。グリシンを就寝前に摂取すると、手足の末梢血流を増加させ、体の内部の熱(深部体温)を効率的に放出させる働きがあります。人は深部体温が下がる過程で眠気を感じるため、この作用が自然で深い眠り(特に徐波睡眠と呼ばれる最も深い段階の睡眠)への移行をスムーズにします。
- クロセチン: クチナシの果実やサフランに含まれる黄色の天然色素です。強い抗酸化作用を持つことで知られています。睡眠に関しては、中途覚醒の回数を減らし、深い眠りを維持する効果が報告されています。また、起床時の眠気を軽減し、日中の活動意欲を高める働きも期待できるため、朝の目覚めの悪さに悩んでいる方にも良い選択肢となります。
ストレスや疲労感を軽くしたいなら「GABA」
日々の仕事や人間関係でストレスを感じやすく、それが睡眠に影響していると感じる方には「GABA」が適しています。
- GABA(γ-アミノ酪酸): 脳内に存在する神経伝達物質で、興奮を鎮める抑制系の働きを担います。GABAを摂取することで、ストレスによって高ぶりがちな交感神経の働きを抑え、心拍数の上昇を抑制し、リラックス状態を示す脳波(α波)を増加させることが報告されています。これにより、一時的な精神的ストレスや、仕事などによる疲労感を緩和する効果が期待できます。心身がリラックスすることで、寝つきが良くなり、睡眠の質も向上するという好循環が生まれます。
一時的な気分の落ち込みには「ラフマ由来成分」
「なんとなく気分が晴れない」「やる気が出ない」といった精神的な不調が、睡眠の質の低下に繋がっていると感じる場合には、「ラフマ由来成分」が役立つかもしれません。
- ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン: ラフマという植物の葉から抽出される成分です。これらの成分は、脳内のセロトニン濃度を高めるのを助ける働きが報告されています。セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、精神の安定や気分の向上に深く関わっています。この作用により、一時的な気分の落ち込みを和らげ、ポジティブな気分をサポートします。また、セロトニンは睡眠ホルモン「メラトニン」の前駆体でもあるため、セロトニンが整うことは、結果的に睡眠の質(眠りの深さ)の向上にも繋がります。
加齢による睡眠の質の低下には「セサミン類」
年齢を重ねるにつれて、「寝つきが悪くなった」「若い頃のようにぐっすり眠れない」と感じる方は少なくありません。これは、加齢に伴う体内機能の変化が原因の一つです。
- セサミン類: ゴマにわずかしか含まれない希少な成分です。強力な抗酸化作用で知られていますが、睡眠に関しても注目されています。加齢とともに乱れがちになる自律神経のバランスを整える働きが報告されています。自律神経が整うことで、心身がリラックスモードに切り替わりやすくなり、寝つきの改善が期待できます。また、疲労回復をサポートする働きもあり、総合的に加齢によって低下しがちな睡眠の質(寝つき、眠りの深さ、寝覚め)を改善する効果が報告されています。
「機能性表示食品」のマークで選ぶ
サプリメントを選ぶ際、パッケージに表示されている情報をどこまで信頼して良いか不安に思うこともあるでしょう。その際に、信頼性の高い基準となるのが「機能性表示食品」のマークです。
このマークが付いている製品は、販売する事業者が、その製品に含まれる機能性関与成分について、科学的な根拠(臨床試験や研究レビューの結果)を消費者庁に届け出ていることを意味します。パッケージには、
- 「機能性表示食品」である旨の表示
- 届出番号(例:A123)
- 機能性関与成分名
- 届け出た機能性の内容(例:「本品にはGABAが含まれます。GABAには睡眠の質(眠りの深さ)の向上に役立つ機能があることが報告されています。」など)
が明記されています。
このマークがあることで、表示されている効果が、単なる企業の宣伝文句ではなく、一定の科学的根拠に基づいていることが保証されます。 届出番号を消費者庁の「機能性表示食品の届出情報検索」データベースで検索すれば、事業者が提出した科学的根拠の概要や安全性に関する情報を誰でも確認できます。
もちろん、機能性表示食品ではないサプリメントの中にも優れた製品は存在しますが、効果の根拠を重視し、安心して選びたいと考える初心者の方にとっては、このマークの有無が非常に分かりやすい判断基準となるでしょう。
毎日続けやすい形状や価格で選ぶ
睡眠サプリは、医薬品のように一度飲めばすぐに劇的な効果が現れるものではありません。体質改善の一環として、ある程度の期間、毎日継続して摂取することが効果を実感するための鍵となります。そのため、無理なく続けられる製品を選ぶことが非常に重要です。
- 形状で選ぶ:
- 錠剤・カプセル: 最も一般的なタイプ。水で飲むだけなので手軽で、味や匂いが気になりにくいのがメリットです。持ち運びにも便利です。
- 粉末(顆粒): 水に溶かして飲んだり、そのまま口に含んだりするタイプ。成分量が多い製品によく見られます。味付きのものもあり、飲みやすさが工夫されています。
- ドリンク: 就寝前に飲むドリンクタイプ。リラックスタイムの習慣として取り入れやすいですが、他の形状に比べてコストが高くなる傾向があります。
- ゼリー・グミ: おやつ感覚で手軽に摂取できるのが魅力です。水なしで摂れるので、場所を選びません。
自分のライフスタイルや好みに合わせて、最も続けやすいと感じる形状を選びましょう。
- 価格で選ぶ:
価格も継続する上で無視できない要素です。高価な製品ほど効果が高いとは一概には言えません。重要なのは、1日あたりのコストを計算し、自分の予算内で無理なく続けられる価格帯の製品を選ぶことです。
例えば、30日分で3,000円の製品なら1日あたり100円、6,000円なら1日あたり200円となります。定期購入割引などを利用すると、通常価格より安く購入できる場合も多いので、公式サイトなどをチェックしてみましょう。まずは1ヶ月試してみて、効果とコストのバランスを見ながら継続するかどうかを判断するのが現実的です。
安全性を重視するなら「GMP認定工場」製造かチェック
毎日口にするものだからこそ、品質と安全性は徹底的にこだわりたいポイントです。そこで注目したいのが「GMP(Good Manufacturing Practice)」認定工場で製造されているかどうかです。
GMPは「適正製造規範」と訳され、原材料の受け入れから製造、製品の出荷に至るまでの全工程において、製品が「安全」に作られ、「一定の品質」が保たれるようにするための製造工程管理基準です。医薬品の世界では製造業者にGMPの遵守が義務付けられていますが、健康食品(サプリメント)においては任意です。
しかし、消費者の安全志向の高まりを受け、自主的にGMP認定を取得する工場が増えています。GMP認定工場で製造された製品は、
- 表示通りの成分が、表示通りの量だけ含まれていること
- 衛生的な環境で製造され、汚染などがないこと
- 品質が安定していること
などが保証されていると言えます。
パッケージや公式サイトに「GMP認定工場製造」といった記載があるかどうかを確認することで、より信頼性の高い製品を選ぶことができます。安全性を最優先に考えるなら、GMP認定は重要なチェック項目の一つです。
【2024年】睡眠の質を高めるサプリおすすめ15選
ここでは、これまでの選び方のポイントを踏まえ、市販で購入可能なおすすめの睡眠の質を高めるサプリを15製品、厳選してご紹介します。各製品の機能性関与成分、届出表示、特徴などを比較し、自分にぴったりのサプリを見つけるための参考にしてください。
本セクションで紹介する製品情報は、各メーカーの公式サイトおよび消費者庁の機能性表示食品届出情報データベース(2024年時点)に基づいています。価格は変動する可能性があるため、最新の情報は各公式サイトでご確認ください。
① ファンケル 睡眠&疲労感ケア
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機能性関与成分 | L-オルニチン一塩酸塩, L-シトルリン, クロセチン |
| 届出表示 | 睡眠の質(長く眠った感覚)を高め、起床時の疲労感を軽減する機能、日常生活の一時的な身体的疲労感を軽減する機能 |
| 形状 | 錠剤 |
| 1日の目安 | 4粒 |
| 参照元 | 株式会社ファンケル公式サイト、消費者庁 機能性表示食品届出情報 |
睡眠の質と日中の疲労感の両方にアプローチしたい方におすすめの製品です。アミノ酸の一種である「L-オルニチン」と「L-シトルリン」が、成長ホルモンの分泌を促し、身体的な疲労感を軽減。さらに、クチナシ由来の「クロセチン」が、睡眠の質を高め、すっきりとした目覚めをサポートします。「長く眠った感覚」と「起床時の疲労感軽減」という、朝の感覚に焦点を当てた機能性が特徴的です。日中の活動で疲れやすいと感じる方が、夜の休息と日中の活力の両方をケアするのに適しています。
② 味の素 グリナ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機能性関与成分 | グリシン |
| 届出表示 | すみやかに深睡眠をもたらし、睡眠の質の向上(熟眠感の改善、睡眠リズムの改善)や、起床時の爽快感のあるよい目覚め、日中の眠気の改善、疲労感の軽減、作業効率の向上に役立つ機能 |
| 形状 | スティック(粉末) |
| 1日の目安 | 1本 |
| 参照元 | 味の素株式会社公式サイト、消費者庁 機能性表示食品届出情報 |
「グリシン」を主成分とした睡眠サプリのパイオニア的存在です。アミノ酸研究の知見を活かし、睡眠の質を高める成分としてグリシンに着目。摂取することで深部体温をスムーズに低下させ、自然で深い眠り(深睡眠)へと導きます。「熟眠感の改善」や「起床時の爽快感」だけでなく、「日中の眠気の改善」「作業効率の向上」といった、日中のパフォーマンスへの好影響まで幅広く報告されている点が大きな特徴です。グレープフルーツ風味の粉末スティックタイプで、飲みやすいのもポイント。長年の研究実績に裏打ちされた信頼性を求める方におすすめです。
③ アサヒグループ食品 ネナイト
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機能性関与成分 | L-テアニン |
| 届出表示 | 睡眠の質を高めること(起床時の疲労感を軽減)が報告されている |
| 形状 | 錠剤 |
| 1日の目安 | 4粒 |
| 参照元 | アサヒグループ食品株式会社公式サイト、消費者庁 機能性表示食品届出情報 |
起床時の疲労感や眠気を軽減したい方に注目してほしいのが「ネナイト」です。機能性関与成分として、お茶にも含まれるリラックス成分「L-テアニン」を200mg配合。L-テアニンには、睡眠の質を高め、起床時の疲労感を軽減する機能が報告されています。夜中に目が覚めてしまう、ぐっすり眠れた感じがしないといった悩みにアプローチし、すっきりとした朝の目覚めをサポートします。ドラッグストアなどでも手に入りやすく、比較的手頃な価格で始めやすいのも魅力の一つです。
④ ハウスウェルネスフーズ ネルノダ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機能性関与成分 | GABA |
| 届出表示 | 睡眠の質(眠りの深さ、すっきりとした目覚め)の向上に役立つ機能や、仕事や勉強などによる一時的な疲労感や精神的ストレスを緩和する機能 |
| 形状 | ドリンク、粒 |
| 1日の目安 | 1本(ドリンク)、4粒(粒) |
| 参照元 | ハウスウェルネスフーズ株式会社公式サイト、消費者庁 機能性表示食品届出情報 |
睡眠の質向上とストレス緩和の両方を求める方に最適なのが「ネルノダ」です。機能性関与成分「GABA」を100mg配合。GABAの働きにより、眠りの深さやすっきりとした目覚めといった睡眠の質を高めるだけでなく、日中の活動による一時的な疲労感や精神的ストレスを緩和する機能も報告されています。就寝前のリラックスタイムに取り入れやすいドリンクタイプと、手軽に摂取できる粒タイプの2種類から選べるのも嬉しいポイント。ストレスで寝つきが悪いと感じる方や、忙しい毎日で心身の疲れを感じている方におすすめです。
⑤ DHC グッドスリープ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機能性関与成分 | ラフマ由来ヒペロシド, ラフマ由来イソクエルシトリン |
| 届出表示 | 睡眠の質(眠りの深さ)の向上に役立つことが報告されている |
| 形状 | カプセル |
| 1日の目安 | 1粒 |
| 参照元 | 株式会社ディーエイチシー公式サイト、消費者庁 機能性表示食品届出情報 |
眠りの深さに特化してアプローチしたい方におすすめのサプリです。機能性関与成分として、古くから健康に役立つハーブとして知られるラフマから抽出した「ラフマ由来ヒペロシド」と「ラフマ由来イソクエルシトリン」を配合。これらの成分には、睡眠の質(眠りの深さ)を高める機能が報告されています。1日1粒目安と手軽に続けやすい点も魅力です。夜中に目が覚めやすい、朝になっても眠りが浅い感じがするといった悩みを抱える方が、深い眠りを目指すために試してみる価値のある製品です。
⑥ 大塚製薬 賢者の快眠 睡眠リズムサポート
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機能性関与成分 | アスパラガス由来含プロリン-3-アルキルジケトピペラジン |
| 届出表示 | 就寝・起床リズムを整えることにより、睡眠の質を高めること(起床時の睡眠への満足感)をサポートする機能、休日明けの心の健康(楽しい気分、いきいきとした気分)を維持する機能 |
| 形状 | スティック(粉末) |
| 1日の目安 | 1本 |
| 参照元 | 大塚製薬株式会社公式サイト、消費者庁 機能性表示食品届出情報 |
乱れがちな睡眠リズムを整えたい方に特に注目してほしいユニークな製品です。アスパラガスから発見された希少成分「アスパラガス由来含プロリン-3-アルキルジケトピペラジン」を配合。この成分は、身体の持つ睡眠と覚醒の切り替えの仕組みをサポートし、就寝・起床リズムを整えることで睡眠の質を高める機能が報告されています。さらに、「休日明けの心の健康を維持する」というユニークな機能性も。週末に夜更かしをしてしまい、月曜の朝がつらいといった方にぴったりのサプリメントです。
⑦ 小林製薬 ナイトミン 眠る力
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機能性関与成分 | クロセチン |
| 届出表示 | 良質な眠りをサポートする(睡眠の質を高め、中途覚醒回数を減らし、起床時の眠気を緩和する)ことが報告されている |
| 形状 | ソフトカプセル |
| 1日の目安 | 1粒 |
| 参照元 | 小林製薬株式会社公式サイト、消費者庁 機能性表示食品届出情報 |
「夜中に目が覚めてしまう」「朝の眠気がつらい」という具体的な悩みに応える製品です。機能性関与成分として、クチナシ由来の「クロセチン」を7.5mg配合。クロセチンの働きにより、中途覚醒の回数を減らし、起床時の眠気を和らげることで、良質な眠りをサポートします。加齢などによって眠りが浅くなりがちな方や、朝すっきりと活動を開始したい方に適しています。ソフトカプセルで飲みやすく、1日1粒という手軽さも継続しやすいポイントです。
⑧ グリコ パワープロダクション グリシンプレミアム
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機能性関与成分 | グリシン |
| 届出表示 | 睡眠の質を高める(熟眠感の改善、睡眠リズムの改善)、起床時の爽快感のある良い目覚めを助ける、日中の眠気の改善、疲労感の軽減、作業効率の向上に役立つ機能 |
| 形状 | スティック(粉末) |
| 1日の目安 | 1本 |
| 参照元 | 江崎グリコ株式会社公式サイト、消費者庁 機能性表示食品届出情報 |
スポーツサプリメントの知見を活かした、アスリートや日常的に運動をする方にもおすすめの製品です。主成分は「グリシン」3000mgで、深い眠りをもたらし、睡眠の質を高めることで、翌朝のすっきりとした目覚めをサポートします。日中のパフォーマンス向上まで見据えた機能性表示が特徴で、質の高い休息を求める方に最適です。休息をサポートするGABAやL-トリプトファンなども配合されており、総合的なコンディショニングを重視する方に選ばれています。
⑨ リフレ ぐっすりずむ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機能性関与成分 | L-テアニン |
| 届出表示 | 起床時の疲労感を軽減することが報告されている |
| 形状 | 錠剤 |
| 1日の目安 | 1粒 |
| 参照元 | 株式会社リフレ公式サイト、消費者庁 機能性表示食品届出情報 |
「朝、起きた時のだるさや疲れが気になる」という方にシンプルな機能で応えるサプリメントです。機能性関与成分「L-テアニン」を200mg配合し、起床時の疲労感を軽減することに特化しています。1日1粒目安で続けやすく、価格も手頃なため、睡眠サプリを初めて試す方にもおすすめです。余計な成分は含まず、L-テアニンの効果をシンプルに実感したい方に適しています。
⑩ サントリーウエルネス セサミンEX
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機能性関与成分 | セサミン類 |
| 届出表示 | 身体的・精神的疲労感を軽減する機能、年齢とともに低下する睡眠の質(寝つき、眠りの深さ、寝覚め)を高めるのに役立つ機能、年齢とともに低下する血管のしなやかさの維持に役立つ機能、年齢とともに低下する認知機能の一部である注意力の維持に役立つ機能 |
| 形状 | ソフトカプセル |
| 1日の目安 | 3粒 |
| 参照元 | サントリーウエルネス株式会社公式サイト、消費者庁 機能性表示食品届出情報 |
加齢に伴う複合的な悩みに応えるエイジングケアサプリです。ゴマの希少成分「セサミン類」を機能性関与成分とし、年齢とともに低下しがちな睡眠の質(寝つき、眠りの深さ、寝覚め)を高める機能が報告されています。それに加え、疲労感の軽減、血管のしなやかさの維持、注意力の維持など、複数の機能性が認められている点が最大の特徴です。睡眠だけでなく、総合的な健康維持や若々しさを目指す中高年の方に特に支持されています。
⑪ ファイン グリシン3000&テアニン200
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機能性関与成分 | グリシン, L-テアニン |
| 届出表示 | グリシン:すみやかに深睡眠をもたらし、睡眠の質を向上(熟眠感の改善)、起床時の爽快感のある良い目覚めをサポート。L-テアニン:一過性の作業にともなうストレスをやわらげる機能 |
| 形状 | スティック(粉末) |
| 1日の目安 | 1本 |
| 参照元 | 株式会社ファイン公式サイト、消費者庁 機能性表示食品届出情報 |
深い眠りをサポートする「グリシン」と、リラックスを促す「L-テアニン」を同時に摂取できる製品です。「グリシン」を3000mg、「L-テアニン」を200mgと、どちらの成分も十分な量が配合されています。グリシンが深い眠りへと導き、L-テアニンが日中のストレスを和らげるという、睡眠とストレスの両面にアプローチできるのが強みです。レモン風味の粉末で飲みやすく、コストパフォーマンスにも優れているため、人気の高い製品の一つです。
⑫ UHA味覚糖 特濃ミルク8.2 ラムレーズン
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機能性関与成分 | GABA |
| 届出表示 | 睡眠の質(眠りの深さ)の向上に役立つ機能、仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する機能 |
| 形状 | キャンディ |
| 1日の目安 | 3粒 |
| 参照元 | UHA味覚糖株式会社公式サイト、消費者庁 機能性表示食品届出情報 |
サプリメントを飲む習慣がない方でも、おやつ感覚で手軽に取り入れられるのが、このキャンディタイプの機能性表示食品です。3粒で機能性関与成分「GABA」を100mg摂取でき、睡眠の質の向上と、一時的なストレス・疲労感の緩和が期待できます。人気の「特濃ミルク8.2」シリーズなので味は保証付き。夜のリラックスタイムに、温かい飲み物と一緒に楽しむのもおすすめです。サプリの錠剤や粉末が苦手な方に最適な選択肢です。
⑬ ディアナチュラゴールド グリシン3000&テアニン200
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機能性関与成分 | グリシン, L-テアニン |
| 届出表示 | グリシン:睡眠の質を高める(熟眠感の改善、中途覚醒回数の減少)。L-テアニン:起床時の疲労感を軽減する |
| 形状 | スティック(粉末) |
| 1日の目安 | 1本 |
| 参照元 | アサヒグループ食品株式会社公式サイト、消費者庁 機能性表示食品届出情報 |
大手サプリメントブランド「ディアナチュラ」のゴールドシリーズから出ている、グリシンとテアニンのダブル配合製品です。グリシン3000mgが熟眠感を改善し、中途覚醒を減らすことで睡眠の質を高め、L-テアニン200mgが起床時の疲労感を軽減します。睡眠の「深さ」と「目覚めのすっきり感」の両方にアプローチする設計が特徴です。品質と安全性に定評のあるブランドで、安心して選びたい方におすすめ。グレープフルーツ味でさっぱりと飲めます。
⑭ 北の快適工房 北の大地の夢しずく
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機能性関与成分 | アスパラガス由来含プロリン-3-アルキルジケトピペラジン |
| 届出表示 | 就寝・起床リズムを整えることにより、睡眠の質を高めること(起床時の睡眠への満足感)をサポート、休日明けの心の健康(楽しい気分、いきいきとした気分)を維持 |
| 形状 | スティック(ドリンク) |
| 1日の目安 | 1本 |
| 参照元 | 株式会社北の達人コーポレーション公式サイト、消費者庁 機能性表示食品届出情報 |
大塚製薬の「賢者の快眠」と同じく、アスパラガス由来の独自成分で睡眠リズムにアプローチする製品です。こちらは飲み切りやすいドリンクタイプで、グレープフルーツ風味で提供されています。「就寝・起床リズムを整える」ことで睡眠の質を高め、特に「休日明けの心の健康維持」に役立つ点がユニークです。不規則な生活で体内時計が乱れがちな方や、週末と平日のギャップに悩む方に適しています。
⑮ オリヒロ 賢人の快眠
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機能性関与成分 | ラフマ由来ヒペロシド, ラフマ由来イソクエルシトリン, GABA |
| 届出表示 | ラフマ由来成分:睡眠の質(眠りの深さ)の向上。GABA:仕事や勉強による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和 |
| 形状 | スティック(粉末) |
| 1日の目安 | 1本 |
| 参照元 | オリヒロプランデュ株式会社公式サイト、消費者庁 機能性表示食品届出情報 |
眠りの深さとストレス緩和、2つの悩みに1本で対応できるハイブリッドな製品です。睡眠の質を高める「ラフマ由来成分」と、ストレスや疲労感を和らげる「GABA」という、異なるアプローチを持つ2つの機能性関与成分を配合しています。「ストレスで眠りが浅くなっている」と感じる方に最適な組み合わせと言えるでしょう。水なしでも飲めるナイトリフレッシュ風味の顆粒タイプで、手軽に摂取できるのも便利です。
サプリだけに頼らない!睡眠の質を高める生活習慣
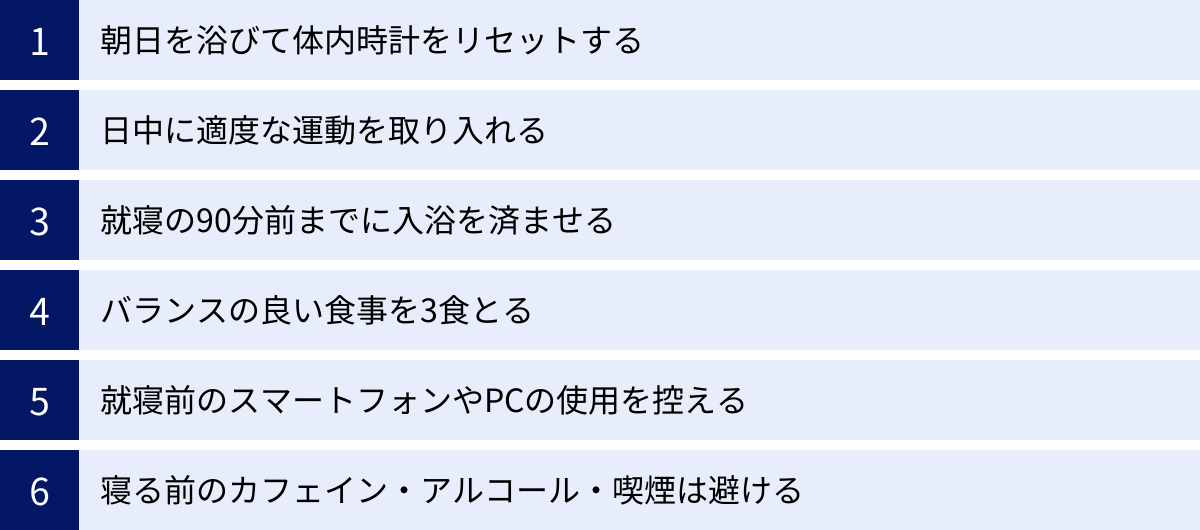
睡眠サプリは質の高い睡眠を得るための強力なサポーターですが、それだけに頼るのは根本的な解決にはなりません。最も重要なのは、日々の生活習慣を見直し、睡眠に適した体内環境を自ら作り出すことです。ここでは、今日から実践できる睡眠の質を高めるための6つの生活習慣を紹介します。
朝日を浴びて体内時計をリセットする
私たちの体には、約24時間周期でリズムを刻む「体内時計(サーカディアンリズム)」が備わっています。この時計が、眠りや目覚め、体温、ホルモン分泌などをコントロールしています。この体内時計を毎朝正しくリセットすることが、質の高い睡眠への第一歩です。
そのリセットのスイッチとなるのが「太陽の光」です。朝、目から太陽の光が入ると、脳にある体内時計の中枢が刺激され、心身を活動モードにするホルモン「セロトニン」の分泌が活発になります。そして、このセロトニンは、約14〜16時間後に睡眠を促すホルモン「メラトニン」に変化します。
つまり、朝にしっかりと光を浴びることが、夜の自然な眠気に繋がるのです。毎朝起きたら、まずはカーテンを開けて部屋に光を取り込みましょう。理想は、15分〜30分程度、屋外で朝日を浴びることです。通勤時に一駅分歩いたり、ベランダで軽いストレッチをしたりするだけでも効果があります。曇りや雨の日でも、室内照明よりはるかに強い光量があるので、屋外に出る習慣をつけることが大切です。
日中に適度な運動を取り入れる
日中の適度な運動は、睡眠の質を向上させる上で非常に効果的です。運動には、以下のようなメリットがあります。
- 寝つきを良くする: 運動によって上昇した体温が、夜にかけて下がっていく過程で自然な眠気を誘発します。
- 深い睡眠を増やす: 定期的な運動習慣は、脳と体の休息に不可欠な「深睡眠(徐波睡眠)」の時間を増やすことが分かっています。
- ストレス解消: 運動は、ストレスホルモンであるコルチゾールを減少させ、気分をリフレッシュさせる効果があります。ストレスによる不眠の改善にも繋がります。
おすすめは、ウォーキング、ジョギング、ヨガ、水泳といった有酸素運動です。週に3〜5回、1回30分程度を目安に、少し汗ばむくらいの強度で続けるのが理想です。
ただし、運動するタイミングには注意が必要です。就寝直前の激しい運動は、交感神経を刺激して体を興奮状態にしてしまい、かえって寝つきを悪くします。運動は、就寝の3時間前までには終えるようにしましょう。夕方から夜の初めの時間帯に行うのが最も効果的とされています。
就寝の90分前までに入浴を済ませる
質の高い睡眠には、体温の変化、特に体の内部の温度である「深部体温」が深く関わっています。人は、この深部体温が低下するタイミングで眠気を感じ、スムーズに眠りに入ることができます。
このメカニズムを効果的に利用するのが、就寝前の入浴です。就寝の約90分前に、38〜40℃程度のぬるめのお湯に15〜20分ほど浸かるのがおすすめです。入浴によって一時的に深部体温が0.5℃ほど上昇し、その後、お風呂から上がって体温が急降下するタイミングで、強い眠気が訪れます。
熱すぎるお湯(42℃以上)や長すぎる入浴は、交感神経を刺激してしまい逆効果になる可能性があるので注意しましょう。また、シャワーだけで済ませると体の芯まで温まらないため、深部体温を効果的に上げるには、湯船に浸かることが重要です。入浴は心身をリラックスさせる効果もあるため、一日の疲れを癒す習慣としても最適です。
バランスの良い食事を3食とる
食生活と睡眠は密接に関連しています。特に、睡眠ホルモン「メラトニン」の材料となる栄養素を意識的に摂取することが大切です。
メラトニンは、「トリプトファン(必須アミノ酸)」→「セロトニン(神経伝達物質)」→「メラトニン(睡眠ホルモン)」という順序で体内で合成されます。トリプトファンは体内では作れないため、食事から摂取する必要があります。
トリプトファンを多く含む食品には、乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズ)、大豆製品(豆腐、納豆、味噌)、バナナ、ナッツ類、赤身魚などがあります。これらの食品を、朝食や昼食で摂ることで、日中にセロトニンが十分に作られ、夜のメラトニン分泌に備えることができます。
また、夕食のタイミングも重要です。就寝直前に食事を摂ると、消化活動のために胃腸が働き続け、脳や体が休まらず、睡眠の質が低下します。夕食は、就寝の3時間前までに済ませるのが理想です。もし、夜遅くに小腹が空いた場合は、消化の良いホットミルクやハーブティーなどがおすすめです。
就寝前のスマートフォンやPCの使用を控える
現代人にとって最も難しい習慣の一つかもしれませんが、睡眠の質を考える上で極めて重要です。スマートフォンやPC、テレビなどの画面から発せられる「ブルーライト」は、太陽光に多く含まれる波長の短い光で、体内時計に強い影響を与えます。
夜にブルーライトを浴びると、脳は「まだ昼間だ」と錯覚し、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を強力に抑制してしまいます。その結果、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりするのです。
理想は、就寝の1〜2時間前には、デジタルデバイスの使用を完全にやめることです。どうしても使用する必要がある場合は、画面の明るさを最低限に落としたり、多くのデバイスに搭載されている「ナイトモード」や「ブルーライトカット機能」を活用したりするだけでも効果があります。寝室にスマートフォンを持ち込まない、充電はリビングで行うといったルールを作るのも良い方法です。
寝る前のカフェイン・アルコール・喫煙は避ける
就寝前の嗜好品は、睡眠に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
- カフェイン: コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには強力な覚醒作用があります。その効果は個人差がありますが、摂取後30分〜1時間でピークに達し、4〜6時間程度持続すると言われています。質の良い睡眠のためには、遅くとも就寝の4〜5時間前からはカフェインの摂取を控えるのが賢明です。
- アルコール: 「寝酒をするとよく眠れる」というのは大きな誤解です。アルコールは一時的に寝つきを良くする効果がありますが、睡眠の後半部分で中途覚醒を増やし、レム睡眠を抑制するなど、睡眠の構造を大きく乱します。結果として、眠りが浅くなり、朝起きた時に疲労感が残る原因となります。
- 喫煙: タバコに含まれるニコチンには、カフェインと同様に覚醒作用があります。ニコチンが切れると離脱症状で目が覚めやすくなることもあり、睡眠を断続的にしてしまいます。
これらの嗜好品は、睡眠の質を直接的に低下させる要因です。質の高い睡眠を求めるなら、就寝前の摂取は避けるようにしましょう。
睡眠サプリに関するよくある質問
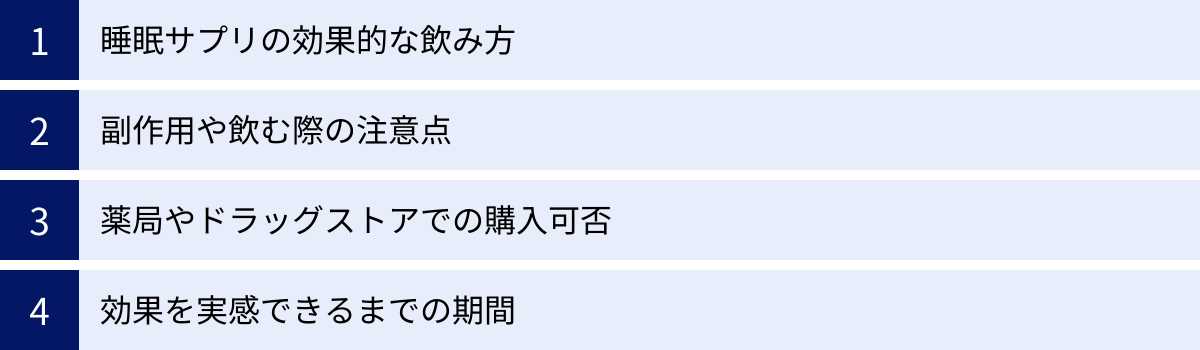
睡眠サプリを始めるにあたって、多くの人が抱く疑問や不安があります。ここでは、特に多く寄せられる質問について、分かりやすくお答えします。
睡眠サプリはいつ飲むのが効果的ですか?
睡眠サプリを飲むタイミングは、その製品に含まれる成分や設計によって異なりますが、一般的には就寝の30分~1時間前に飲むことが推奨されるケースが多いです。これは、摂取した成分が体内で吸収され、効果を発揮し始めるまでの時間を考慮しているためです。
例えば、リラックス効果を期待するL-テアニンや、深部体温の低下を促すグリシンなどは、眠りにつく前のタイミングで摂取することで、スムーズな入眠をサポートします。
しかし、これはあくまで一般的な目安です。最も重要なのは、購入した製品のパッケージや公式サイトに記載されている「お召し上がり方」や「1日の摂取目安量」を必ず確認し、その指示に従うことです。メーカーが、自社製品の成分特性や臨床試験の結果に基づいて、最も効果的な摂取タイミングを推奨しているためです。
また、GABAのように日中のストレス緩和効果も期待できる成分の場合、ストレスを感じる日中の時間帯に飲むことを想定した製品もあります。自分の目的と製品の特性を理解し、推奨された飲み方を守ることが、効果を最大限に引き出す鍵となります。
副作用や飲む際の注意点はありますか?
睡眠サプリは「食品」に分類されるため、医薬品のような重篤な副作用が起こることは基本的に考えにくいです。しかし、食品である以上、体質や体調によっては体に合わない可能性はゼロではありません。
- 体質による不適合: 特定の成分に対してアレルギーがある場合や、胃腸がデリケートな方が摂取した場合、まれにアレルギー反応や胃の不快感、下痢などを引き起こすことがあります。初めて飲む際は、少量から試してみるのも一つの方法です。
- 過剰摂取のリスク: 「たくさん飲めば効果も高まるだろう」と考えて、推奨される1日の摂取目安量を超えて飲むのは絶対にやめましょう。過剰摂取は、かえって体調を崩す原因となったり、予期せぬ健康被害に繋がったりする可能性があります。必ず目安量を守ってください。
- 薬との飲み合わせ: 何らかの病気で治療中の方や、医薬品を服用中の方がサプリメントを摂取する場合、薬の効果に影響を与えたり、相互作用を起こしたりする可能性があります。
- 妊娠・授乳中の方: 妊娠中や授乳中は、お母さんの体が非常にデリケートな時期であり、赤ちゃんへの影響も考慮する必要があります。安全性が確認されていない成分も多いため、自己判断での摂取は避けるべきです。
結論として、持病がある方、医薬品を服用中の方、妊娠・授乳中の方、その他健康に不安がある方は、睡眠サプリを摂取する前に、必ずかかりつけの医師、薬剤師、または登録販売者に相談してください。
薬局やドラッグストアなど市販で購入できますか?
はい、この記事で紹介したような睡眠サプリの多くは、全国の薬局やドラッグストア、スーパーマーケット、コンビニエンスストアなどで市販されています。 気軽に立ち寄って、実際に商品を手に取り、パッケージの表示などを確認しながら選べるのが市販品のメリットです。
ただし、店舗の規模や品揃えによっては、取り扱いがない商品もあります。また、一部の製品は、メーカーの公式サイトや大手オンラインモール(Amazon、楽天市場など)での通信販売が中心となっている場合もあります。
オンラインストアでは、定期購入割引が適用されたり、限定のキャンペーンが実施されたりすることもあるため、継続して利用する場合は、公式サイトをチェックしてみるのがおすすめです。まずは近所のドラッグストアで試してみて、気に入った商品をオンラインの定期便で継続するといった使い分けも賢い方法です。
効果はどのくらいの期間で実感できますか?
睡眠サプリの効果の現れ方には、非常に大きな個人差があります。 また、医薬品のように飲んだらすぐに眠くなる、といった即効性を期待するものではありません。
数日で「なんとなく目覚めが良くなった気がする」と感じる方もいれば、数週間から1~2ヶ月程度、継続して摂取することで、徐々に「そういえば、夜中に起きることが減ったな」「日中の眠気が軽くなった」といった変化を実感する方もいます。
効果を実感するまでの期間は、その人の元々の睡眠の状態、体質、生活習慣、ストレスの度合いなど、さまざまな要因に左右されます。
重要なのは、焦らずに一定期間、継続して摂取してみることです。そして、それと同時に、本記事で紹介したような生活習慣の改善にも取り組むことが、効果を実感するための最短ルートと言えます。サプリはあくまで「サポート」役です。食事、運動、入浴といった基本的な生活を見直しながらサプリを併用することで、相乗効果が期待でき、より早く、より確かな変化を感じられる可能性が高まります。まずは1ヶ月を目安に、生活改善とセットで試してみることをおすすめします。
まとめ
質の高い睡眠は、私たちの心と体の健康、そして日々の生産性を支える基盤です。この記事では、睡眠の悩みを抱える方々の一助となるべく、睡眠の質を高めるサプリメントについて、その基本から選び方、おすすめ製品、そしてサプリだけに頼らない生活習慣まで、多角的に解説してきました。
最後に、本記事の重要なポイントを振り返ります。
- 睡眠サプリは「機能性表示食品」を選ぼう: 科学的根拠に基づいた効果が表示されており、安心して選ぶための基準となります。医薬品とは異なり、あくまで睡眠の質を「サポート」する食品です。
- 自分の悩みに合った「成分」で選ぼう: 「眠りの深さ」にはL-テアニンやグリシン、「ストレス」にはGABA、「加齢による悩み」にはセサミン類など、自分の課題に合った成分を選ぶことが成功の鍵です。
- 継続することが大切: サプリは継続することで効果が期待できます。無理なく続けられる形状や価格、そして安全性の高いGMP認定工場製造の製品を選ぶ視点を持ちましょう。
- サプリはあくまで補助。生活習慣の改善が本質: 朝日を浴びる、適度な運動、正しい入浴、バランスの取れた食事など、根本的な生活習慣の見直しこそが、最も効果的で持続可能な睡眠改善策です。
睡眠の悩みは人それぞれです。この記事で紹介した情報が、あなた自身の睡眠を見つめ直し、自分に最適な解決策を見つけるためのヒントとなれば幸いです。
まずは、できそうな生活習慣の改善を一つからでも始めてみませんか。そして、その努力を後押しするパートナーとして、自分に合った睡眠サプリを上手に活用してみてください。
質の高い睡眠を取り戻し、活力に満ちた、すっきりとした毎日を送るための一歩を、今日から踏み出しましょう。