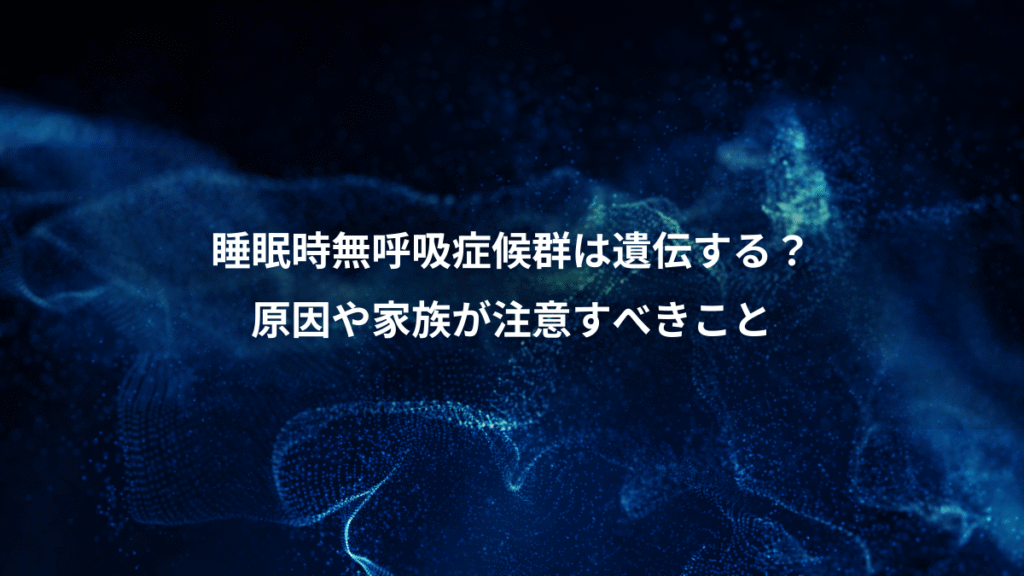「家族が大きないびきをかいていて、時々呼吸が止まっているように見える」「父親が睡眠時無呼吸症候群(SAS)と診断されたけれど、自分もなる可能性があるのだろうか?」
睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に何度も呼吸が止まったり、浅くなったりする病気です。この病気は、日中の激しい眠気や集中力の低下を引き起こすだけでなく、放置すると高血圧、心臓病、脳卒中といった命に関わる生活習慣病のリスクを高めることが知られています。
ご家族に睡眠時無呼吸症候群の方がいると、「この病気は遺伝するのではないか」と不安に思う方も少なくないでしょう。結論から言うと、睡眠時無呼吸症候群という病気そのものが直接遺伝するわけではありません。しかし、病気になりやすい骨格や体質といった「素因」が遺伝する可能性は十分にあります。
この記事では、睡眠時無呼吸症候群と遺伝の複雑な関係性について、医学的な観点から深く掘り下げて解説します。遺伝が関係する要因、それ以外の主な原因、子供の場合に特に注意すべき点、そしてご自身やご家族が「もしかして?」と思った時にできることまで、網羅的にご紹介します。
この記事を最後まで読めば、睡眠時無呼吸症候群と遺伝に関する正しい知識が身につき、ご自身や大切なご家族の健康を守るための具体的な第一歩を踏み出せるはずです。
目次
睡眠時無呼吸症候群と遺伝の関係

睡眠時無呼吸症候群(SAS: Sleep Apnea Syndrome)と遺伝の関係は、多くの人が疑問に思う点です。「親がSASだから自分もきっと…」と心配になるのも無理はありません。しかし、この関係性は「病気がそのまま遺伝する」という単純なものではありません。ここでは、その複雑な関係を正しく理解するために、「病気そのものの遺伝」と「なりやすい体質の遺伝」という2つの側面に分けて詳しく解説します。
睡眠時無呼吸症候群そのものは遺伝しない
まず最も重要な結論として、睡眠時無呼吸症候群という病気そのものが、特定の遺伝子によって親から子へ直接的に受け継がれる「遺伝病」ではありません。 遺伝病と聞くと、例えばメンデルの法則に従うような、特定の遺伝子の変異が原因で高い確率で発症する疾患を思い浮かべるかもしれませんが、SASはそうした単一遺伝子疾患とは異なります。
SASは、さまざまな要因が複雑に絡み合って発症する「多因子疾患」に分類されます。これは、遺伝的な素因(なりやすさ)に加えて、肥満、加齢、生活習慣(飲酒や喫煙)、骨格の特徴といった後天的な「環境因子」が複数重なり合うことで、発症に至る病気だということです。
では、なぜ「SASは遺伝する」というイメージが広まっているのでしょうか。その理由の一つに、「家族内集積性」が挙げられます。これは、特定の病気が血縁関係のある家族内で多発する傾向のことです。SASの患者さんの家族を調べてみると、確かに血縁者にもSASの人が多いという報告は少なくありません。
しかし、これは病気の遺伝子が受け継がれているからというよりは、家族間で顔や顎の骨格が似ることや、同じような食生活や生活スタイルを送ることで、結果的に肥満などのリスク因子を共有しやすいためと考えられています。例えば、家族みんなで脂っこい食事や濃い味付けを好む家庭では、家族全員が肥満傾向になりやすく、それがSASの発症につながる可能性があります。つまり、病気が遺伝したのではなく、病気を引き起こす「環境」が家族内で似通っている結果、発症が集中して見られることがあるのです。
この点を理解することは非常に重要です。なぜなら、「遺伝だから仕方ない」と諦めるのではなく、遺伝以外の要因、特に自分でコントロール可能な生活習慣などを見直すことで、発症を予防したり、症状を改善したりできる可能性が大いにあることを意味するからです。
病気になりやすい体質や骨格は遺伝する可能性がある
睡眠時無呼吸症候群そのものは遺伝しない一方で、SASを発症しやすくする「身体的な特徴」や「体質」、すなわち遺伝的素因が親から子へ受け継がれる可能性は十分にあります。 こちらが、SASと遺伝を語る上での核心部分です。
具体的に遺伝する可能性がある「なりやすさ」の要因は、主に以下の2つが挙げられます。
- 顔や顎の骨格
- 肥満になりやすい体質
顔の形や顎の大きさ、首の長さといった骨格は、親から子へと似る傾向が強いことは誰もが経験的に知っているでしょう。そして、これらの骨格の特徴は、空気の通り道である「上気道」の広さに直接影響します。例えば、下顎が小さい、下顎が後方に引っ込んでいる、首が短いといった骨格的な特徴は、気道を狭くする原因となり、SASの強力なリスク因子となります。もしご両親がこのような骨格の特徴を持ち、SASを発症しているのであれば、そのお子さんも同様の骨格を受け継ぎ、SASになりやすい素地を持っている可能性があるのです。
また、「太りやすさ」という体質も遺伝的な影響を受けることが科学的に明らかになっています。基礎代謝の高さや、脂肪の燃焼効率、食欲をコントロールするホルモンの働きなどには、遺伝子が関与しています。親が「あまり食べていないのに太りやすい」という体質であれば、子供もその体質を受け継いでいる可能性があります。そして、肥満はSASの最大の原因の一つであるため、肥満になりやすい体質は、間接的にSASのリスクを高める遺伝的要因と言えます。
まとめると、睡眠時無呼吸症候群と遺伝の関係は、「病気そのものではなく、病気を引き起こすリスクとなる骨格や体質が遺伝する」と理解するのが最も正確です。家族にSASの患者さんがいる場合、それは自分にとって重要なサインと捉えるべきです。遺伝的素因を持っている可能性を自覚し、特に体重管理や生活習慣に注意を払うことで、発症を未然に防いだり、早期発見につなげたりすることが可能になります。遺伝は運命ではなく、あくまでリスクの一つ。そのリスクを知り、正しく対策を講じることが、健康を守る上で何よりも大切なのです。
遺伝が関係する睡眠時無呼吸症候群の2つの要因
前章で、睡眠時無呼吸症候群(SAS)そのものではなく、「なりやすい素因」が遺伝する可能性について述べました。ここでは、その代表的な2つの遺伝的要因である「顔や顎の骨格」と「肥満になりやすい体質」について、それぞれがどのようにSASの発症に関わっているのかを、より深く掘り下げて解説します。これらの要因を理解することは、ご自身のSASリスクを客観的に評価し、適切な対策を考える上で非常に役立ちます。
① 顔や顎の骨格
顔や顎の骨格は、親子の顔立ちが似るように、遺伝の影響を強く受ける部分です。そして、この骨格の形状が、空気の通り道である「上気道」の広さを決定づける極めて重要な要素となります。特に、以下のような骨格的特徴は、上気道を狭くし、SASのリスクを著しく高めることが知られています。
- 下顎が小さい(小顎症)
- 下顎が後方に位置している(下顎後退症)
- 首が短くて太い
- 顔の奥行きが浅い
これらの骨格がなぜ問題なのでしょうか。そのメカニズムを理解するためには、睡眠中の私たちの喉の中で何が起こっているかを想像する必要があります。
人が眠りにつくと、全身の筋肉が緩みます。これには、喉の周りや舌を支えている筋肉も含まれます。通常であれば、筋肉が緩んでも気道は十分に確保されています。しかし、元々骨格的に気道が狭い人の場合、筋肉の弛緩によって舌が喉の奥に落ち込み(舌根沈下)、気道を塞いでしまうのです。これが、閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)の典型的な発生メカニズムです。
例えば、「下顎が小さい」または「下顎が後退している」と、舌が収まるスペースそのものが狭くなります。そのため、仰向けに寝た際に、舌が後方へ移動しやすく、容易に気道を閉塞させてしまいます。また、「首が短くて太い」場合、首周りの軟部組織(脂肪など)が多くなりがちで、これが外側から気道を圧迫する原因となります。
特に、日本人を含むアジア人は、欧米人と比較して骨格的に顎が小さく、顔の奥行きが浅い傾向があるため、肥満でなくてもSASを発症しやすい人種であると言われています。欧米ではSAS患者の多くが重度の肥満を伴いますが、日本では軽度の肥満や、 thậm chí là痩せ型の人でも、骨格的な問題からSASを発症するケースが少なくありません。
ご自身の骨格がリスクに当てはまるか気になる場合は、簡単なチェック方法があります。横顔を見て、鼻の先端と顎の先端を結んだ線を「Eライン(エステティックライン)」と呼びます。このEラインよりも唇が前に出ている場合、下顎が後退している可能性が考えられます。もちろん、これはあくまで簡易的な目安であり、正確な診断には専門医による評価が必要ですが、一つの参考にはなるでしょう。
このように、親から受け継いだ顔や顎の骨格は、自分では変えることのできないSASの素因です。しかし、このリスクを自覚していれば、他のコントロール可能な要因(体重管理、飲酒を控える、横向きで寝るなど)に一層注意を払うことで、発症を予防したり、症状を軽減したりすることが可能になります。
② 肥満になりやすい体質
もう一つの重要な遺伝的要因が「肥満になりやすい体質」です。肥満がSASの最大の原因であることは広く知られていますが、その「太りやすさ」自体に遺伝が関わっていることは、あまり意識されていないかもしれません。
近年の研究により、人の体重や体脂肪率には遺伝的な要因が大きく関与していることが明らかになっています。「肥満遺伝子」と呼ばれるものがいくつか発見されており、これらの遺伝子のタイプによって、太りやすさが変わってくると考えられています。
例えば、以下のような働きを持つ遺伝子が知られています。
- 基礎代謝に関わる遺伝子: 同じ生活をしていても、エネルギー消費量が少なく、脂肪を溜め込みやすい体質になります。
- 脂肪の燃焼・分解に関わる遺伝子: 摂取した脂肪が燃焼されにくく、体脂肪として蓄積されやすい傾向があります。
- 食欲のコントロールに関わる遺伝子: 満腹感を得にくかったり、高カロリーなものを欲しやすかったりする傾向があります。
こうした遺伝子を持つ人は、持たない人と比べて、同じ量の食事をしても太りやすく、一度増えた体重を減らすのにも苦労する可能性があります。もしご両親や血縁者に肥満の人が多い場合、こうした「肥満になりやすい体質」を受け継いでいる可能性が考えられます。
そして、この遺伝的な「太りやすさ」が、SASの発症に直結します。体重が増加し、体に脂肪が蓄積すると、それはお腹周りだけでなく、首周りや喉の内部、舌にまで及びます。
- 首周りの脂肪: 気道を外側から圧迫し、内腔を狭めます。ワイシャツの首回りがきつくなってきたら要注意のサインです。
- 喉や舌への脂肪沈着: 喉の壁(軟口蓋や咽頭壁)や舌そのものが分厚くなり、内側から気道を狭くします。これにより、睡眠中の舌根沈下がより起こりやすくなります。
重要なのは、「肥満遺伝子を持っているから必ず太る」わけではないという点です。遺伝はあくまで「なりやすさ」を決定する要因の一つであり、最終的に肥満になるかどうかは、食生活、運動習慣、ストレス管理といった「環境因子」が大きく影響します。遺伝的に太りやすい体質であっても、バランスの取れた食事と定期的な運動を心がけることで、適正体重を維持し、SASのリスクを大幅に低減させることが可能です。
むしろ、ご自身の遺伝的リスクを認識することは、「自分は他の人より少し体重管理に気をつけなければならない」という意識を持つきっかけとなり、健康的な生活を送るための強い動機付けになり得ます。遺伝的要因を正しく理解し、それを乗り越えるための具体的な行動計画を立てることが、SAS予防の鍵となるのです。
遺伝以外の睡眠時無呼吸症候群の主な原因
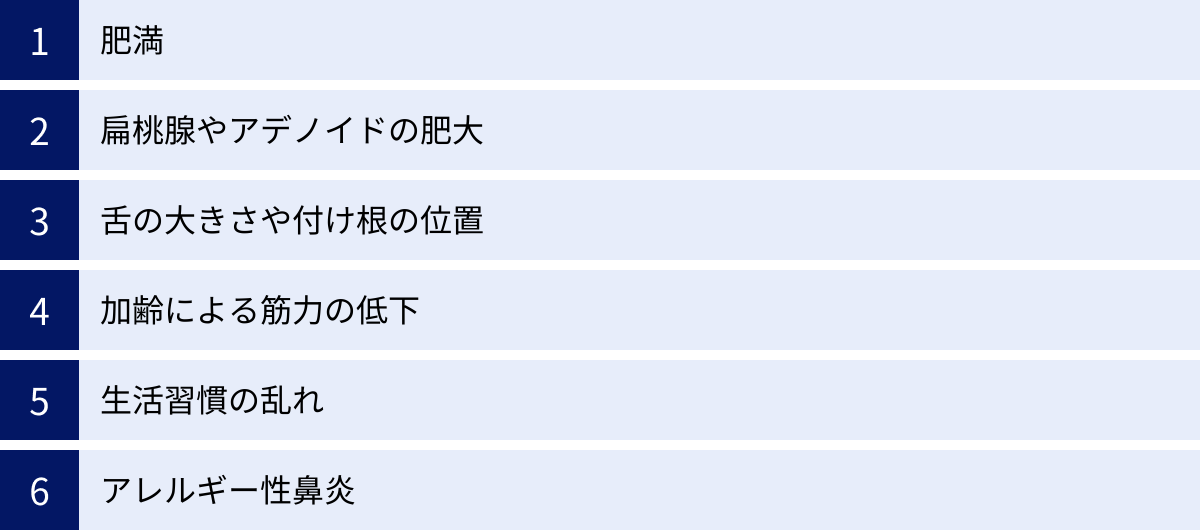
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、遺伝的な素因だけで発症するわけではありません。むしろ、日常生活の中に潜むさまざまな後天的な要因が複雑に絡み合い、発症の引き金となるケースが非常に多いのです。遺伝的なリスクがないと考えている人でも、これらの要因が重なればSASを発症する可能性は十分にあります。ここでは、遺伝以外にSASを引き起こす主な原因を詳しく解説します。ご自身の生活習慣や身体の状態と照らし合わせながら、リスクをチェックしてみましょう。
肥満
肥満は、遺伝的要因を除いても、閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)の最大かつ最も一般的な原因です。 体重が増加し、体脂肪率が高くなると、その影響は全身に及びますが、特に上気道への影響は深刻です。
肥満がSASを引き起こすメカニズムは、主に2つあります。
- 上気道への直接的な脂肪沈着: 体に脂肪がつくと、それはお腹や太ももだけでなく、目に見えない体の内部にも蓄積します。特に、首周り、喉の奥の壁(軟口蓋や咽頭側壁)、そして舌の根元に脂肪が沈着します。これにより、空気の通り道である上気道の内腔が物理的に狭くなります。起きている間は筋肉の力で気道が開かれていますが、睡眠中に筋肉が弛緩すると、この狭くなった気道が完全に塞がってしまうのです。一般的に、体重が10%増加すると、SASの重症度を示すAHI(無呼吸低呼吸指数)が約32%悪化するという報告もあり、体重とSASの密接な関係がうかがえます。
- 胸部・腹部の脂肪による呼吸機能への影響: 腹部に脂肪が多く蓄積する内臓脂肪型肥満の場合、横になるとその脂肪が横隔膜を押し上げ、肺の容積を圧迫します。これにより、一回あたりの換気量が減少し、呼吸機能そのものが低下する傾向があります。これもまた、睡眠中の呼吸を不安定にする一因となります。
肥満の指標であるBMI(Body Mass Index)が25以上になると、SASのリスクが高まり始めるとされています。特にBMIが30を超える高度な肥満では、SASを合併している可能性が非常に高くなります。
扁桃腺やアデノイドの肥大
扁桃腺(口蓋扁桃)やアデノイド(咽頭扁桃)は、喉の奥にあるリンパ組織です。これらが生まれつき大きかったり、炎症によって腫れたりすると、上気道の空間を物理的に狭めてしまい、SASの直接的な原因となります。
この要因は、特に子供のSASにおいて最も一般的な原因として知られています(後述)。しかし、大人であっても、子供の頃から扁桃腺が大きいままの人や、慢性的な炎症で肥大している人は、SASのリスクが高まります。特に、痩せているのに大きないびきをかく、あるいは無呼吸を指摘されるという人は、この扁桃腺やアデノイドの肥大が隠れた原因である可能性があります。鏡で口の奥を覗いたときに、左右の扁桃腺が大きく、中央に迫っているように見える場合は注意が必要です。
舌の大きさや付け根の位置
骨格だけでなく、舌そのものの大きさや形状もSASに関係します。専門的には「巨舌症」と呼ばれる、顎の大きさに比べて舌が相対的に大きい状態も、気道を狭くする要因です。
また、舌の大きさは普通でも、舌の付け根(舌根)が喉の奥の方(後方)に位置している場合、睡眠中に舌が落ち込みやすくなります。これらは解剖学的な個人差であり、遺伝的な影響も考えられますが、肥満によって舌に脂肪がつくことで、後天的に舌が大きくなり、リスクが増大することもあります。
加齢による筋力の低下
年齢を重ねることも、SASの重要なリスク因子です。加齢とともに、全身の筋力が低下していくことは避けられませんが、これは上気道の開存性を維持する筋肉(上気道開大筋群)も例外ではありません。
この筋肉群は、舌や軟口蓋を前方に引きつけ、睡眠中に気道が塞がらないように支える重要な役割を担っています。しかし、加齢によってこの筋力が衰えると、睡眠中の筋肉の弛緩に対して抵抗する力が弱まり、気道が虚脱しやすくなります。これが、高齢になるといびきをかきやすくなったり、SASを発症しやすくなったりする大きな理由です。特に、40代以降からリスクは上昇し始め、60代でピークに達すると言われています。若い頃は問題がなかった人でも、加齢という要因が加わることで、元々持っていた骨格的なリスクなどが顕在化してくるケースも少なくありません。
生活習慣の乱れ
日々の何気ない生活習慣の中にも、SASのリスクを高める要因が数多く潜んでいます。これらは意識的に改善できる部分であり、治療においても非常に重要なポイントとなります。
- アルコール摂取: 就寝前の飲酒は特に危険です。アルコールには筋肉を弛緩させる作用があるため、上気道開大筋群の働きを弱め、舌根沈下や気道の閉塞を著しく助長します。普段はいびきをかかない人でも、飲酒後には大きないびきをかくのはこのためです。
- 喫煙: 喫煙は、喉の粘膜に慢性的な炎症を引き起こします。炎症によって粘膜が腫れると、気道が狭くなり、SASを悪化させます。また、喫煙は睡眠の質そのものを低下させることも知られています。
- 睡眠薬・精神安定剤の服用: 一部の睡眠薬や精神安定剤には、アルコールと同様に筋弛緩作用があります。不眠の改善のために服用した薬が、結果的にSASを誘発・悪化させているケースもあるため、SASが疑われる場合は、必ず医師に服用中の薬を伝える必要があります。
アレルギー性鼻炎
慢性的な鼻詰まり(鼻閉)も、SASの重要な誘因・悪化因子です。アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎(蓄膿症)、鼻中隔弯曲症などによって鼻の通りが悪くなると、人間は無意識に口で呼吸しようとします。
しかし、口呼吸はSASにとって非常に不利な呼吸法です。鼻呼吸の場合、舌は上顎に軽くついた安定した位置にありますが、口呼吸になると、口を開けるために舌の位置が下がり、喉の奥へと落ち込みやすくなります。 これにより、気道が狭くなり、無呼吸が誘発されるのです。常に鼻が詰まっている、朝起きると口がカラカラに乾いているといった症状がある人は、まず鼻の治療を行うことで、いびきや無呼吸が改善するケースも少なくありません。
これらの遺伝以外の要因は、一つひとつは些細に見えるかもしれませんが、複数重なることでSASのリスクを飛躍的に高めます。ご自身の状態を客観的に見つめ直し、改善できる点から取り組むことが、SASの予防と治療の第一歩となります。
子供の睡眠時無呼吸症候群で特に注意すべき原因
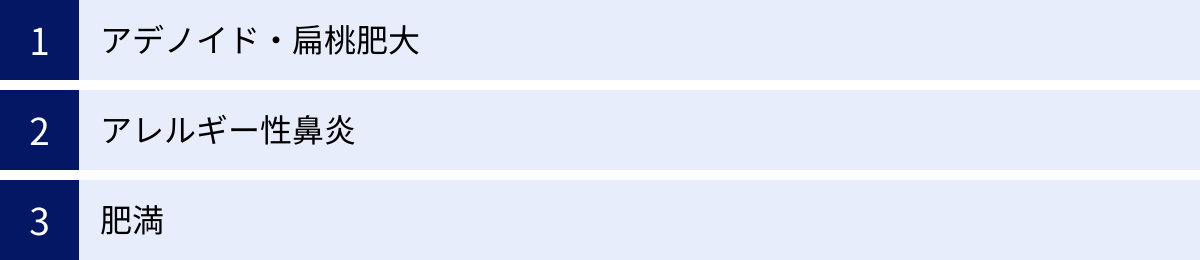
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、大人の病気というイメージが強いかもしれませんが、子供にも発症します。そして、子供のSASは、その原因や体に与える影響において、大人のSASとは異なる特徴を持っています。子供の健やかな成長を妨げる可能性があるため、保護者による早期発見と適切な対応が極めて重要です。ここでは、子供のSASで特に注意すべき3つの主な原因について解説します。
アデノイド・扁桃肥大
子供の閉塞性睡眠時無呼吸症候群における、最も頻度の高い原因がアデノイドと扁桃(口蓋扁桃)の肥大です。
- アデノイド: 鼻の突き当り、喉の一番上にあるリンパ組織で、通常は直接目で見えません。「咽頭扁桃」とも呼ばれます。
- 扁桃: 喉の奥の両脇に見える、こぶのようなリンパ組織です。一般的に「扁桃腺」と呼ばれているものです。
これらの組織は、体内に侵入する細菌やウイルスから体を守る免疫機能の役割を担っており、幼児期(3歳〜6歳頃)に生理的に最も大きくなります。 その後、学童期以降は徐々に小さくなっていくのが一般的です。
問題は、このアデノイドや扁桃が、空気の通り道である上気道の最も狭い部分に存在していることです。そのため、これらが通常よりも大きく肥大すると、気道を物理的に塞いでしまい、いびきや無呼吸を引き起こします。特に子供は大人に比べて気道が細いため、わずかな肥大でも深刻な閉塞につながりやすいのです。
子供のSASは、大人のように「太っているから」ではなく、このアデノイド・扁桃肥大が原因であるケースが大多数を占めるという点が大きな特徴です。したがって、痩せているお子さんでも、大きないびきをかいていればSASの可能性を疑う必要があります。
子供のSASが見過ごされると、成長ホルモンの分泌障害(成長ホルモンは深い睡眠中に多く分泌されるため)、学業成績の低下、集中力の欠如、日中の多動や落ち着きのなさ(ADHDと誤診されることもある)、さらには胸郭の変形(漏斗胸)などを引き起こす可能性があります。お子さんの健やかな心身の発達のために、いびきや無呼吸のサインを見逃さないことが非常に重要です。
アレルギー性鼻炎
アレルギー性鼻炎による慢性的な鼻詰まりも、子供のSASの重要な原因・悪化因子です。大人と同様に、鼻が詰まると口呼吸になります。子供の場合、口呼吸が習慣化すると、SASのリスクを高めるだけでなく、顔の発達にも影響を及ぼすことがあります。
常に口をぽかんと開けている状態が続くと、「アデノイド様顔貌」と呼ばれる特有の顔つき(面長でしまりのない表情、前に突き出た歯など)になる可能性があります。また、慢性的な鼻詰まりは、睡眠の質を低下させ、日中の活動にも悪影響を与えます。
ハウスダストやダニ、スギ花粉などが原因で、お子さんが常に鼻をすすっていたり、鼻をこすっていたり、口を開けて寝ていたりする場合には、まず耳鼻咽喉科で鼻の治療をしっかりと行うことが、SASの予防・改善につながります。アデノイド肥大とアレルギー性鼻炎は合併していることも多く、両方からのアプローチが必要な場合も少なくありません。
肥満
かつては子供のSASの原因として肥満は少数派でしたが、近年、食生活の欧米化や運動不足による小児肥満の増加に伴い、肥満が原因の子供のSASも増加傾向にあります。
大人の場合と同様に、子供でも体重が増加すると首周りや喉に脂肪がつき、気道を狭くします。アデノイドや扁桃肥大といった元々のリスクに肥満が加わることで、症状がさらに重症化するケースも多く見られます。
小児肥満は、SASのリスクを高めるだけでなく、高血圧、脂質異常症、2型糖尿病といった生活習慣病を若いうちから引き起こす原因にもなります。また、小児期の肥満の約70〜80%が成人肥満に移行すると言われており、生涯にわたる健康問題につながる可能性があります。
もしお子さんが肥満傾向にあり、大きないびきをかいている場合は、アデノイド・扁桃肥大の可能性と合わせて、肥満が原因である可能性も考慮する必要があります。この場合、耳鼻咽喉科や小児科での評価とともに、栄養指導や運動習慣の見直しといった、家族ぐるみでの生活習慣の改善が治療の重要な柱となります。
子供のいびきは「疲れているだけ」「成長の証」などと軽視されがちですが、その裏には治療が必要な病気が隠れているかもしれません。特に、呼吸が止まる、息苦しそうにする、陥没呼吸(呼吸のたびに胸や鎖骨の上がへこむ)といった症状が見られる場合は、速やかに専門医に相談することをおすすめします。
もしかして?睡眠時無呼吸症候群の主な症状
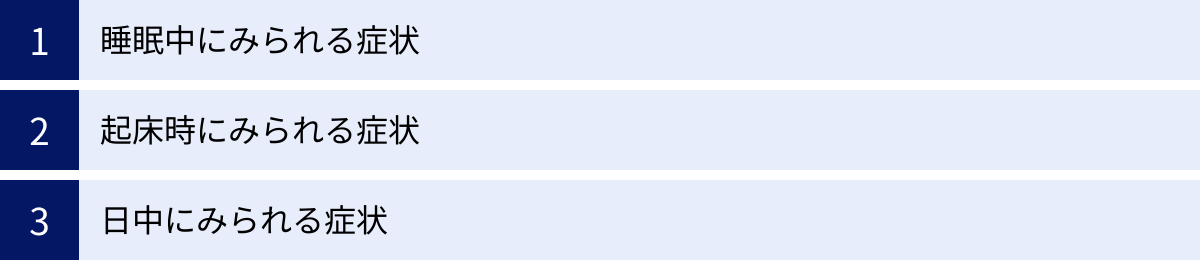
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に起こる病気のため、本人に自覚がないケースが非常に多いのが特徴です。そのため、自分自身や家族の些細なサインに気づくことが、早期発見の第一歩となります。SASの症状は、睡眠中だけでなく、起床時や日中の活動にも現れます。ここでは、時間帯別に主な症状を具体的に解説します。これらの症状に心当たりがないか、チェックしてみましょう。
睡眠中にみられる症状
睡眠中の症状は、本人は気づきにくく、ベッドパートナー(配偶者や家族)によって指摘されることがほとんどです。ご家族に以下の症状が見られたら、SASのサインかもしれません。
- 激しいいびき: SASの最も代表的な症状です。ただの大きないびきではなく、「ガーッ、ガーッ…(いびき)…シーーーン…(呼吸停止)…ゴガッ!ググッ!(あえぎながら呼吸再開)」という、いびきが途中で止まり、しばらく静かになった後、あえぐような大きな音とともに再開する、という特徴的なパターンを示します。この呼吸が止まっている時間が「無呼吸」の状態です。
- 呼吸の停止: 家族が気づく最も重要なサインです。医学的には10秒以上の呼吸停止を「無呼吸」と定義します。呼吸が止まっている間、胸やお腹は呼吸しようと動いているのに、鼻や口からの空気の出入りがない状態です。
- 息苦しさ、あえぎ、窒息感: 無呼吸の状態から呼吸が再開する際に、本人は息苦しさを感じ、むせたり、あえいだりすることがあります。この時、脳が覚醒(マイクロアウェイクニング)するため、睡眠が分断されます。
- 頻繁な寝返り、落ち着きのない睡眠: 苦しさから、何度も寝返りをうったり、手足をばたつかせたりすることがあります。睡眠が浅く、非常に寝相が悪いのも特徴の一つです。
- 頻繁に目が覚める(中途覚醒): 息苦しさで夜中に何度も目が覚めてしまうことがあります。トイレに行きたくて起きることも多いです(後述)。
- 寝汗をかく: 睡眠中に無呼吸状態になると、体は低酸素状態に陥ります。これを補おうと心臓や交感神経が活発に働くため、エネルギーを消費し、多量の寝汗をかくことがあります。
- 夜間頻尿: 睡眠中の低酸素状態は、利尿作用のあるホルモン(心房性ナトリウム利尿ペプチド)の分泌を促進します。そのため、夜中に何度もトイレに起きたくなることがあります。年齢のせいだと思われがちですが、SASが原因であるケースも少なくありません。
起床時にみられる症状
睡眠中に十分な休息がとれていないため、朝起きたときから不調を感じることがあります。
- 頭痛: 特に起床時の頭痛は、SASの典型的な症状の一つです。睡眠中の低酸素状態により、脳の血管が拡張することが原因と考えられています。鎮痛薬を飲んでもすっきりしない鈍い痛みが特徴です。
- 口の渇き、喉の痛み: SASの人は、鼻詰まりなどから口を開けて寝る「口呼吸」になっていることがほとんどです。そのため、朝起きると口の中や喉がカラカラに乾いていたり、ヒリヒリと痛んだりします。
- 熟睡感がない: 何時間寝ても「ぐっすり眠れた」という感覚がなく、疲れが取れていない感じがします。「睡眠時間は足りているはずなのに、なぜかスッキリしない」という感覚は、睡眠の質が著しく低下しているサインです。
- 体が重い、だるい: 睡眠中に体と脳が十分に休息できていないため、朝から倦怠感が強く、活動を始めるのが億劫に感じられます。
日中にみられる症状
SASの最も深刻な影響は、日中の社会生活に現れます。夜間の質の悪い睡眠が、日中のさまざまなパフォーマンス低下につながります。
- 耐えがたいほどの強い眠気: SASの最も代表的な日中の症状です。会議中、パソコン作業中、食事中、さらには人と話している最中など、通常では考えられない状況で、自分でも抗えないほどの強い眠気に襲われます。 最も危険なのが運転中の居眠りで、重大な交通事故の原因となることが社会問題にもなっています。
- 集中力・記憶力の低下: 睡眠不足と低酸素状態は、脳の機能に直接的なダメージを与えます。その結果、仕事や勉強に集中できなくなったり、物覚えが悪くなったり、うっかりミスが増えたりします。
- 全身の倦怠感・疲労感: 常に体がだるく、疲れやすい状態が続きます。週末に寝だめをしても、根本的な原因が解決しないため、疲労感は解消されません。
- 意欲の低下、気分の落ち込み、イライラ: SASによる慢性的な身体的不調は、精神面にも影響を及ぼします。何事にもやる気が出なくなったり、些細なことでイライラしたり、気分が落ち込みやすくなったりします。重症化すると、うつ病を合併することもあります。
これらの症状は、SASが単なる「いびき」の問題ではなく、日中の活動や生活の質(QOL)、さらには生命の安全にまで関わる深刻な病気であることを示しています。もし一つでも当てはまる症状があれば、軽く考えずに専門家への相談を検討することが重要です。
自分でできる睡眠時無呼吸症候群セルフチェックリスト
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は自覚しにくい病気ですが、いくつかの兆候からそのリスクを推測できます。以下のチェックリストは、ご自身やご家族にSASの疑いがあるかどうかを簡易的に判断するためのものです。
このチェックリストは、医学的な診断に代わるものではありません。 あくまで受診を検討する際の目安としてご活用ください。当てはまる項目が多いほどSASの可能性が高まりますので、専門の医療機関に相談することをおすすめします。
| カテゴリ | チェック項目 |
|---|---|
| 睡眠中の様子 | □ 家族やパートナーから「いびきがうるさい」と指摘されたことがある。 |
| □ いびきが止まり、しばらくして大きな呼吸とともに再開することがある。 | |
| □ 睡眠中に息が苦しくなって目が覚めることがある。 | |
| □ 寝汗をひどくかくことがある。 | |
| □ 寝相が悪く、何度も寝返りをうつ。 | |
| □ 夜中に何度もトイレに起きる。 | |
| 起床時の状態 | □ 朝、起きたときに頭痛がする。 |
| □ 朝、起きたときに口や喉がカラカラに乾いている。 | |
| □ 睡眠時間を十分にとっても、寝た気がしない、熟睡感がない。 | |
| □ 朝から体がだるく、疲れが取れていない感じがする。 | |
| 日中の状態 | □ 日中、特に会議中や運転中などに強い眠気に襲われる。 |
| □ 集中力が続かず、仕事や家事でミスが増えた。 | |
| □ 最近、物忘れがひどくなったと感じる。 | |
| □ なんとなく意欲がわかず、気分が落ち込みがちだ。 | |
| 身体的な特徴 | □ BMIが25以上である。(BMI = 体重kg ÷ (身長m × 身長m)) |
| □ 首が短く、がっしりしている。または首周りが太い。(男性: 43cm以上, 女性: 38cm以上が目安) | |
| □ 顎が小さい、または下顎が後退している(受け口ではない)。 | |
| □ 鼻がよく詰まる(アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎など)。 |
【チェック結果の評価】
- 3個以下: 現時点でのリスクは低いかもしれませんが、油断は禁物です。生活習慣に気をつけましょう。
- 4〜7個: SASの可能性があります。一度、専門医に相談することを検討してみましょう。特に「いびきの停止」や「日中の強い眠気」にチェックがついた場合は、受診をおすすめします。
- 8個以上: SASの可能性が非常に高いと考えられます。放置すると健康に深刻な影響を及ぼす恐れがあるため、できるだけ早く専門の医療機関を受診してください。
このセルフチェックでリスクを認識することが、健康への第一歩です。特に、ご家族がチェック項目に多く当てはまる場合は、本人の自覚がない可能性が高いため、この結果をもとに受診を優しく促してあげることが大切です。
家族が睡眠時無呼吸症候群かもしれない時にできること
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の最も難しい点の一つは、症状の大部分が本人の無意識下(睡眠中)で起こるため、自覚症状が乏しいことです。「いびきは昔から」「日中の眠気は仕事の疲れのせい」などと、本人は病気だと思っていないケースが非常に多くあります。だからこそ、一緒に生活するご家族の気づきとサポートが、治療への第一歩として何よりも重要になります。ここでは、家族がSASかもしれないと気づいた時に、具体的にできること、すべきことを2つのステップで解説します。
睡眠中の様子をよく観察・記録する
本人に受診をすすめる際、「いびきがうるさいよ」と感情的に伝えるだけでは、なかなか聞き入れてもらえないかもしれません。「またか」「疲れているだけだ」と反発されてしまうこともあります。そこで重要になるのが、客観的な事実に基づいた説得です。そのためには、まず睡眠中の様子を冷静に観察し、記録することが非常に有効です。
具体的に観察・記録すべきポイントは以下の通りです。
- いびきの音量とパターン:
- スマートフォンの録音アプリを使って、一晩のいびきを録音してみましょう。「百聞は一見に如かず」で、実際に自分のいびきを聞かせることは、本人に問題を自覚させる上で非常に効果的です。
- ただ録音するだけでなく、「ガーッ、ガーッ…(静かになる)…ゴガッ!」という特徴的なパターンがあるかどうかを確認します。
- 無呼吸の頻度と時間:
- いびきが止まり、呼吸が停止しているように見える時間を、スマートフォンのストップウォッチ機能などで計測します。10秒以上の停止が1時間に何回くらいあるかを数えてみましょう。「昨夜、1時間に15回も10秒以上呼吸が止まっていたよ」という具体的な数字は、本人に事の重大さを伝える強力な材料になります。
- 呼吸再開時の様子:
- 無呼吸の後、呼吸が再開するときの様子も重要です。大きなあえぎ声を出したり、しゃくりあげるような呼吸をしたり、苦しそうに体を動かしたりしていないか観察します。
- その他の様子:
- 苦しそうに何度も寝返りをうつ、胸や鎖骨のあたりが呼吸のたびにへこむ(陥没呼吸)、大量の寝汗をかいている、といった様子もメモしておきましょう。
これらの観察記録(録音データ、無呼吸の回数・時間のメモなど)は、本人に病気の深刻さを理解してもらうための客観的な証拠となるだけでなく、後日、医療機関を受診した際に、医師に症状を正確に伝えるための非常に貴重な情報となります。医師はこれらの情報をもとに、より的確な診断を進めることができます。手間はかかりますが、このステップが本人を治療へと導くための最も重要なプロセスです。
専門の医療機関への受診をすすめる
客観的な記録が準備できたら、次はいよいよ本人に受診をすすめるステップです。しかし、伝え方には細心の注意が必要です。相手を追い詰めたり、非難したりするような言い方は避け、あくまで心配しているという気持ちが伝わるように、優しく、しかし真剣に話すことが大切です。
受診をすすめる際のポイントは以下の通りです。
- タイミングを選ぶ:
- 相手が疲れている時や機嫌が悪い時は避け、リラックスして話ができる時間を選びましょう。
- 非難ではなく、心配を伝える:
- 「あなたのいびきで眠れない!」という非難の口調ではなく、「昨夜、呼吸が何度も止まっていて、本当に心配になった」「あなたの体のことが大切だから、一度調べてもらわない?」といった、相手を思いやる言葉で切り出しましょう。
- 客観的な事実を見せる:
- ここで、準備しておいた観察記録が役立ちます。録音したいびきを聞かせたり、無呼吸の回数や時間を記録したメモを見せたりしながら、「こんな状態なんだよ」と冷静に事実を伝えます。
- 放置するリスクを具体的に説明する:
- ただ「体に悪い」と言うだけでなく、SASを放置した場合に起こりうる具体的な健康リスク(高血圧、心筋梗塞、脳卒中、糖尿病など)や、日中の眠気による交通事故のリスクなどを、落ち着いて説明します。これは脅しではなく、正しい情報を提供して、危機感を持ってもらうためです。
- 「一緒に病院へ行こう」と提案する:
- 本人が一人で病院へ行くことに抵抗を感じる場合もあります。「私も心配だから一緒に行くよ」「予約も手伝うよ」と寄り添う姿勢を見せることで、受診への心理的なハードルを大きく下げることができます。
家族の協力なしにSASの治療を始めることは非常に困難です。あなたの愛情のこもった粘り強い働きかけが、大切な家族の健康、そして命を守ることにつながります。 根気強く、しかし優しく、治療への道をサポートしてあげてください。
睡眠時無呼吸症候群の検査の流れ
「睡眠時無呼吸症候群かもしれない」と思い、医療機関を受診することを決意しても、「どんな検査をするのだろう?」「痛いことや苦しいことをされるのだろうか?」といった不安を感じる方は少なくありません。しかし、SASの検査は体に大きな負担をかけるものではなく、確立された手順に沿って行われます。ここでは、一般的な検査の流れを3つのステップに分けて具体的に解説します。流れを事前に知っておくことで、安心して検査に臨むことができます。
問診
まず最初に行われるのが、医師による詳しい問診です。これは、患者さんの症状や生活背景を正確に把握し、SASの可能性や重症度を推測するための非常に重要なステップです。問診では、主に以下のようなことを聞かれます。
- 自覚症状について:
- 日中の眠気の程度(「エプワース眠気尺度」などの質問票を用いることもあります)
- 起床時の頭痛や口の渇きの有無
- 熟睡感のなさ、中途覚醒の頻度
- 睡眠中の様子(家族からの情報):
- いびきの有無、音量、パターン(止まることがあるか)
- 無呼吸の有無、頻度、時間(家族が記録したメモがあれば非常に役立ちます)
- 身体的な情報:
- 身長、体重(BMIを算出します)、首周りの長さの測定
- 喉の診察(扁桃の大きさ、軟口蓋の形などを視診します)
- 鼻の診察(鼻詰まりの原因となるアレルギー性鼻炎や鼻中隔弯曲症の有無を確認します)
- 生活習慣や既往歴について:
- 飲酒・喫煙の習慣
- 服用中の薬(特に睡眠薬や精神安定剤)
- 高血圧、糖尿病、心臓病などの持病の有無
この問診と身体診察の結果から、医師はSASの疑いが強いかどうかを判断し、次のステップである具体的な検査に進むかどうかを決定します。家族からの客観的な情報が診断の大きな手助けとなるため、可能であればパートナーや家族に同伴してもらうと良いでしょう。
自宅でできる簡易検査
問診でSASが強く疑われた場合、まず行われるのが自宅でできる簡易検査です。これは、専門の検査機器を医療機関から借りて帰り、普段通りに自宅で寝ながら行うスクリーニング検査です。入院の必要がなく、手軽に行えるため、多くの患者さんが最初に受ける検査となります。
使用する機器は、腕時計のような本体に、指先に装着するセンサーと鼻の下に当てる呼吸センサーがついたものが一般的です。これらのセンサーで、睡眠中に以下の項目を測定します。
- 血中酸素飽和度(SpO2): 血液中の酸素の量を測定します。無呼吸になると酸素濃度が低下するため、その変動パターンを記録します。
- 脈拍: 無呼吸による低酸素状態に反応して脈拍がどう変化するかを見ます。
- 呼吸の気流: 鼻からの空気の流れを検知し、呼吸が止まっている(無呼吸)か、弱くなっている(低呼吸)かを判断します。
一晩装着して眠り、後日、機器を医療機関に返却すると、記録されたデータが解析されます。この検査で最も重要な指標が「AHI(Apnea Hypopnea Index:無呼吸低呼吸指数)」です。これは、睡眠1時間あたりの「無呼吸」と「低呼吸」の合計回数を示す数値で、SASの重症度を判定する世界共通の基準です。
| AHI(1時間あたりの回数) | 重症度 |
|---|---|
| 5回未満 | 正常 |
| 5回以上 15回未満 | 軽症 |
| 15回以上 30回未満 | 中等症 |
| 30回以上 | 重症 |
簡易検査の結果、AHIが40回以上で、かつ日中の眠気などの典型的な症状がある場合は、この検査だけでSASと診断され、CPAP療法などの保険診療を開始できることがあります。
入院して行う精密検査(PSG検査)
簡易検査の結果、AHIが5回以上40回未満であった場合や、SAS以外の睡眠障害(周期性四肢運動障害など)が疑われる場合など、より詳細な診断が必要な際には、入院して行う精密検査「終夜睡眠ポリグラフィ検査(PSG:Polysomnography)」が行われます。このPSG検査は、SASの診断におけるゴールドスタンダード(最も信頼性の高い標準的な検査法)と位置づけられています。
通常、1泊2日で検査専門の施設や病院に入院して行います。体中に多くのセンサーを装着して眠るため、少し窮屈に感じるかもしれませんが、痛みはありません。
PSG検査では、簡易検査の項目に加えて、以下のような非常に多くの生体情報を同時に記録します。
- 脳波: 睡眠の深さや段階(レム睡眠、ノンレム睡眠)を正確に判定します。
- 心電図: 睡眠中の不整脈の有無などを詳しく調べます。
- 筋電図: 顎や足の筋肉の動きを記録し、睡眠の質や他の睡眠関連疾患の有無を評価します。
- 眼球運動: レム睡眠の状態を把握します。
- いびきの音、睡眠時の体位 など
これらの膨大な情報から、睡眠の質がどれだけ低下しているか、無呼吸がどの睡眠段階で、どの体位で起こりやすいかなどを極めて詳細に分析することができます。これにより、最も正確なAHIが算出され、確定診断と治療方針の決定が行われます。SASの診断プロセスは、このように段階的に、かつ科学的根拠に基づいて行われます。不安に思わず、専門医の指示に従って検査を受けることが、適切な治療への第一歩となります。
睡眠時無呼吸症候群の代表的な治療法
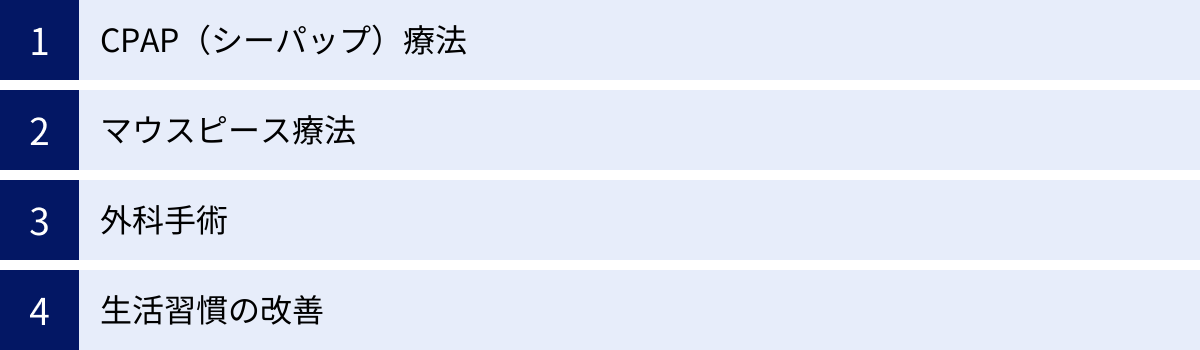
睡眠時無呼吸症候群(SAS)と診断された場合、その重症度や原因、患者さん自身のライフスタイルに合わせて、さまざまな治療法が選択されます。治療の目的は、単にいびきをなくすことだけではありません。睡眠中の無呼吸をなくし、睡眠の質を改善することで、日中の眠気や倦怠感を解消し、将来起こりうる高血圧や心疾患、脳卒中といった深刻な合併症を予防することにあります。ここでは、SASの代表的な4つの治療法について、それぞれの特徴やメリット・デメリットを詳しく解説します。
CPAP(シーパップ)療法
CPAP(Continuous Positive Airway Pressure:持続陽圧呼吸療法)療法は、中等症から重症の閉塞性睡眠時無呼吸症候群に対して、現在世界で最も広く行われている標準的な治療法です。
【仕組み】
CPAPは、鼻や口に装着したマスクを介して、持続的に圧力をかけた空気を気道に送り込む装置です。この空気の圧力が、睡眠中に緩んだ喉の筋肉によって気道が塞がってしまうのを、内側から風船を膨らませるように支え、常に開いた状態に保ちます。これにより、睡眠中の無呼吸やいびきを防ぎ、安定した呼吸を維持することができます。
【メリット】
- 効果が非常に高い: 適切に使用すれば、ほとんどの患者さんで無呼吸やいびきが劇的に改善します。治療を始めたその日から効果を実感できることも少なくありません。
- 合併症リスクの低減: 睡眠中の無呼吸と低酸素状態を解消することで、高血圧や心疾患、脳卒中などのリスクを大幅に下げることが多くの研究で証明されています。
- 日中のQOL(生活の質)向上: 睡眠の質が改善されることで、日中の眠気や倦怠感がなくなり、集中力や活力が回復します。
【デメリット・注意点】
- 対症療法である: CPAPはSASを根本的に治す治療法ではなく、装置を使用している間だけ効果を発揮する対症療法です。そのため、基本的には毎晩、継続して使用する必要があります。
- 装着感への慣れ: マスクの装着感や、空気が送り込まれる感覚に慣れるまで、少し時間がかかる場合があります。
- 定期的なメンテナンスと通院: 装置のメンテナンスや、月1回程度の定期的な通院が必要です。
- 保険適用: 日本では、AHI(無呼吸低呼吸指数)が20回/時以上の場合に保険適用となります。保険適用の場合、毎月の自己負担額は3割負担で約4,500円〜5,000円程度です。
マウスピース療法
マウスピース(口腔内装置、スリープスプリント)療法は、主に軽症から中等症のSAS患者さん、またはCPAP療法が体に合わない、あるいは続けられない患者さんに適応される治療法です。
【仕組み】
患者さん一人ひとりの歯形に合わせて作製したマウスピースを、睡眠中に装着します。この装置は、下顎を数ミリ前方に突き出させた状態で固定する構造になっています。下顎が前方に移動することで、それに連動して舌の付け根(舌根)も前方に引き出され、喉の奥の気道が広がり、呼吸がしやすくなります。
【メリット】
- 手軽で持ち運びに便利: CPAPのような大掛かりな装置が不要で、旅行や出張時にも手軽に持ち運べます。
- 電源が不要: どこでも使用できます。
- 比較的安価: CPAPのように毎月の費用はかからず、作製時の費用のみです。保険適用(紹介状が必要)の場合、自己負担額は3割負担で5万円〜6万円程度が目安です。
【デメリット・注意点】
- 適応が限られる: 重症のSASや、肥満度が高い患者さんには効果が出にくい場合があります。
- 専門の歯科医が必要: 作製にはSASの治療に精通した歯科医師による精密な調整が必要です。
- 副作用の可能性: 顎関節症の悪化、歯や歯茎の痛み、噛み合わせの変化などが起こる可能性があります。
- 残っている歯が少ないと作れない: 装置を固定するための健康な歯が一定数以上必要です。
外科手術
外科手術は、SASの原因がアデノイド・扁桃肥大や鼻の構造的な問題など、解剖学的に明確な場合に検討される根治的な治療法です。
【主な手術の種類】
- 口蓋垂軟口蓋咽頭形成術(UPPP): 最も代表的な手術の一つ。肥大した軟口蓋や口蓋垂、扁桃などを切除して、喉の奥の気道を物理的に広げます。
- アデノイド・扁桃摘出術: 子供のSASの第一選択となる手術です。アデノイドや扁桃が肥大している大人にも有効です。
- 鼻中隔矯正術・下鼻甲介切除術: 鼻中隔弯曲症やアレルギー性鼻炎による鼻詰まりが主原因の場合に行われます。
- 顎顔面手術: 顎が極端に小さい、後退しているなど、骨格に重度の問題がある場合に、顎の骨を切って前方に移動させる大掛かりな手術です。
【メリット】】
- 根治の可能性がある: 原因を物理的に取り除くため、成功すればSASが治癒し、CPAPやマウスピースから解放される可能性があります。
【デメリット・注意点】】
- 侵襲性(体への負担)とリスク: 手術には痛みや出血、感染症などのリスクが伴います。UPPPでは術後の嚥下障害(飲み込みにくさ)などが起こることもあります。
- 効果が不確実な場合も: 手術をしても、期待したほどの効果が得られないことや、数年後に再発することもあります。
- 適応が限られる: 手術が有効なのは、原因が明確な一部の患者さんに限られます。
生活習慣の改善
生活習慣の改善は、特定の治療法というよりも、すべてのSAS患者さんにとって不可欠な、治療の基本となるものです。 特に軽症の患者さんでは、これだけで症状が大幅に改善することもあります。CPAPやマウスピースを使用している人も、生活習慣の改善を並行して行うことで、治療効果を高めることができます。
【具体的な改善策】
- 減量: 肥満が原因の場合、最も効果的な治療法です。体重を5〜10%減らすだけで、AHIが大幅に改善することが知られています。食事療法と運動療法を組み合わせ、継続的に取り組むことが重要です。
- アルコール・睡眠薬の制限: 就寝前の飲酒や、筋弛緩作用のある睡眠薬は、気道の閉塞を悪化させるため、控えるか、医師に相談の上で変更する必要があります。
- 禁煙: 喫煙は喉の炎症を引き起こし気道を狭くするため、禁煙が強く推奨されます。
- 睡眠時の体位の工夫(側臥位睡眠): 仰向けで寝ると、重力で舌が喉の奥に落ち込みやすくなります。横向き(側臥位)で寝るだけで、いびきや無呼吸が軽減されることがあります。抱き枕を利用したり、パジャマの背中にテニスボールを縫い付けたりして、自然と横向きを維持する工夫も有効です。
- 鼻炎の治療: アレルギー性鼻炎などによる鼻詰まりがある場合は、点鼻薬や内服薬でしっかりと治療し、鼻の通りを良くすることが大切です。
これらの治療法は、一つだけを選ぶというより、患者さんの状態に合わせて複合的に行われることもあります。どの治療法が自分に最適か、専門医とよく相談して決定することが、治療成功への鍵となります。
睡眠時無呼吸症候群に関するよくある質問
睡眠時無呼吸症候群(SAS)について、多くの人が抱く疑問や不安があります。ここでは、特に多く寄せられる3つの質問について、分かりやすくお答えします。
何科を受診すればよいですか?
「いびきや無呼吸で病院に行きたいけれど、何科に行けばいいのかわからない」という声は非常に多く聞かれます。SASの診療は複数の科にまたがっており、主に以下の診療科が窓口となります。
- 呼吸器内科: 肺や気管支など、呼吸器全般を専門とする科です。SASは呼吸の病気であるため、多くの呼吸器内科で診断からCPAP療法の導入・管理まで行っています。高血圧や心臓病など、内科的な合併症を持っている方にも適しています。
- 耳鼻咽喉科: 鼻、喉、耳の専門家です。SASの原因となるアデノイド・扁桃肥大、アレルギー性鼻炎、鼻中隔弯曲症といった、鼻や喉の構造的な問題を詳しく診察できます。マウスピース療法の相談や、外科手術を検討する場合にも中心となる科です。
- いびき外来・睡眠外来(睡眠センター): 睡眠障害全般を専門的に扱う外来です。SASだけでなく、むずむず脚症候群やナルコレプシーなど、他の睡眠障害との鑑別が必要な場合や、より専門的な検査・治療を受けたい場合に適しています。大学病院や専門クリニックに設置されていることが多いです。
- 精神科・心療内科: SASによる日中の眠気や倦怠感が、うつ病や他の精神疾患と関連している場合もあります。精神科・心療内科で睡眠の問題を扱っているクリニックもあります。
- 循環器内科: SASが原因で高血圧や不整脈などの心臓・血管系の病気を発症している場合、循環器内科が診療の窓口となることもあります。
【初めて受診する場合のおすすめ】
もしどこに行けばよいか迷う場合は、まず「呼吸器内科」または「耳鼻咽喉科」を受診するのが一般的です。あるいは、かかりつけの内科医に相談し、専門の医療機関を紹介してもらうという方法も良いでしょう。病院のウェブサイトで「いびき」「睡眠時無呼吸症候群」の診療を行っているかを確認してから予約すると確実です。
治療にかかる費用はどのくらいですか?
SASの治療費用は、検査内容や治療法によって異なります。ここでは、健康保険が適用される場合(3割負担)の一般的な目安をご紹介します。
| 項目 | 内容 | 費用の目安(3割負担) |
|---|---|---|
| 初診・問診 | 医師による診察、相談 | 2,000円~3,000円程度 |
| 簡易検査 | 自宅で行うスクリーニング検査 | 3,000円~4,000円程度 |
| 精密検査(PSG) | 1泊入院して行う詳細な検査 | 20,000円~50,000円程度(入院基本料などにより変動) |
| CPAP療法 | 装置のレンタル料と月1回の診察料 | 月額 4,500円~5,000円程度 |
| マウスピース療法 | 装置の作製費用(診察・検査料は別途) | 50,000円~60,000円程度 |
| 外科手術 | 手術の種類や入院日数により大きく変動 | 100,000円~300,000円程度(高額療養費制度の対象となる場合が多い) |
CPAP療法は継続的な治療となるため、毎月一定の費用がかかります。 一方、マウスピースや外科手術は初期費用がかかりますが、月々のランニングコストは発生しません。
なお、入院や手術で医療費が高額になった場合は、所得に応じて自己負担額の上限が定められている「高額療養費制度」を利用できます。事前に加入している健康保険組合に申請しておくことで、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることも可能です。費用について不安な点があれば、事前に医療機関の窓口で相談してみましょう。
女性や痩せている人でも発症しますか?
はい、発症します。 「SAS=太った中年男性の病気」というイメージが根強いですが、これは大きな誤解です。女性や痩せている人でも、SASになるリスクは十分にあります。
【女性の場合】
女性は、女性ホルモン(特にプロゲステロン)に上気道開大筋の活動を活発にする働きがあるため、閉経前は男性に比べてSASになりにくいとされています。しかし、閉経を迎えて女性ホルモンが減少すると、その保護作用が失われ、SASの発症リスクが急激に高まります。 閉経後の女性の発症率は、男性とほぼ同等になるとも言われています。
また、女性のSASは、男性のような激しいいびきや典型的な無呼吸が目立たず、不眠、日中の疲労感、気分の落ち込み、頭痛といった、更年期障害やうつ病と間違われやすい症状で現れることも多く、見逃されやすい傾向があるため注意が必要です。
【痩せている人の場合】
痩せている人や、肥満ではない人がSASを発症する場合、その主な原因は「骨格的な要因」にあります。
- 顎が小さい、下顎が後退している
- 首が細く長い
- 扁桃腺が大きい
- 鼻中隔が曲がっている
上記のような特徴があると、気道が元々狭いため、わずかな体重増加や加齢による筋力低下でもSASを発症しやすくなります。特に日本人を含むアジア人は、欧米人に比べて骨格的に気道が狭い傾向があるため、痩せ型でもSASを発症する人の割合が高いことが知られています。
「自分は太っていないから大丈夫」「女性だから関係ない」という思い込みは禁物です。体型や性別に関わらず、いびきや日中の眠気などの気になる症状があれば、一度専門医に相談することをおすすめします。