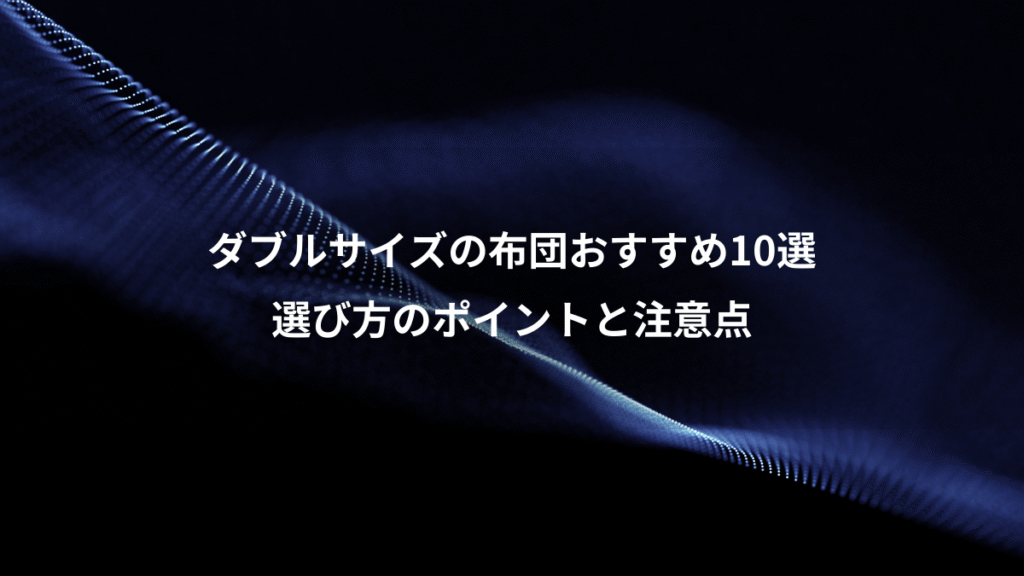「二人で寝るからダブルサイズ」「一人でも広々と眠りたい」など、様々な理由でダブルサイズの布団は選ばれています。しかし、一口にダブルサイズの布団といっても、中綿の素材や機能性、季節に合わせた種類など、その選択肢は多岐にわたります。自分に合わない布団を選んでしまうと、「思ったより暖かくない」「重くて寝苦しい」「手入れが大変」といった後悔につながりかねません。
快適な睡眠は、日中のパフォーマンスを左右する重要な要素です。そのためには、ご自身のライフスタイルや睡眠環境に最適な布団を選ぶことが不可欠です。
この記事では、ダブルサイズの布団の基本的な知識から、後悔しないための選び方のポイント、具体的な人気商品、そして購入前に知っておきたい注意点まで、網羅的に解説します。素材ごとの特徴や季節に合わせた布団の種類、清潔に保つための機能性など、あらゆる角度からあなたにぴったりの一枚を見つけるお手伝いをします。
この記事を最後まで読めば、数多くの選択肢の中から、ご自身にとって最高の寝心地を提供するダブルサイズの布団を見つけ出すことができるでしょう。
目次
ダブルサイズの布団とは?
ダブルサイズの布団を選ぶにあたり、まずはその基本的なサイズ感や、どのような使い方に適しているのかを正しく理解することが重要です。ここでは、ダブルサイズの布団の定義と、一般的な使用人数について詳しく解説します。この基本情報を押さえることで、ご自身の生活スタイルに本当に合っているのかを判断する最初のステップとなります。
ダブルサイズの基本的な大きさ
日本の家庭用品品質表示法に基づくJIS(日本産業規格)では、ダブルサイズの掛け布団の標準寸法は「幅190cm × 長さ210cm」と定められています。このサイズは、寝室のスペースや使用者の体格を考慮して設計されており、多くの寝具メーカーがこの基準に沿って商品を製造しています。
ただし、注意点として、すべてのメーカーがこのJIS規格に厳密に従っているわけではありません。特に海外ブランドや一部の国内メーカーでは、独自のサイズ基準を設けている場合があります。例えば、幅が180cmや200cmといった商品も市場には存在します。そのため、布団を購入する際は、必ず商品に記載されている具体的な寸法を確認することが非常に重要です。特に、すでに持っている掛け布団カバーを使用したい場合や、ベッドのサイズとのバランスを考える際には、数センチの違いが使い心地に大きく影響することがあります。
他のサイズの布団と大きさを比較すると、その特徴がより明確になります。
| 布団の種類 | 標準的なサイズ(幅 × 長さ) | 主な用途 |
|---|---|---|
| シングル | 150cm × 210cm | 大人1人用 |
| セミダブル | 170cm × 210cm | 大人1人がゆったり使う用 |
| ダブル | 190cm × 210cm | 大人2人用、または1人が贅沢に使う用 |
| クイーン | 210cm × 210cm | 大人2人がゆったり使う用 |
| キング | 230cm × 210cm | 大人2人と子供1人など、さらにゆとりを求める用 |
表を見てわかる通り、ダブルサイズはシングルサイズよりも幅が40cm広くなっています。この40cmの差が、一人で使う際のゆとりや、二人で使う際のフィット感につながります。一方で、クイーンサイズと比較すると20cm狭いため、二人で使う場合には体格や寝相によっては少し窮屈に感じる可能性も秘めています。
この「幅190cm」というサイズは、二人分の肩幅や寝返りに必要なスペースを考慮した寸法ですが、あくまで標準的な体格を基準としています。ご自身の体格や、パートナーと一緒に使う場合はお互いの体格を考慮して、このサイズが適切かどうかを判断する必要があります。
ダブルサイズは何人で使うのが一般的?
ダブルサイズの布団は、その名の通り「ダブル=2人」で使うことを想定して作られていますが、実際には様々な使われ方があります。ここでは、主な使用パターンである「一人で使う場合」と「二人で使う場合」のそれぞれのメリット・デメリットを詳しく見ていきましょう。
一人でゆったり使う場合
意外に思われるかもしれませんが、ダブルサイズの布団を一人で贅沢に使うという選択は、睡眠の質を向上させる上で非常に有効です。
メリット:
- 圧倒的な解放感と寝返りの自由: シングルサイズでは、寝返りを打った際に布団の端から腕や足がはみ出してしまい、寒さで目が覚めることがあります。ダブルサイズであれば、どんなに寝返りを打っても体が布団にすっぽりと包まれるため、朝まで暖かく快適に眠れます。
- 優れたフィット感と保温性: 布団が体を完全に覆うことで、体と布団の間に隙間ができにくくなります。これにより、外からの冷気が入り込むのを防ぎ、布団内部の暖かい空気を逃がしにくいため、保温性が高まります。
- 精神的な安心感: 大きな布団に包まれる感覚は、精神的な安心感やリラックス効果をもたらすと言われています。ベッドの上で読書をしたり、タブレットを見たりする際にも、ゆったりとしたスペースを確保できます。
デメリット:
- スペースの確保: 当然ながら、シングルサイズの布団よりも大きな収納スペースや干す場所が必要になります。部屋の広さや収納スペースに余裕がない場合は、管理が負担になる可能性があります。
- 手入れの手間とコスト: 布団自体が大きく重くなるため、天日干しや洗濯、布団カバーの着脱といった作業が大変になります。また、クリーニングに出す際の料金も高くなる傾向があります。
- 価格: シングルサイズに比べて布団本体やカバーの価格が高くなります。
特に、寝相があまり良くない方や、眠りが浅く少しの寒さでも目が覚めてしまう方にとっては、一人でダブルサイズを使うメリットは非常に大きいと言えるでしょう。
二人で使う場合
ダブルサイズの布団は、一般的にカップルや夫婦など、大人二人での使用を想定されています。
メリット:
- 省スペース: シングル布団を2枚並べるよりも、省スペースで済みます。ベッドフレームもダブルサイズ一つで良いため、寝室のレイアウトの自由度が高まります。
- 一体感と経済性: 一枚の布団を共有することで、パートナーとの一体感が得られます。また、布団やカバーを1セット購入するだけで済むため、シングル2組を用意するよりも初期費用を抑えられる場合があります。
デメリット:
- 寝返りの影響を受けやすい: 二人で使用する際の最大のデメリットは、相手の動きがダイレクトに伝わってしまうことです。一方が寝返りを打つと、布団が引っ張られてもう一方が寒さを感じたり、その振動で目が覚めてしまったりすることがあります。
- 体格によっては窮屈: 標準的な体格の二人であれば問題ないかもしれませんが、大柄な方同士の場合、幅190cmでは寝返りを打つスペースが十分に確保できず、窮屈に感じることがあります。結果として、無意識に相手を気遣い、睡眠の質が低下する可能性があります。
- 布団の奪い合い: 就寝中に無意識のうちに布団を自分の方へ引き寄せてしまい、パートナーが寒い思いをする「布団の奪い合い」が起こりがちです。
- 好みの違い: 暑がりの人と寒がりの人、重い布団が好きな人と軽い布団が好きな人など、快適だと感じる寝具の好みが異なる場合、どちらかが我慢を強いられることになります。
これらの点を考慮すると、ダブルサイズの布団を二人で快適に使えるのは、比較的小柄なカップルや、お互いの密着感を重視するカップルに限られると言えるかもしれません。もし、睡眠の質を最優先するならば、後述する「シングル布団2枚使い」や、さらに大きい「クイーンサイズ」を検討することも重要です。
また、小さなお子様と添い寝するためにダブルサイズを選ぶケースもありますが、子供は成長が早く、すぐに手狭になります。長期的な視点で見ると、子供が自分の部屋で寝るようになった後の使い方も含めて検討することをおすすめします。
後悔しない!ダブルサイズの布団の選び方
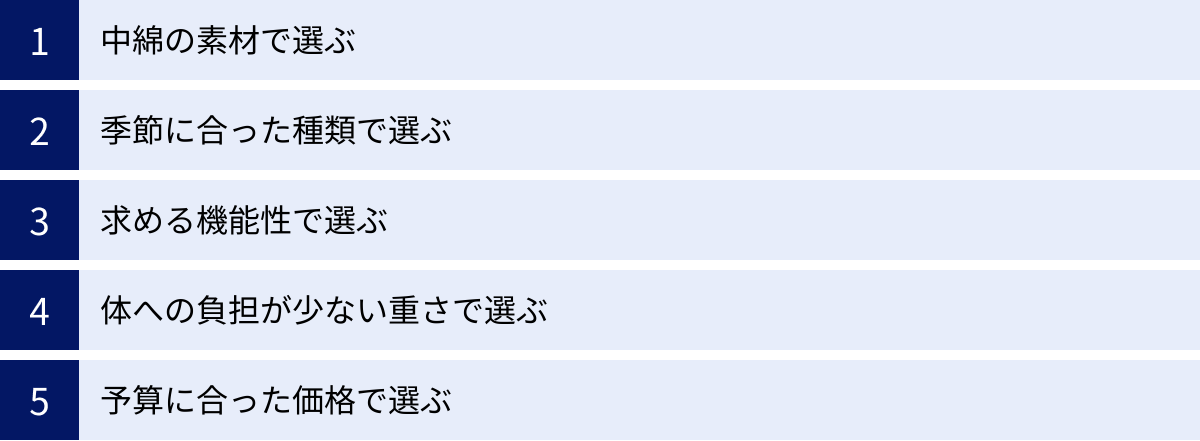
ダブルサイズの布団は決して安い買い物ではありません。だからこそ、購入後に「こんなはずではなかった」と後悔しないために、選び方のポイントをしっかりと押さえておくことが大切です。ここでは、「中綿の素材」「季節に合った種類」「機能性」「重さ」「価格」という5つの視点から、あなたに最適な一枚を見つけるための具体的な方法を詳しく解説します。
中綿の素材で選ぶ
布団の寝心地や性能を決定づける最も重要な要素が、中に詰められている「中綿(なかわた)」の素材です。素材ごとに保温性、吸湿性、重さ、価格、手入れのしやすさなどが大きく異なります。それぞれの特徴を理解し、ご自身の好みやライフスタイルに合ったものを選びましょう。
| 中綿の素材 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |
|---|---|---|---|
| 羽毛 | 非常に軽く、保温性・吸湿放湿性に優れる | 高価、特有の匂い、アレルギーのリスク | 軽くて暖かい布団が欲しい人、本格的な寝心地を求める人 |
| 羊毛 | 保温性・吸湿放湿性が高い、弾力性がある | 重い、特有の匂い、家庭での洗濯が難しい | 汗をかきやすい人、弾力のある寝心地が好きな人 |
| 真綿 | 肌に優しい、吸湿性・通気性が良い、ホコリが出にくい | 非常に高価、保温性は羽毛に劣る、手入れが繊細 | 肌が敏感な人、アレルギー体質の人、極上のフィット感を求める人 |
| 木綿 | 吸湿性が高い、保温性がある、比較的手頃 | 重い、放湿性が低く乾きにくい、へたりやすい | 昔ながらの寝心地が好きな人、日中の布団干しが苦にならない人 |
| 合成繊維 | 安価、軽い、家庭で洗濯可能、アレルギーが出にくい | 吸湿性が低く蒸れやすい、静電気が起きやすい | 手入れの手間を省きたい人、アレルギーが心配な人、コストを抑えたい人 |
羽毛|軽くて保温性が高い
羽毛布団は、その名の通り水鳥の羽毛を中綿として使用した布団です。高級布団の代名詞的存在であり、その軽さと暖かさから絶大な人気を誇ります。
- 特徴と構造: 羽毛布団の中綿は、主に「ダウン」と「フェザー」の2種類で構成されています。
- ダウン: 水鳥の胸元にある、軸のない綿毛状の羽毛。一つひとつが放射状に広がっており、たくさんの空気を含むことで高い保温性を発揮します。このダウンの割合(ダウン率)が高いほど、高品質で暖かく、軽い布団になります。
- フェザー: 中央に硬い軸がある、いわゆる「羽根」。通気性や弾力性を担いますが、保温性はダウンに劣ります。
- メリット: 最大のメリットは「軽さ」と「保温性」の両立です。空気の層をたっぷりと含むため、少量でも非常に暖かく、体にかけた時の圧迫感が少ないのが特徴です。また、睡眠中にかく汗を吸収し、日中に発散させる「吸湿放湿性」にも優れているため、布団の中が蒸れにくく快適な状態を保ちます。体にフィットする「ドレープ性」も高く、肩口などから冷気が入るのを防ぎます。
- デメリット: 高品質なものほど価格が高くなる点が一番のデメリットです。また、動物由来の素材であるため、洗浄が不十分な製品は特有の獣毛臭がすることがあります。羽毛自体にアレルギー反応を示す方もいるため、アレルギー体質の人は注意が必要です。家庭での洗濯が難しい製品も多く、基本的には専門のクリーニング業者に依頼することになります。
- 選び方のポイント: 「ダウン率」と「ダウンパワー」を確認しましょう。一般的に、ダウン率が85%以上のものが高品質とされています。ダウンパワー(dp)は、羽毛のかさ高を示す数値で、350dp以上が良質、400dp以上なら高品質な布団と言えます。
羊毛|吸湿・放湿性に優れている
羊毛(ウール)は、主に羊の毛を中綿として使用した布団です。天然の優れた機能性を持つ素材として、根強い人気があります。
- 特徴と構造: 羊毛の繊維は「クリンプ」と呼ばれる縮れた構造をしています。このクリンプが複雑に絡み合うことで、多くの空気を含み、高い保温性を生み出します。
- メリット: 特筆すべきは、吸湿放湿性の高さです。羊毛は自重の約30%もの水分を吸収できると言われており、睡眠中の汗を素早く吸い取ってくれます。さらに、吸収した水分を放出する力も高いため、布団の中がジメジメしにくく、一年を通して爽やかな寝心地を保ちます。適度な弾力性があり、体をしっかりと支えてくれるのも特徴です。また、羊毛は燃えにくい性質(難燃性)を持っているため、安全性も高い素材です。
- デメリット: 羽毛に比べると重さがあり、体にかけた時にずっしりとした感覚があります。動物由来のため、特有の匂いが気になる場合や、虫食いのリスクがあります。家庭での洗濯は縮みの原因になるため、基本的にはクリーニングに出す必要があります。
真綿|肌に優しく通気性が良い
真綿(まわた)とは、蚕の繭を引き伸ばして綿状にした、いわゆるシルク(絹)のことです。古くから最高級の寝具素材として知られています。
- メリット: 人間の肌に近いアミノ酸で構成されているため、肌への刺激が極めて少なく、非常に優しい肌触りが魅力です。吸湿性や放湿性も抜群で、常にサラッとした快適な状態を保ちます。繊維が長いため、ホコリや切れ端が出にくく、アレルギーや喘息が心配な方にもおすすめです。体に吸い付くようなしなやかなフィット感(ドレープ性)も真綿ならではの特徴です。
- デメリット: 最大のデメリットは価格が非常に高価であることです。また、保温性に関しては、同等のかさ高の羽毛布団には劣ります。非常にデリケートな素材であるため、水洗いはできず、手入れには細心の注意が必要です。
木綿|吸湿性は高いが乾きにくい
木綿(もめん・コットン)は、古くから日本の布団で使われてきた、最も伝統的な天然素材です。
- メリット: 吸湿性に非常に優れており、睡眠中の汗をしっかりと吸い取ってくれます。日向に干した時のふっくらとした暖かさは、木綿布団ならではの心地よさです。天然素材の中では比較的安価なのも魅力です。
- デメリット: 放湿性が低く、一度吸った湿気が抜けにくいという大きな欠点があります。そのため、こまめに天日干しをしないと、布団が湿って重くなり、カビやダニの原因にもなります。他の素材に比べて重量があり、長年使っていると中綿が偏って「へたり」やすい点もデメリットです。
合成繊維|安価で手入れが簡単
合成繊維とは、主にポリエステルなどを原料として作られた人工の繊維です。技術の進歩により、様々な機能を持つ製品が開発されています。
- メリット: 最大のメリットは、価格が安く、手入れが非常に簡単なことです。多くの製品が家庭の洗濯機で丸洗いでき、乾きも早いため、常に清潔な状態を保ちやすいです。天然素材ではないため、アレルギーの原因となる動物性のタンパク質や、繊維に付着する虫の心配がありません。ホコリが出にくい「低発塵性」の製品も多く、抗菌・防臭・防ダニといった機能的な加工がしやすいのも特徴です。
- デメリット: 天然繊維に比べて吸湿性が低いため、睡眠中に蒸れを感じやすいことがあります。特に汗をかきやすい人は、不快に感じるかもしれません。また、静電気が発生しやすく、ホコリを寄せ付けやすいという側面もあります。
季節に合った種類で選ぶ
布団は、季節に合わせて厚みや中綿の量が異なるいくつかの種類に分けられます。日本の四季に対応するためには、それぞれの特徴を理解して使い分けるか、オールシーズン対応の製品を選ぶのが賢明です。
| 布団の種類 | 対応季節 | 中綿の量(目安) | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 本掛け布団 | 冬 | 約1.6kg〜 | 最も厚手で保温性が高い、冬のメイン布団 |
| 合掛け布団 | 春・秋 | 約1.0kg〜 | 本掛けと肌掛けの中間、季節の変わり目に便利 |
| 肌掛け布団 | 夏 | 約0.4kg〜 | 最も薄手、夏場の冷房対策やタオルケット代わりに |
| 2枚合わせ布団 | オールシーズン | – | 合掛けと肌掛けのセット、組み合わせで3通りに使える |
本掛け布団(冬向け)
一般的に「冬用の掛け布団」と言われるのがこのタイプです。中綿が最も多く詰められており、抜群の保温性を誇ります。真冬の厳しい寒さでも、これ一枚で暖かく眠れるように設計されています。ダブルサイズの場合、羽毛布団なら中綿量が1.6kg以上のものが目安となります。
合掛け布団(春・秋向け)
本掛け布団と肌掛け布団の中間に位置するのが合掛け布団です。本掛け布団ほど厚くなく、肌掛け布団ほど薄くないため、春や秋といった季節の変わり目に重宝します。マンションなど気密性の高い住宅であれば、冬でも毛布と組み合わせることで十分対応できる場合もあり、使用期間が最も長い汎用性の高い布団と言えます。
肌掛け布団(夏向け)
「ダウンケット」や「キルトケット」とも呼ばれ、夏用に作られた薄手の掛け布団です。タオルケットだけでは少し肌寒い梅雨時や、冷房を効かせた部屋で寝る際の寝冷え防止に役立ちます。軽く、家庭で洗濯しやすい製品が多いのも特徴です。
2枚合わせ布団(オールシーズン対応)
合掛け布団と肌掛け布団がセットになっており、ホックやボタンで着脱できるタイプです。春と秋は合掛け布団一枚、夏は肌掛け布団一枚、そして冬は2枚を重ねて本掛け布団として使うことで、一年中快適な温度調整が可能です。収納スペースが限られている場合に特に便利ですが、2枚分の手入れが必要になる点や、重ねた際にずれないようにするためのホックの着脱が少々面倒に感じる場合もあります。
求める機能性で選ぶ
現代の布団には、快適な睡眠をサポートし、日々の手入れを楽にするための様々な機能が付加されています。ご自身の悩みやニーズに合わせて、必要な機能が備わっているかを確認しましょう。
快適な睡眠のための保温性・吸湿性
快適な睡眠環境の指標として「寝床内気候(しんしょうないきこう)」という言葉があります。これは、布団と体の間にできる空間の温度が33℃前後、湿度が50%前後に保たれている状態が最も快適であるとされるものです。この理想的な状態を維持するためには、布団の「保温性」と「吸湿性(吸湿放湿性)」が鍵となります。冬場は外の冷気を遮断し体温を逃がさない保温性が、夏場や汗をかきやすい人は、汗を吸って素早く発散させる吸湿性が重要になります。これらの性能は、前述した中綿の素材によって大きく左右されます。
清潔に保つための防ダニ・抗菌・防臭加工
人は寝ている間にコップ1杯分の汗をかくと言われており、布団は湿気や皮脂によってダニや雑菌が繁殖しやすい環境です。
- 防ダニ加工: ダニの侵入を防いだり、増殖を抑制したりする加工です。アレルギーの原因となるダニの死骸やフンを減らす効果が期待できます。高密度に織られた生地で物理的にダニの侵入を防ぐタイプと、薬剤でダニを寄せ付けないタイプがあります。
- 抗菌・防臭加工: 繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などが原因で発生する嫌な臭いを防ぐ加工です。「SEKマーク」は、繊維評価技術協議会が定めた基準をクリアした製品に付けられる認証マークで、品質の目安になります。
手入れのしやすさ(家庭で洗濯可能か)
布団を清潔に保つためには、定期的な洗濯が理想です。しかし、素材やサイズによっては家庭での洗濯が難しい場合があります。
購入前に必ず「洗濯表示」を確認し、「洗濯機マーク」や「手洗いマーク」が付いているかをチェックしましょう。ダブルサイズの布団を洗濯機で洗う場合、洗濯機の容量が10kg以上ないと、布団が傷んだり、洗濯機が故障したりする原因になります。容量が足りない場合や、デリケートな素材の場合は、コインランドリーの大型洗濯機を利用するか、専門のクリーニング業者に依頼することになります。
体への負担が少ない重さで選ぶ
布団の重さも、睡眠の質に影響を与える見過ごせない要素です。重すぎる布団は体に圧迫感を与え、寝返りを妨げることがあります。スムーズな寝返りは、体圧を分散させ、血行を促進するために不可欠です。
一方で、ある程度の重さがあった方が体にフィットし、安心感が得られるという人もいます。特に、軽すぎると寝返りのたびに布団がずれてしまい、肩口から冷気が入って寒さを感じることもあります。
素材別のおおよその重さの目安は以下の通りです。
- 羽毛布団: 約2.0kg 〜 3.5kg
- 羊毛布団: 約4.0kg 〜 5.5kg
- 合成繊維布団: 約2.5kg 〜 4.0kg
- 木綿布団: 約5.5kg 〜 7.0kg
これはあくまで布団全体の重さであり、実際の寝心地は中綿の種類や量、側生地の素材によっても変わります。ご自身が心地よいと感じる重さを選ぶことが大切です。
予算に合った価格で選ぶ
ダブルサイズの布団の価格は、数千円で購入できる安価なものから、数十万円する高級なものまで非常に幅広いです。価格は主に、中綿の素材の種類と質、量、そして側生地の品質、ブランドなどによって決まります。
| 中綿の素材 | 価格帯の目安(ダブルサイズ) |
|---|---|
| 羽毛 | 20,000円 〜 200,000円以上 |
| 羊毛 | 15,000円 〜 50,000円 |
| 真綿 | 100,000円 〜 500,000円以上 |
| 木綿 | 10,000円 〜 30,000円 |
| 合成繊維 | 5,000円 〜 20,000円 |
一般的に、価格と品質(快適性や耐久性)は比例する傾向にあります。安価な布団は、すぐにへたってしまったり、保温性が低かったりすることがあります。一方、高価な布団は初期投資は大きいですが、適切に手入れをすれば10年以上快適に使えるものも多く、長期的な視点で見ればコストパフォーマンスが高いと言えます。
ご自身の予算を明確にし、その範囲内で最も優先したい機能(暖かさ、軽さ、手入れのしやすさなど)を満たす布団を選ぶことが、賢い買い物のコツです。
【2024年】ダブルサイズの布団おすすめ人気10選
ここでは、これまでの選び方のポイントを踏まえ、2024年時点で人気のあるダブルサイズの布団を10点厳選して紹介します。それぞれの商品の特徴や価格、どんな人におすすめなのかを詳しく解説しますので、ぜひ布団選びの参考にしてください。
※商品の仕様や価格は変更される可能性があるため、最新の情報は各公式サイトでご確認ください。
① ニトリ Nウォーム
特徴:
ニトリの「Nウォーム」シリーズは、「吸湿発熱」素材を使用した大人気の掛け布団です。体から発散される水分を吸収し、それを熱に変換する特殊な化学繊維を採用しており、布団に入った瞬間から暖かさを感じやすいのが最大の特徴です。暖かさのレベルに応じて「Nウォーム」「Nウォームスーパー」「Nウォームダブルスーパー」の3段階が用意されており、お住まいの地域の気候や寒さの感じ方に合わせて選べます。多くのモデルで抗菌防臭や制菌加工が施されており、家庭の洗濯機で丸洗いできるため、清潔さを保ちやすいのも嬉しいポイントです。
- 中綿の素材: ポリエステル、レーヨンなど(モデルによる)
- 機能性: 吸湿発熱、蓄熱、抗菌防臭、制菌、洗濯可(モデルによる)
- 価格帯: 比較的手頃な価格帯から展開
- こんな人におすすめ:
- 布団に入った時のひんやり感が苦手な人
- 手頃な価格で暖かい布団が欲しい人
- 手入れの簡単な布団を求めている人
参照:株式会社ニトリ 公式通販ニトリネット
② 無印良品 羽毛掛ふとん
特徴:
無印良品の羽毛布団は、シンプルで洗練されたデザインと、品質へのこだわりが魅力です。羽毛の産地であるウクライナやポーランドの農場と直接契約し、のびのびと飼育された水鳥の羽毛のみを使用しています。採取された羽毛は、現地の工場で丁寧に洗浄・選別され、羽毛本来の保温性や復元力を最大限に引き出しています。側生地にはオーガニックコットンを使用し、肌触りも良好です。軽くて暖かい「一層式」と、より保温性の高い「二層式」があり、好みに合わせて選べます。
- 中綿の素材: グレーダックダウン、フェザー
- 機能性: 高い保温性、軽量、オーガニックコットン側生地
- 価格帯: 中価格帯
- こんな人におすすめ:
- 品質や素材の背景にこだわりたい人
- シンプルで飽きのこないデザインが好きな人
- 本格的な羽毛布団の寝心地を体験したい人
参照:無印良品 公式ネットストア
③ 西川 羽毛布団
特徴:
450年以上の歴史を持つ老舗寝具メーカー「西川」の羽毛布団は、その品質と信頼性で高い評価を得ています。長年の研究に基づいて開発された独自のキルティング(縫製)パターンは、羽毛の偏りを防ぎ、体へのフィット感を高めることで、暖かさを逃しません。厳しい品質基準をクリアした高品質なダウンのみを使用し、ダウンパワーの高い製品が揃っています。価格帯は幅広く、エントリーモデルから最高級品までラインナップが豊富なため、予算に合わせて本格的な寝心地を選べるのが強みです。
- 中綿の素材: ダウン、フェザー(産地やダウン率により多種多様)
- 機能性: 独自のキルティング技術、高いダウンパワー、豊富なラインナップ
- 価格帯: 中価格帯〜高価格帯
- こんな人におすすめ:
- 品質と信頼性を最も重視する人
- 長く使える、一生ものの布団を探している人
- 予算内で最高の羽毛布団を見つけたい人
参照:西川株式会社 公式サイト
④ GOKUMIN グランウォーム
特徴:
GOKUMINは、オンラインを中心に展開する寝具ブランドで、高機能ながらコストパフォーマンスに優れた製品で人気を集めています。「グランウォーム」は、中空構造のポリエステル綿に、炭(カーボン)を練り込んだ「炭綿」をブレンドした掛け布団です。この炭綿が遠赤外線効果で体を芯から温め、高い蓄熱・保温性を発揮します。抗菌・防臭機能も備えており、家庭での丸洗いも可能です。羽毛のような暖かさを目指しつつ、合成繊維の手軽さを両立させたハイブリッドな製品です。
- 中綿の素材: ポリエステル(炭配合中空綿など)
- 機能性: 蓄熱保温、遠赤外線効果、抗菌防臭、洗濯可
- 価格帯: 手頃な価格帯
- こんな人におすすめ:
- コストを抑えつつ、高い保温性を求める人
- 羽毛アレルギーが心配だが、暖かい布団が欲しい人
- 機能性と手入れのしやすさを両立させたい人
参照:GOKUMIN[極眠] 公式サイト
⑤ アイリスオーヤマ ほこりの出にくい掛け布団
特徴:
アイリスオーヤマの掛け布団は、手頃な価格と実用的な機能で人気です。特に「ほこりの出にくい掛け布団」は、中綿に切れにくい中空ポリエステル綿を使用することで、アレルギーの原因となりうるハウスダストの発生を抑制します。側生地には、桃の表面のようなしっとりとした肌触りの「ピーチスキン加工」が施されており、カバーなしでも心地よく使えます。軽量で、家庭の洗濯機で気軽に洗えるため、子供用や来客用としても非常に便利です。
- 中綿の素材: ポリエステル(中空構造綿)
- 機能性: 低発塵性、ピーチスキン加工、軽量、洗濯可
- 価格帯: 非常に手頃な価格帯
- こんな人におすすめ:
- とにかく価格を抑えたい人
- アレルギーや喘息が心配な人
- 頻繁に洗濯して清潔に使いたい人
参照:アイリスオーヤマ公式通販サイト アイリスプラザ
⑥ タンスのゲン 羽毛布団
特徴:
タンスのゲンは、インターネット通販を中心に、高品質な家具や寝具をリーズナブルな価格で提供しています。羽毛布団に関しても、世界有数の羽毛の産地であるポーランドやハンガリー産の高品質なダウンを使用した製品を数多くラインナップしています。羽毛の品質を保証する「CILギャランティーラベル」付きの製品が多く、客観的な品質評価に基づいて選べるのが特徴です。自社工場で充填から製造まで行うことで、中間コストを削減し、高品質な羽毛布団を驚きの価格で実現しています。
- 中綿の素材: ホワイトダックダウン、グースダウンなど(産地、品質別に多数)
- 機能性: CILギャランティーラベルによる品質保証、高いコストパフォーマンス
- 価格帯: 手頃な価格帯〜中価格帯
- こんな人におすすめ:
- 品質の良い羽毛布団をできるだけ安く手に入れたい人
- 産地やダウンパワーなど、スペックを比較して選びたい人
- ネットでの口コミや評判を重視する人
参照:タンスのゲン本店
⑦ エムール エムールカラー
特徴:
エムールは、機能性とデザイン性を両立させた寝具を企画・販売する日本のブランドです。「エムールカラー」シリーズは、豊富なカラーバリエーションが魅力の日本製掛け布団です。中綿には、帝人フロンティアが開発した高機能ポリエステル綿「マイティトップ®II ECO」を使用。この素材は、防ダニ・抗菌防臭効果に優れており、効果の持続性も高いとされています。国内の工場で一つひとつ丁寧に作られており、品質の高さも安心です。
- 中綿の素材: ポリエステル(帝人マイティトップ®II ECO)
- 機能性: 日本製、防ダニ、抗菌防臭、豊富なカラーバリエーション
- 価格帯: 手頃な価格帯
- こんな人におすすめ:
- 品質の高い日本製の布団が欲しい人
- ダニや菌、臭いが気になる人
- 寝室のインテリアに合わせて布団の色を選びたい人
参照:エムール -EMOOR- 布団・家具 公式通販サイト
⑧ 昭和西川 ホテルモード 掛け布団
特徴:
西川グループの一員である昭和西川が手掛ける「ホテルモード」シリーズは、その名の通り、ホテルのような上質な寝心地を家庭で再現することをコンセプトにしています。側生地には、柔らかく、なめらかな肌触りのピーチスキン加工を採用。中綿には、ふっくらとしたボリューム感と弾力性を持つポリエステル綿を使用し、体を優しく包み込みます。詰め物に工夫を凝らすことで、ホコリが出にくく、洗濯機での丸洗いも可能です。手頃な価格で、ワンランク上のリッチな寝心地を体感できます。
- 中綿の素材: ポリエステル
- 機能性: ホテルのような寝心地、ピーチスキン加工、ボリューム感、洗濯可
- 価格帯: 手頃な価格帯
- こんな人におすすめ:
- ふかふかでボリュームのある布団が好きな人
- 肌触りの良さを重視する人
- 手頃な価格で高級感を味わいたい人
参照:昭和西川公式通販サイト 西川ストアONLINE
⑨ ナイスデイ mofua (モフア)
特徴:
ナイスデイの「mofua(モフア)」は、とろけるような肌触りの「プレミアムマイクロファイバー」を使用した寝具シリーズで、特に秋冬シーズンに絶大な人気を誇ります。髪の毛の1/100以下の極細繊維が、体温を逃さず、暖かい空気の層を作ります。掛け布団だけでなく、毛布や敷きパッドなどラインナップが豊富で、シリーズで揃えることで統一感のあるコーディネートが可能です。静電気防止加工が施されている点も、乾燥する季節には嬉しいポイントです。
- 中綿の素材: ポリエステル
- 側生地の素材: ポリエステル(プレミアムマイクロファイバー)
- 機能性: 抜群の肌触り、高い保温性、静電気防止加工、豊富なカラー
- 価格帯: 手頃な価格帯
- こんな人におすすめ:
- 何よりも肌触りを最優先したい人
- 毛布と一体化したような暖かい布団が欲しい人
- デザインやカラーコーディネートを楽しみたい人
参照:株式会社ナイスデイ 公式サイト
⑩ LOWYA(ロウヤ) 洗える掛け布団
特徴:
LOWYA(ロウヤ)は、トレンド感のあるデザイン性の高い家具やインテリア雑貨を扱う人気ブランドです。掛け布団も、機能性はもちろんのこと、デザイン性に優れたものが揃っています。高機能な中綿素材「シンサレート」を使用したモデルは、羽毛の約2倍の暖かさを持つとされ、薄くても高い保温性を発揮します。また、リバーシブルで使えるデザインや、お洒落な布団カバーとセットで販売されている商品も多く、寝室のインテリアにこだわりたい方に支持されています。もちろん、家庭で洗える実用性も兼ね備えています。
- 中綿の素材: ポリエステル、シンサレートなど(モデルによる)
- 機能性: 高いデザイン性、高機能中綿(シンサレート)、洗濯可
- 価格帯: 手頃な価格帯〜中価格帯
- こんな人におすすめ:
- 寝室のインテリアやデザインにこだわりたい人
- 薄くて軽いのに暖かい布団を探している人
- お洒落な布団カバーも一緒に探している人
参照:LOWYA(ロウヤ)
公式サイト
ダブルサイズの布団選びで知っておきたい注意点
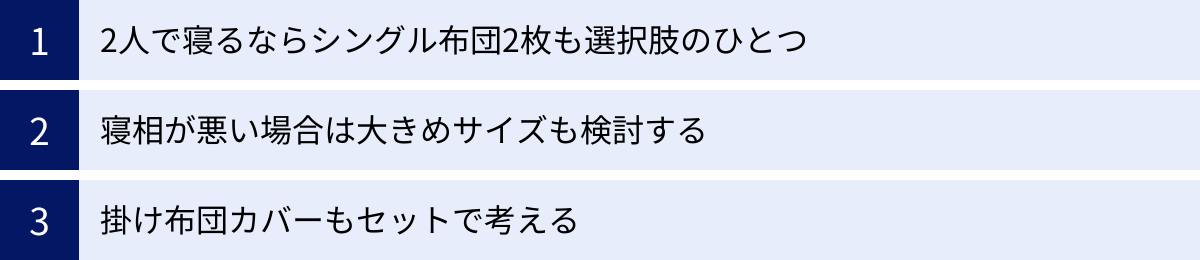
自分にぴったりの布団を見つけたと思っても、使い方や組み合わせによっては思わぬ落とし穴があることも。ここでは、ダブルサイズの布団を購入する前に、ぜひ知っておきたい3つの注意点を解説します。これらのポイントを事前に考慮することで、より満足度の高い選択ができるようになります。
2人で寝るならシングル布団2枚も選択肢のひとつ
「二人で寝るならダブルサイズ」という固定観念を一度リセットし、「シングル布団を2枚並べて使う」という選択肢を検討することは、睡眠の質を追求する上で非常に重要です。この方法は、ヨーロッパのホテルなどでは一般的なスタイルであり、多くのメリットがあります。
メリット:相手の動きが気にならず、好みの布団を選べる
- 睡眠の独立性確保: 最大のメリットは、パートナーの動きに睡眠を妨げられないことです。一方が寝返りを打っても、もう一方の布団が引っ張られることがありません。これにより、夜中に寒さで目が覚めたり、振動で起こされたりするストレスから解放されます。それぞれの睡眠サイクルを尊重し、朝までぐっすりと眠ることができます。
- 個別の好みに対応可能: 快適な睡眠環境は人それぞれです。暑がりの人は通気性の良い肌掛け布団、寒がりの人は保温性の高い羽毛布団を選ぶなど、各自が自分の体質や好みに合わせて最適な布団を自由に選択できます。重さの好みや、羽毛アレルギーの有無といった問題も、この方法なら簡単に解決します。
- 衛生管理のしやすさ: シングルサイズはダブルサイズに比べて軽量で小さいため、天日干しや布団カバーの交換といった日々の手入れが格段に楽になります。クリーニングに出す際の料金も安く済みます。
- 将来的な柔軟性: 将来的に別々の部屋で寝ることになった場合でも、そのまま各自の布団として使い続けることができます。ライフステージの変化に柔軟に対応できるのも大きな利点です。
デメリット:布団の間に隙間ができやすい
- 隙間からの冷気: シングル布団を2枚並べた際に、どうしても中央に隙間ができてしまいがちです。この隙間から冬場に冷気が入り込み、寒さを感じることがあります。
- 対策: この問題を解決するために、「すきまパッド(マットレスバンド付き)」という専用のアイテムがあります。T字型のパッドをマットレスの隙間に埋め、バンドで2つのマットレスを固定することで、隙間をなくし一体感を出すことができます。また、キングサイズやクイーンサイズの大きなボックスシーツで2つのマットレスをまとめて覆ってしまうのも有効な方法です。
- 見た目の一体感の欠如: 2枚の布団が並んでいる状態は、ダブルサイズ1枚に比べて見た目の一体感に欠けると感じる人もいるかもしれません。
- 対策: 日中は、ベッドスプレッドや大きなブランケットを上から掛けることで、ホテルのようにすっきりと見せることができます。
二人での快適な睡眠を最優先に考えるのであれば、ダブルサイズに固執せず、シングル2枚使いのメリットとデメリットを十分に比較検討することをおすすめします。
寝相が悪い場合は大きめサイズも検討する
ダブルサイズは大人二人用とされていますが、これはあくまで標準的な体格の人が、比較的おとなしく寝ることを想定したサイズです。もし、ご自身やパートナーの寝相があまり良くない場合や、体格が大きい場合には、ダブルサイズでは窮屈に感じ、結果として睡眠の質を下げてしまう可能性があります。
夜中に腕や足がベッドから落ちたり、相手を無意識に押してしまったりする経験がある方は、さらに大きいサイズの布団を検討する価値があります。
- クイーンサイズ(幅210cm × 長さ210cm)の検討: ダブルサイズよりも幅が20cm広くなるだけで、一人あたりのスペースに10cmの余裕が生まれます。このわずかな差が、寝返りの自由度を大きく向上させ、お互いのパーソナルスペースを確保することにつながります。
- キングサイズ(幅230cm × 長さ210cm)の検討: さらにゆとりを求めるならキングサイズです。小さなお子様と一緒に寝る「川の字」も、キングサイズなら余裕を持って実現できます。
もちろん、サイズが大きくなればなるほど、布団本体やカバーの価格は高くなり、選択肢も少なくなります。また、洗濯や干すといった手入れの手間も増大します。寝室に十分なスペースが確保できるかどうかも重要な判断基準です。
可能であれば、家具店や寝具専門店のショールームで、実際に様々なサイズのベッドに横になってみることをおすすめします。頭で考えるだけでなく、体でその広さを実感することで、自分たちにとって本当に快適なサイズがどれなのかを判断しやすくなります。
掛け布団カバーもセットで考える
快適な寝心地のためには、布団本体だけでなく、直接肌に触れる「掛け布団カバー」の存在も非常に重要です。布団選びの際には、必ずカバーのこともセットで考えるようにしましょう。
- サイズの確認は必須: 「ダブルサイズの布団だから、ダブルサイズのカバーを買えばいい」と安易に考えてはいけません。前述の通り、布団本体のサイズはメーカーによって微妙に異なる場合があります。幅190cmの布団に幅185cmのカバーをかけようとすると、布団が中で窮屈になり、本来のふっくら感が損なわれてしまいます。逆に、大きすぎるカバーでは、中で布団が動いてしまい、体にフィットしません。必ず購入する布団の寸法(幅×長さ)を正確に確認し、それに合ったサイズのカバーを選ぶようにしてください。
- 素材で寝心地が変わる: カバーの素材は、寝心地を大きく左右します。
- 綿(コットン): 吸湿性・通気性に優れ、肌触りが良い定番素材。高密度に織られたサテン生地はなめらかで、ガーゼ生地は柔らかく通気性が良いなど、織り方によって特徴が異なります。
- 麻(リネン): 吸湿・発散性に非常に優れ、熱を逃しやすいので夏場に最適。シャリ感のある独特の肌触りが特徴です。
- シルク: 人間の肌に近い成分でできており、肌への負担が少ない高級素材。なめらかで保湿性にも優れます。
- マイクロファイバー: 冬場に人気の素材。きめ細かな繊維が暖かく、とろけるような肌触りが魅力です。
布団本体の性能を最大限に活かすためにも、季節や好みに合わせてカバーの素材を選ぶことが大切です。
- 機能性とデザイン性: カバーの機能性もチェックしましょう。布団とカバーを固定するためのスナップボタンが何ヶ所付いているか(8ヶ所留めが一般的)、ファスナーが全開になるタイプか(布団の出し入れがしやすい)などは、日々の使い勝手に影響します。また、カバーは寝室の印象を決めるインテリアの一部でもあります。部屋の雰囲気に合わせて、好みの色や柄を選ぶ楽しみもあります。
布団を購入する予算には、良質なカバーの費用もあらかじめ含めて計画しておくことをおすすめします。
ダブルサイズの布団に関するよくある質問
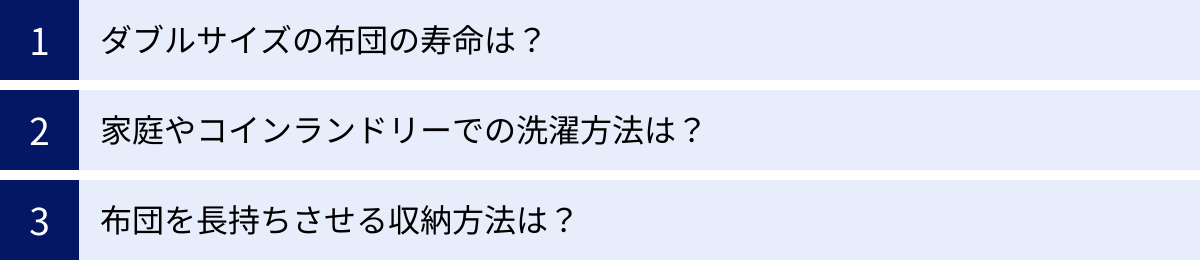
ここでは、ダブルサイズの布団に関して、多くの方が抱く疑問についてQ&A形式で詳しくお答えします。寿命や手入れの方法、収納のコツを知ることで、お気に入りの布団をより長く、快適に使い続けることができます。
ダブルサイズの布団の寿命は?
布団の寿命は、中綿の素材や使用頻度、手入れの状況によって大きく異なります。あくまで一般的な目安ですが、素材別の寿命は以下の通りです。
| 中綿の素材 | 寿命の目安 |
|---|---|
| 羽毛 | 10年〜15年 |
| 羊毛 | 5年〜7年 |
| 真綿 | 5年〜10年 |
| 木綿 | 3年〜5年 |
| 合成繊維 | 3年〜5年 |
高品質な羽毛布団などは、適切なメンテナンスを行えば10年以上快適に使える一方、合成繊維や木綿の布団は比較的寿命が短い傾向にあります。
しかし、年数だけで判断するのではなく、布団が発する「買い替えのサイン」に気づくことが重要です。以下のような状態が見られたら、寿命が近づいている可能性があります。
- かさ高(ボリューム)がなくなった: 新品の頃に比べて、明らかにふっくら感がなくなり、薄っぺらくなった。
- 暖かさを感じにくくなった: 中綿がへたって空気を含む層が減り、保温性が低下している。
- 重く感じるようになった: 汗や湿気が抜けきらずに蓄積し、布団全体が重くジメジメしている。
- 中の綿が偏っている: 布団の中で中綿がダマになったり、片側に寄ってしまったりしている。
- 匂いが取れない: 天日干しやクリーニングをしても、汗やカビの匂いが消えない。
- 側生地が破れたり、羽毛が飛び出してきたりする: 経年劣化により生地が傷んでいる。
これらのサインが見られたら、新しい布団への買い替えを検討するタイミングです。特に羽毛布団の場合は、専門業者による「リフォーム(打ち直し)」という選択肢もあります。これは、中の羽毛を取り出して洗浄・殺菌し、新しい羽毛を足して新しい側生地に詰め直すサービスです。愛着のある布団を再生させたい場合に有効な方法です。
家庭やコインランドリーでの洗濯方法は?
布団を清潔に保つための洗濯ですが、正しい手順を踏まないとかえって布団を傷めてしまう可能性があります。家庭とコインランドリー、それぞれの洗濯方法のポイントを解説します。
【洗濯前の共通の準備】
- 洗濯表示の確認: まず最初に、必ず布団についている洗濯表示を確認します。「洗濯機マーク」や「手洗いマーク」があれば家庭で洗濯可能です。「水洗い不可」のマークがある場合は、専門のクリーニング店に依頼してください。
- 布団用洗濯ネットの用意: 布団を傷みやねじれから守るため、必ず大きめの布団用洗濯ネットに入れます。
- 汚れのチェック: シミや特に汚れている部分があれば、液体洗剤の原液を直接つけて軽く叩くなど、前処理をしておくと汚れが落ちやすくなります。
【家庭での洗濯方法】
- 洗濯機の容量: ダブルサイズの掛け布団を洗うには、容量10kg以上の洗濯機が必要です。無理に詰め込むと、十分に洗えないだけでなく、洗濯機の故障の原因になります。
- 洗濯コース: 「大物洗いコース」や「毛布コース」など、水流が優しく、たっぷりの水で洗うコースを選びます。
- 洗剤: 洗剤が残りにくい液体タイプの中性洗剤がおすすめです。柔軟剤は、羽毛の撥水性を損なったり、吸水性を低下させたりすることがあるため、使用は避けた方が無難です。
- 乾燥: 自宅で干す場合は、M字型に干せる物干しスタンドなどを使って、風通しを良くするのがポイントです。完全に乾くまでには1〜2日かかることもあります。
【コインランドリーでの洗濯方法】
- メリット: 家庭用よりはるかに大型の洗濯機・乾燥機があるため、中綿までしっかり洗い、パワフルな熱風で乾燥させることができます。ダニ対策にも効果的です。
- 洗濯機の容量目安: ダブルサイズの掛け布団なら、22kg以上の大型洗濯機を選びましょう。
- 乾燥機の容量目安: 乾燥機はさらに大きい25kg以上のものを選ぶと、布団が中でよく回転し、乾きムラが少なくなります。
- 乾燥のコツ: 乾燥時間は60分〜80分が目安です。40分ほど経過したら一度取り出し、裏返したり畳み方を変えたりすると、全体が均一に乾きます。完全に乾いていないとカビの原因になるため、少し湿っていると感じたら追加で乾燥させましょう。
布団を長持ちさせる収納方法は?
シーズンオフの布団を正しく収納することは、寿命を延ばし、次のシーズンも快適に使うために非常に重要です。
【収納前の準備】
- 洗濯・乾燥は必須: 収納前には必ず洗濯またはクリーニングを行い、汚れや皮脂を完全に落とします。そして、何よりも重要なのが「完全に乾燥させる」ことです。少しでも湿気が残っていると、収納中にカビやダニが大量発生する原因になります。天気の良い日に2〜3日かけて天日干しするか、布団乾燥機を念入りにかけるなどして、中までしっかり乾かしてください。
【収納場所と収納方法】
- 場所: 湿気がたまりにくい、押し入れの上段やクローゼットの天袋などが最適です。床に直接置く場合は、すのこを敷いて空気の通り道を作ると良いでしょう。
- 収納袋: 通気性の良い不織布製の収納ケースがおすすめです。ビニール製の袋は通気性が悪く、湿気がこもりやすいため避けた方が無難です。
- 圧縮袋の使用に関する注意点: 省スペースで便利な圧縮袋ですが、羽毛布団や真綿布団への使用は避けるべきです。強い圧力で羽毛のダウンボールが潰れたり、羽軸が折れたりして、本来のふっくら感や保温性が損なわれ、元に戻らなくなる可能性があります。ポリエステルなどの合成繊維布団であれば、圧縮しても比較的復元しやすいですが、それでも長期間の圧縮は避け、収納時も圧縮しすぎないように注意が必要です。
【日々の手入れ】
オフシーズンの収納だけでなく、日常的な手入れも布団を長持ちさせる秘訣です。
- 起きたらすぐに畳まず、1時間ほど掛けておいて、寝ている間にかいた汗の湿気を飛ばしましょう。
- 週に1〜2回、天気の良い日に天日干しをします。素材によって適切な干し時間が異なるため注意が必要です(羽毛は片面1時間程度、木綿は片面2時間程度が目安)。
- シーツやカバーはこまめに洗濯し、布団本体の汚れを防ぎましょう。
まとめ
快適な睡眠を手に入れるためのパートナーである、ダブルサイズの布団。この記事では、その基本情報から選び方の詳細なポイント、具体的なおすすめ商品、そして購入後の注意点やメンテナンス方法に至るまで、幅広く解説してきました。
最後に、この記事の重要なポイントを振り返ります。
- ダブルサイズの基本を理解する: 標準サイズは「幅190cm × 長さ210cm」。一人で贅沢に使うか、比較的密着して眠りたい二人での使用に向いています。睡眠の質を優先するなら、シングル2枚使いも有力な選択肢です。
- 後悔しない選び方の5つのポイント:
- 中綿の素材: 軽さと暖かさの「羽毛」、吸湿性の「羊毛」、手軽さの「合成繊維」など、それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分のライフスタイルに合ったものを選びましょう。
- 季節に合った種類: 冬は「本掛け」、春秋は「合掛け」、夏は「肌掛け」。一年中使いたいなら「2枚合わせ」が便利です。
- 求める機能性: 清潔さを保つ「防ダニ・抗菌・防臭加工」や、手入れが楽な「洗濯可否」は重要なチェック項目です。
- 体への負担が少ない重さ: 重すぎず軽すぎない、自分が心地よいと感じる重さを選ぶことが快眠につながります。
- 予算に合った価格: 価格と品質は比例する傾向にあります。長期的な視点でコストパフォーマンスを考え、納得のいく一枚を選びましょう。
- 購入前の注意点を押さえる: パートナーとの睡眠を考えるなら「シングル2枚」という選択肢を。寝相が悪いなら「クイーンサイズ」の検討を。そして、布団本体と合わせて「掛け布団カバー」のサイズや素材も忘れずにチェックすることが大切です。
- 正しい手入れで長く使う: 定期的な洗濯や乾燥、適切な収納方法を実践することで、お気に入りの布団の寿命を延ばし、いつでも清潔で快適な状態を保つことができます。
数多くの情報をお伝えしましたが、最も大切なのは「あなた自身が、毎晩その布団で心からリラックスして眠れるか」ということです。この記事で得た知識を基に、様々な商品を比較検討し、ぜひあなたにとって最高の寝心地を提供するダブルサイズの布団を見つけてください。質の高い睡眠は、明日への最高の投資となるはずです。